en ja es pt
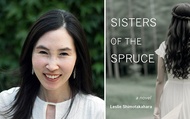
culture

第11回ニッケイ物語「いただきます3! ニッケイの食と家族、そしてコミュニティ」では、食がどのようにニッケイコミュニティをつなぐ役割をはたしているのか、代々受け継がれてきたニッケイのレシピにはどのようなものがあるのか、好きな和食やニッケイ料理は何なのかといった、いくつかのトピックについて考えてもらいました。
ディスカバー・ニッケイでは、2022年5月から9月にかけ、ニッケイ食に関するストーリーを募集し、10月31日までお気に入り作品に投票していただきました。全15作品(日本語:1、英語:8、スペイン語:6、ポルトガル語:1)が、ブラジル、カナダ、ペルー、米国から寄せられました。うち一つは、多言語による作品でした。
本シリーズへ寄稿してくださったみなさん、どうもありがとうございました。
編集委員の方々に、これらの投稿作品を読んでいただき、お気に入り作品を選んでもらいました。また、ニマ会コミュニティの方々にも、お気に入り作品に投票をお願いしました。下記がお気に入りに選ばれた作品です。
日本語:

深沢正雪さんのコメント
以前、日本から来たばかりの職人に、ブラジルではやりの〝変化球〟寿司についてコメントを求めたところ、「あれは日本料理ではなく、環太平洋料理ですね」とバッサリ切られた。だから、まるで別の国とは思えない体験談だと感じる。元祖日本にはないタイプの寿司店Temakeria(手巻き専門店)まであり、それをブラジル人がイタリアに進出させたと報道された。
ブラジル近海には寒流が流れておらず、脂ののった寿司ネタがほとんどないため、クリームチーズやソースなどで補強しないと旨くないという事情もある。日本と同じ食材が手に入らない環境で作るわけだから、当然、現地適応させるしかない。
このエピソードが俊逸なのは、現地の日本食事情だけでなく、世代が新しくなるほど文化が混ざり、旧世代も徐々にそれを容認する心境に変化するという移住者心理のパターンが表現されている点ではないか。
日本料理が外国で変化するのと同様、環境が違えば人も変わる。かと思えば、日本から離れて20年以上も経ち、頻繁に帰れない場所に住んでいると、むしろ母国の変化の急激さに戸惑うことも多い。取り残された気分になる。変わるのは、移住者の側ばかりではないと痛感する今日この頃だ。
英語:

ギル・アサカワさんのコメント
私は、「いただきます3!」に投稿されたすべての英語作品がさまざまな理由で大好きですが、ジャーナリズム専攻の大学生、キーラ・カラツさんによる『思考の糧―TikTokと卵焼き―』が特に気に入っています。このエッセイは、もともと今年6月に『羅府新報』に掲載されたものです。カラツさんは日系とドイツ系の四世で、日系アイデンティティや家族、文化、歴史についての一連の洞察力のあるエッセイをディスカバー・ニッケイに投稿しており、そのすべてが読み応えのある、惹きつけられる作品です。
このエッセイにカラツさんは、動画のけた外れな拡散を可能にしているTikTokなどのソーシャルメディアと彼女の世代の結びつきについて書いています。カラツさんによれば彼女のアカウントのフォロワー数は少なく、再生回数が最も多かった投稿はお父さんと一緒に作った卵焼きの1分間の動画で、視聴数は(人気クリエーターの基準ではかなり少ない)2,000回でした。しかし、この投稿に視聴者から熱心なコメントが寄せられたのです。
結局寄せられたコメントの多くは肯定的なものでしたが、カラツさんは否定的なコメントに言及し、現在の反アジア人感情の波を糸口に、食についてのエッセイを紡ぎ、「インターネットは新しい種類の悪意を生んだ。それは書き込まれるが、口にされることはない」と書いています。
カラツさんのストレートな表現と明瞭さは、卵焼きを作る喜び(と納豆や赤飯は好まないこと)を、現代のテクノロジーや社会正義についての示唆に富んだ思索に昇華させました。カラツさんは、ジャーナリストとして、文化思想家として、素晴らしいキャリアを築くことでしょう。それは、ニッケイコミュニティにとって楽しみな未来です。
念のために書いておきますが、私は赤飯も納豆も大好きです・・・もちろん卵焼きも!
スペイン語:

ハビエル・ガルシア・ウォング・キットさんのコメント
このエッセイには、歴史的、家族的、そして化学的にとても重要な視点がいくつも含まれていたので、お気に入り作品に選ばせてもらいました。この餅から、南米に移住した日本人、特に沖縄県出身者にとって「食」が非常に大切なものであったことが伺えます。また、このエッセイを読み、日本だけでなくペルーで何が起こったのかを知ることができました。さらに日系コミュニティーの伝統を受け継ぐための連帯意識と団結、そして、世界各地の日系人も行っているように、家業を始めるにあたり重視した文化的価値を改めて知ることができました。
ポルトガル語:

ニッケイ食 ー ブラジル風の和食
メイリ―・マユミ・オノハラ
テルマ・シライシさんのコメント
メイリーさんの思い出の料理や家族から受け継いだ習慣などについてのエッセイーはとても良かったです。
レシピに合わせて、現地にある食材を選び、新しい味が作り出されます。メイリーさんの家族にもこのようなレシピが代々受け継がれているのでしょう。ブラジルの国民料理の「フェイジョン」に日本の海藻を加えるレシピはとても気に入りました。私も今度、家で「フェイジョン」を作るときに試したいと思います。
ポップカルチャーの影響で日本料理はブラジルで注目されています。お寿司は現地の食材を取り入れ、新しい寿司のネタが開発されていますが、伝統的な寿司のレシピが生かされているとのこと。また、日本人がブラジルで育てた食材の多くが、このような新しい多様な組み合わせを可能にしていると、メイリーさんは述べています。
お弁当についてのお話は、家族と旅行の楽しみやおばあちゃんの思い出につながっています。特に、おばあちゃんが使っていたアルミ製の弁当箱を大事にしまってあることを聞いて、素晴らしいことだと思いました。
二つの国の影響を受けた家庭料理の味と独特のアイデンティティのお話です。
We have closed submissions for this series, but you can still share your story on Discover Nikkei. Please check our Journal submission guidelines to share your story!
編集委員の皆さんのご協力に、心より感謝申し上げます。
日本語
 深沢正雪さんは、日系ブラジル人コミュニティに詳しいジャーナリスト兼作家。1995年に群馬県大泉町でブラジル人と共に工場労働者として働いた経験をまとめた著書『パラレル・ワールド』は、1999年の潮ノンフィクション賞を受賞。現在サンパウロで『ブラジル日報』の編集長を務めている。
深沢正雪さんは、日系ブラジル人コミュニティに詳しいジャーナリスト兼作家。1995年に群馬県大泉町でブラジル人と共に工場労働者として働いた経験をまとめた著書『パラレル・ワールド』は、1999年の潮ノンフィクション賞を受賞。現在サンパウロで『ブラジル日報』の編集長を務めている。
英語 ギル・アサカワさんは、ジャーナリスト、編集者、日系・アジア系アメリカ人文化、歴史、アイデンティティの専門家。ブログ記事をnikkeiview.comへ掲載しているほか、著書に『Being Japanese American』がある。2022年8月には次作『Tabemasho! Let’s Eat! A Tasty History of Japanese Food in America』の出版を予定している。
ギル・アサカワさんは、ジャーナリスト、編集者、日系・アジア系アメリカ人文化、歴史、アイデンティティの専門家。ブログ記事をnikkeiview.comへ掲載しているほか、著書に『Being Japanese American』がある。2022年8月には次作『Tabemasho! Let’s Eat! A Tasty History of Japanese Food in America』の出版を予定している。
スペイン語 ハビエル・ガルシア・ウォング=キットさんは、ジャーナリスト兼大学教授で、雑誌『Otros Tiempos』のディレクターを務めている。著書として『Tentaciones narrativas』と『De mis cuarenta』があり、ペルー日系人協会の機関誌『KAIKAN』にも寄稿している。
ハビエル・ガルシア・ウォング=キットさんは、ジャーナリスト兼大学教授で、雑誌『Otros Tiempos』のディレクターを務めている。著書として『Tentaciones narrativas』と『De mis cuarenta』があり、ペルー日系人協会の機関誌『KAIKAN』にも寄稿している。
ポルトガル語 テルマ・シライシさんは、ブラジルと日本の食材を使った日本食を提供する「レストラン藍染」の料理長で、サンパウロにあるジャパン・ハウスの「藍染」でも指揮を取っている。真の日本の価値観と、地元で採れた季節の食材をベースに、温かいものと冷たいものをバランスよく組み合わせた料理がシライシさんのスタイル。在サンパウロ日本領事館の厨房を担当し、農林水産省を通じて日本政府から「日本食普及の親善大使」の称号を授与された。シライシさんは、この栄誉を受けたブラジル人初、世界でも数少ない女性料理人の一人です。
テルマ・シライシさんは、ブラジルと日本の食材を使った日本食を提供する「レストラン藍染」の料理長で、サンパウロにあるジャパン・ハウスの「藍染」でも指揮を取っている。真の日本の価値観と、地元で採れた季節の食材をベースに、温かいものと冷たいものをバランスよく組み合わせた料理がシライシさんのスタイル。在サンパウロ日本領事館の厨房を担当し、農林水産省を通じて日本政府から「日本食普及の親善大使」の称号を授与された。シライシさんは、この栄誉を受けたブラジル人初、世界でも数少ない女性料理人の一人です。
 ペルー日系人協会(APJ—Asociación Peruano Japonesa)は、ペルーの日系社会とその関係機関を代表する非営利団体。1917年11月3日に設立されたAPJは、日本人移民とその子孫の記憶を保存し、文化振興と福祉支援の活動を展開する他、教育と保健サービスの提供を行っている。また、ペルーと日本の文化、科学、技術交流を促進し、両国の友好関係を強化するための活動も行っている。
ペルー日系人協会(APJ—Asociación Peruano Japonesa)は、ペルーの日系社会とその関係機関を代表する非営利団体。1917年11月3日に設立されたAPJは、日本人移民とその子孫の記憶を保存し、文化振興と福祉支援の活動を展開する他、教育と保健サービスの提供を行っている。また、ペルーと日本の文化、科学、技術交流を促進し、両国の友好関係を強化するための活動も行っている。
 ワシントン州日本文化会館(JCCCW—Japanese Cultural and Community Center of Washington)は、1913年に日本人移民によってコミュニティの集会所兼日本語学校として建設された。この日本語学校は1902年に設立され、アメリカ本土最古の日本語学校として現在も運営されている。JCCCWは、展覧会や講座、諸活動を通じて、日本や日系アメリカ人の歴史と文化を保存し、紹介している。
ワシントン州日本文化会館(JCCCW—Japanese Cultural and Community Center of Washington)は、1913年に日本人移民によってコミュニティの集会所兼日本語学校として建設された。この日本語学校は1902年に設立され、アメリカ本土最古の日本語学校として現在も運営されている。JCCCWは、展覧会や講座、諸活動を通じて、日本や日系アメリカ人の歴史と文化を保存し、紹介している。
 ブラジル日本青年会議所は、国際青年会議所(JCI)のブラジルサンパウロ支部。この非営利団体には、新しいアイデアやコラボレーション、多様性を支持するあらゆる社会セクターからアクティブな市民が参加しており、JCIメンバーは、世界の未来に関心を寄せ、地域社会に影響を与えることに力を注いでいる。
ブラジル日本青年会議所は、国際青年会議所(JCI)のブラジルサンパウロ支部。この非営利団体には、新しいアイデアやコラボレーション、多様性を支持するあらゆる社会セクターからアクティブな市民が参加しており、JCIメンバーは、世界の未来に関心を寄せ、地域社会に影響を与えることに力を注いでいる。
 日本文化センター・博物館(NNMCC—Nikkei National Museum and Cultural Centre)は、より良いカナダを目指して、日本文化および日系カナダ人の歴史と遺産を尊重し、保存・共有することを使命としている。2000年9月22日以来、この文化スペースにて独自プログラムや展覧会、イベントを開催。NNMCCのコレクションには、歴史的・文化的に重要な2,600点以上の物品、41,000枚の写真、38メートルの文書資料、650の口述歴史記録、156本のフィルムなどがある。また、NNMCCは、毎年、家族や地域のストーリーをコレクションに追加し、日本人を先祖に持つカナダに住む人々の遺産を未来に伝えている。
日本文化センター・博物館(NNMCC—Nikkei National Museum and Cultural Centre)は、より良いカナダを目指して、日本文化および日系カナダ人の歴史と遺産を尊重し、保存・共有することを使命としている。2000年9月22日以来、この文化スペースにて独自プログラムや展覧会、イベントを開催。NNMCCのコレクションには、歴史的・文化的に重要な2,600点以上の物品、41,000枚の写真、38メートルの文書資料、650の口述歴史記録、156本のフィルムなどがある。また、NNMCCは、毎年、家族や地域のストーリーをコレクションに追加し、日本人を先祖に持つカナダに住む人々の遺産を未来に伝えている。
今回ロゴをデザインしてくれたジェイ・ホリノウチさん、提出原稿の校正、編集、掲載、当企画の宣伝活動などをサポートしてくれている素晴らしいボランティアの方々やご尽力いただいた皆さん、本当にどうもありがとうございます!
免責条項:提出された作品(画像なども含む)に関しては、DiscoverNikkei.org および本企画と連携する他の出版物(電子または印刷)に掲載・出版する権利を、ディスカバー・ニッケイおよび全米日系人博物館に許諾することになります。これにはディスカバー・ニッケイによる翻訳文書も含まれます。ただし、著作権がディスカバーニッケイへ譲渡することはありません。詳しくは、ディスカバーニッケイの利用規約 または プライバシー・ポリシーをご参照ください。