日本語出版への道のり
——日本語版が出る経緯と、イーコンプレス社から出版された理由はどのようなものですか。あまり、この種の本を手がけたことのない会社のようですが。
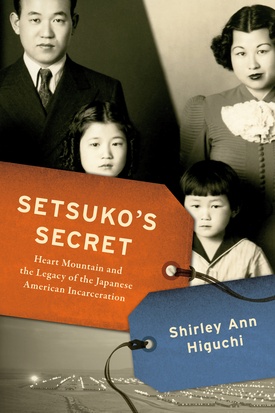
岩田: シャーリーさんが原著を出版した時、私がまったく知らないところで、さらに私よりもはるかにシャーリーさん、母で主人公のセツコさんらヒグチ家と深いつながりを持った人たちが邦訳を出版しようと動いていました。
日本語版作成で中心となった城西国際大学学長で薬学者の杉林堅次さんや、創薬ベンチャー「ナノキャリア」の宮嶋勝春さんたちです。お二人は若い頃、高名な薬学者だった、著者の父ウィリアム(ビル)・ヒグチさん(セツコさんの夫)の下、ミシガン大、あるいはユタ大の博士研究員(ポスドク)として指導を受けていました。杉林先生は当時、セツコさんにたびたび収容所生活について質問したものの、いつも話を上手にはぐらかされていたそうです。なぜ語ろうとしなかったのか、しかも語りたがらなかった収容所の跡地保存のため密かに寄付を続けていたのはなぜか、原著でその「秘密」が明らかになり、大きな衝撃を受け、ぜひ日本語で紹介したいと思ったそうです。
本を出版するのがなかなか大変な状況下で、医療・製薬関連に強い旧知の出版社に働きかけ、出版が実現しました。私自身、出版社につてがあったわけではないので、非常に恵まれていたと思います。
正義感と冷静な分析
——著者はどのような人で、「日系」に関わることについては、どのような考えを持っていると感じますか。
岩田: 正義感の非常に強い方で、「セツコの秘密」を解明するため徹底的に調査する姿勢には頭が下がります。まず、アメリカ政府が公式に謝罪した強制収容という過ちを繰り返してはいけないという思いが非常に強い。トランプ前大統領による排外的な移民政策にも非常に批判的でした。
一方で彼女は、1世、2世の強制収容が自分たち3世に与えた影響についても客観的に分析しています。強制収容の苦しみを「ガマン」「シカタガナイ」といった日本語で胸の内に秘めつつ、マジョリティーである白人社会に同化するために必死に働き、3世に社会での成功を求める姿勢がもたらした負の側面についてです。著者の兄がなぜ交通事故で死亡したのか。それは単なる事故だったのか、家族が公にすることをはばかる事実も冷静に分析しています。
——戦時中の日系人の問題についてある程度の知識がないと、読みこなすのに時間がかかると思いますが、翻訳にあたってどのような点に苦労しましたか。
岩田: 例えば、訳書のサブタイトルにもあるように強制収容という言葉が頻繁に出てきます。原著ではキャンプ(camp)という表現を使うときもありますが、キャンプと表記すると、やはりレジャーのイメージが強いので避けました。日系人の名前は全部カタカナ書きです。人物がたくさん出てくるので、読みにくいかもしれません。
英語をカタカナに直す時も迷うことが多々ありました。「Omura」は「オオムラ(大村)」と書くべきか、もしくは「オムラ(尾村または小村)なのか‥。その都度、いろいろ調べました。ディスカバー・ニッケイのオーラル・インタビューシリーズも参考にしました。グーグル・アースで墓地の墓石を探し当てて、(日本語的に)正しい読み方が判明したケースもあります。
心を打つエピローグ
——訳者として、読者として、感動した、あるいは印象的に残ったのはどういう点ですか。
岩田: もっとも印象に残ったのは「エピローグ」です。シャーリーさんは、外務省の招待で佐賀県の父方の祖父母の親戚を2019年に訪ねます。そこで祖父母の姪にあたる相川澄子さんと面会します。祖父母の苦労話を聞いたことを澄子さんは覚えていて、当時の様子をシャーリーさんに伝え、お互い抱き合って涙を流します。抱き合っている写真はエピローグに収められています。
シャーリーさんは、遠い日本の地方で家族のルーツの苦労を直接聞くことができたことに感謝するとともに、なぜ直接自らの家族からではなく、日本の親戚を訪ねてまでしないとそういう話が聞けなかったのか、日系人の「さが」ともいうべきものを痛感します。
実は、さすがに相川澄子さんを「スミコ・アイカワ」とは書けないので、何とか漢字を調べようと関係者に当たったところ、澄子さんが昨年、お亡くなりになっていたことが分かりました。澄子さんの息子さんと連絡が取れたため、翻訳書を送ったところ、シャーリーさんと抱き合っている写真を見て、自分の母親があんなに感情をあらわにしているのを見たのは初めてで驚いた、と連絡してくれました。それほどシャーリーさんと澄子さんにとって、短い面会は尊いものだったのか、と感じさせられました。
——今後、記者として日系の問題で取り組んでみたいテーマはありますか。
岩田: 「セツコの秘密」は、戦時ヒステリーがもたらした人種差別によって日系人がどれだけ苦しみ、それを克服し、国家がそれを過ちと受けとめた歴史が克明に描かれています。作品からは、こうした負の歴史を繰り返してはいけないというシャーリーさんの強い思いが表れています。
しかしどうでしょう。コロナウイルスという疫病との戦いでは、トランプ前大統領が自らウイルスを「チャイナ・ウイルス」と呼んでアジア系憎悪をかき立てました。今、米国では米中対立の余波により、保守的な州で中国人による不動産取得を禁じる法律が次々と成立しました。19世紀末の中国人排斥法成立当時、あるいは20世紀初頭、日本人移民を農業から排除するためにカリフォルニア州で成立した排日土地法を彷彿させます。
また、当時、将来の人口爆発に備えて移民を奨励した日本は今、急激な少子高齢化に苦しみ、移民を受け入れる側になっています。来年は、1924年に施行された排日移民法から100年の節目です。日本政府による入植者植民主義の歴史やアメリカの過ちなどを振り返りつつ、アメリカだけでなく、世界の日系人の現状と将来について考えていきたいと思っています。
© 2023 Ryusuke Kawai












