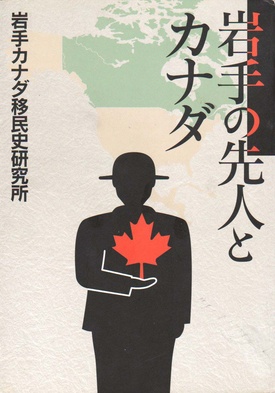第一次世界大戦の後、日本は国際連盟に加盟し、日英同盟は破棄された。日英同盟の延長に関しては、英国自治領カナダの執拗な反対があった。カナダは英国から距離を置き自治権を強化し、安全保障のために米国との友好関係をより重視するようになったのである。
すでに、日本の経済力と軍事力の増大や露骨な拡張主義は、西洋列強の脅威となっていた。彼らの警戒心が人種差別意識によって増幅され、その矛先が北米の日系社会に向かったのは当然の帰結だったかもしれない。
1920年代、BC州政府は日系人の漁労許可証の4割停止を断行した。ヘネー農会の井上次郎は見兼ねて、「落伍者をだしては日本人の恥だ」と失業者を迎え入れた。だが、この善意はいわば仇となって返されることになる。漁業から転じてきた人たちは、ヘネーのリーダーたちが基督教に依拠し同化を目指していることに反旗を翻し、仏教会を設立した。これは、日本の戦争協力に否定的だった従来のヘネー共同体の分裂を意味した。
一方、バンクーバーの日本人会は領事館から「保証権」という名目で資金援助を受けていた。賭博場「昭和倶楽部」支配人・森井悦治は、日本人会の中に「時局委員会」を設置し、米国による日本への輸出禁止に抗して、アルミホイル、医薬品、慰問袋を集めて密かに祖国に送っていたという。RCMPがそれを察知しないはずはない。『Mutual Hostages(引き裂かれた忠誠心)』の著者・戦争史家ジャック・グラナシュタインは、BC州民に渦巻く日系人に対する怒りは危険な状態で、「強制収容は日系人保護のために必要だった」としている。
ところが、1940年10月の段階で、『ニューカナディアン』編集長トーマス(トム)・クニオ・ショーヤマと日本人労組事務局長・梅月高市(日刊『民衆』編集者兼任)を証言者とするBC州特別諮問委員会では、巷間で噂となっている「不忠誠」も「地下工作」も「日系人の中には見受けられない」という結論に達していた。
また、日米開戦後の1942年1月、RCMP代表者が「工作容疑者の数人はすでに収容されており、これ以上日系人を逮捕する必要はない」と報告している。にもかかわらず、2月末には次々と閣議決定による緊急勅令が発令され、日系人全員の強制移動のみならず日系人の財産処分(家、土地、漁船を含む)など踏み込んだ政策になった。「保護」を理由に動産・不動産の「没収」を断行した裏には、日系人をカナダから追放するという最終的な目的があった。
ここに、後のリドレス運動で争点となった「人種差別に基づく誤った政策」があったことは否めないのである。
英語のできない一世にとって政局を知る情報源は日系新聞のみだったが、日本ではいくつかの通信社が同盟通信に統合され対外情報は一元化されていた。日系社会は、アジアを西洋列強支配から解放するという大義のもとに侵略を進める日本政府の策動に乗っていった。1937年、南京虐殺の惨状が新聞で報道されると、北米の中国系社会は反発して国民党を支持する集会を開いた。日本に対する北米社会の怒りは、即座に日系人への差別に転化された。
一方、日本政府も手をこまねいて黙していたわけではない。日本側の主張を海外で発信するために、各地で国策の英字新聞を発行した。日系米人二世ビル・ホソカワが国策新聞に関わっていたことは本人が認めている。実は、カナダでも領事館が資金提供して同じことをしていたのだ。
菊池孝育著『岩手の先人とカナダ』(2007)の「ニューカナディアン紙発刊をめぐって」の章には、開戦時に副領事だった小川徳助氏とトロント在住二世・沖広洪一郎氏が、1970年代に交換した私信が掲載されている。「支那事変が拡大し日本及び日本人に対する風当たりが強く非難が烈しくなったので之に対する緩和の一策として、東信夫・大内雄の両君と計り表向きは二世の啓発紙として小新聞を刊行することとし・・・」、「領事館との関係は極秘とし大戦発生と同時に同紙に対する補助関係の領事館会計簿(毎月三百弗補助)と小生の日記を焼却して終いました」とある。
同紙の初代編集長は東信夫だったが、彼は1939年4月に、突然、満州の奉天で発行されていた国策新聞『満州日日新聞・The Manchurian Daily News』の編集者の職を得て渡満した。彼の後を継いだのがトム・ショーヤマだった。そして開戦を迎えた。ほとんどの『ニューカナディアン』の読者は二世だったが、ショーヤマは日系カナダ市民連盟(JCCL)と日本領事館の間にあって、極めて難しい立場に立たされていたはずだ。
一方、宮崎孝一郎さんも、新聞記者として開戦から7月の家族総移動まで揺れ動き続けた日系コミュニティを冷静な目で自家版『明けゆく百年』に書き残している。宮崎さんは同じカナダ生まれの二世でも、カナダで民主主義教育を受けた二世と、日本で忠君愛国の精神を叩き込まれてきた帰加二世との間には大きな亀裂があることを見て取っていた。だが、日系人全員に対する強制疎開令は、この二つのグループに「家族単位の集団移動の要求」という共通の目的を与えて暫定的に行動をともにさせたのである。これは人権意識に基づくカナダの市民運動の勝利となって結実した。
その一方で、「日本領事館は日系二世の手玉にとられたことになろう」と菊池は記している。編集長トム・ショーヤマのカナダに対する忠誠心は揺るがなかったのだ。戦後、ショーヤマは経済顧問として、サスカチュワン州首相トミー・ダグラスに仕え、そして、1975年には連邦議会においてピエール・トルードー内閣で財務省政務次官に抜擢された。そのニュースを伝えるトロント・スター紙には、彼の友人の弁として「過去は一切語らない男だ」と書かれてある。「語らない」のではなく「語れない」事情があったのではないか。トム・ショーヤマは、発行継続を許された唯一の日系新聞ニューカナディアンの主筆として、自分たちのコミュニティ崩壊の危機を何とか最小限に食い止めようと、刻々と変わる情報の取捨選択を続けたのである。
一方、戦争捕虜として収容所にいた有賀千代吉は、日系人が戦後も恥として語らなかった日系社会の実相を赤裸々にその著『ロッキーの誘惑』に描いている。そのためか、同書は未だに英訳されず日系社会にも一顧だにされていない。筆者は、1992年にバンクーバーでNAJCが開催した「Home Coming・帰郷」会議で有賀さんの家族に会い、この本の英訳許可を願い出た。だが、その方は逡巡した後、「まだ迷惑のかかる人が存命なのでお断りします」と告げられた。
一方で、筆者は長い間この本のタイトルが謎だった。だが、何度か読み直すと、このタイトルが帝国日本をロッキー山脈に見立ているのではないかと思い始めた。「強硬派」と呼ばれた国粋主義者たちでロッキー山脈の美しさに魅せられたように、日本の戦勝を信じて続々と戦争捕虜収容所に吸い込まれていった姿が、この本のタイトルと表紙の絵で揶揄されているのである。
1967年、戦前の日系カナダ社会のボス的存在だった森井悦治が、日本から訪れた新聞記者にインタビューされている。齢82歳の森井が背筋を伸ばして、「・・・当時の私は、日本人同胞からは犬とののしられ、白人からはエージェントだといわれながら、総移動を無事に終わらせたことについて、いまでも間違っていたとは思っていません」(高見弘人『カナダの日本人』1967)」と語っている。森井をカナダ政府と日系社会とのリエゾンとして指名したBCSCは、森井の権威が一気に凋落したのを見て取り、彼と彼の息のかかった日本人会の幹部たちを速やかに移動させた。この時、工作容疑者の「枢要」が消滅したのである。
総じて、開戦から半年の間、驚天動地の状況にも日系社会は冷静に対処し、整然と総移動に応じたように見える。だが、その裏には、人権を守り民主主義を貫こうとした、反抗心と理性を兼ね備えた二世たちがいたことを銘記すべきだろう。こうして戦前の忠君愛国の一世リーダーたちは去り、二世の民主主義勢力がリーダーにのし上がっていった。
© 2022 Yusuke Tanaka