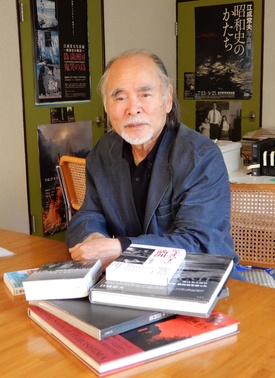戦後日本の隠れた歴史として
戦後の日本が忘れてきたものをとらえてきた写真家・江成常夫氏は、アメリカ人兵士と結婚してアメリカにわたった女性たちのありのままの姿をポートレートとインタビューでまとめた『花嫁のアメリカ』を1981年に出版、それまでメディアが見落としてきた時代と人々を世に知らせ話題を呼んだ。
戦争という日本の負の遺産を何らかの形で背負った人々の戦後に向かい合ってきた江成氏は、この後、戦後中国に残された日本人孤児についても、“アメリカの花嫁”の取材と同様に中国に足を運びインタビューと写真により彼らの戦後と実情をとらえ、作品を通してその声を代弁してきた。
そして最初の花嫁取材から20年後、彼女たちを再び取材し『花嫁のアメリカ 歳月の風景1978-1998』をまとめ、時代の流れと世代の移り変わりのなかで、日本や日本人とはなにか、日系とはなにかを浮かび上がらせたが、昨年、『花嫁のアメリカ』と『花嫁のアメリカ 歳月の風景1978-1998』の2作をあわせた新たな編集による『花嫁のアメリカ[完全版]』が論創社(東京千代田区)から出版された。
“花嫁”に関する2作品とその世界については、第22回で紹介したが、改めてその作品が生まれる背景などについて、神奈川県相模原市の自宅に江成氏を訪ね、話をきいた。
* * * * *
——最初に取材をはじめたとき、どのようにして「花嫁」を訪ね歩いたのですか。
江成: 1978年10月にロサンゼルス郊外のガーデナという町にワンルームのアパートを借りて、そこを拠点に花嫁を探し、訪ねた。サンフランシスコからサンディエゴまで1年間で車で3万5000キロほど走り、合計120人くらいに会った。
訪ねると、あまり話したくない人もいたし、門前払いされることもあったけれど、その労に悔いなかった。どんな人にどんな話を聞けるかが知りたいという気持で、訪ね歩き一人の花嫁に出会ったことを手ずるにして、別の人を紹介してもらったりした。
—そこでまず何を感じましたか。
江成: まず見えたのは、宗教ですね。結局、日本を離れた彼女たちは頼る人がいないから、何かに頼らざるを得ない。それが宗教で、100%といっていいくらいなんらかの宗教に頼っている姿があった。信仰につながっていた。宗教のなかで一番多かったのがNSA(創価学会)です。
カトリックなどほかの宗教を信仰している人もいたが、ほとんどは新興宗教的なものだった。そのルートで花嫁たちを紹介してもらうことがあった。
——『アメリカの花嫁』では、彼女たちの語ったままの言葉がつづられていますが、読者を惹きつけた点の一つが、この言葉だったと思います。
江成: 彼女たちの言葉は、英語と日本語がちゃんぽんになっている。基本は日本語だが、日常は英語で、だから接続詞とか、簡単な英単語がひょこひょこでてくる。これがぼくには新鮮だったし、また悲しくも感じた。
しかし同時に、その言葉には惹かれるものがあった。とにかく人間性の豊かさ、日本では、ともすれば差別された女性たちの気持が伝わってきた。だからそれを、こちらの主観を入れずにそのまま本では紹介したところ、花嫁の心境を素直に表わすという効果をもたらしたようだ。
——出版当時の評価はいかがでしたか。
江成: 写真だけでなく言葉をつけたほうがいいということで、花嫁の言葉を、長い人は長いままにまとめ、写真と言葉を並べたのだが、この年の大宅壮一ノンフィクション賞の候補になった。また、井上ひさしさんが大きく新聞で取り上げてくれた。情報としての目の向け方に価値があったのだろう。
——彼女たちの日本に対する思いはどうだったでしょうか。
江成: 日本人という心、愛国心というのは、つらい思いをした人間こそ強い。取材した人たちの中で、捨てられたようにされたり、二度と日本に帰らないという人はいなかった。なかにはぼくが行くと、お寿司などつくって待っていてくれた人もいた。そういう行為は、日本人としてしっかり生きなければいけないという彼女たちのプライドに繋がっている。日本人であるという意識が強いことは、子どもの育て方にもあらわれていた。
20年後に同じ人(花嫁)を訪ねると、子どもに対する期待が愛国心に繋がっているということがわかったので、(日系2世である)子どもがどう成長しているのかをぜひ、かつて彼女たちのことをさげすんでいた人もいた日本に向けてぼくは伝えたかった。
しいたげられた人ほど母国のことを思っているという点では、中国の戦争孤児もまったく同じ。満州にソ連が攻め込んでから、置き去りにされてしまった子どもたち。ぼくは4年にまたがりそうした戦争孤児を訪ねた。彼らは親などはわからないが、ものすごく日本人に会いたがる。ぼくが行くと名刺をすごく欲しがる。日本にいる日本人とのつながりをほしがっていた。日本に帰りたいという気持ちの表れだ。
——日系2世である、子どもたちとの関係や教育についてはどう感じましたか。
江成 子どものことに関しては、彼女たちが日本人の母親であることの誇りを持っていると感じた。日本人が忘れたようなエチケットも教えられているようで、母親としてのしつけもしっかりしているようだった。
日本では戦後本来の日本の文化が忘れられているようだが、一方、花嫁の子どもたちは、しっかりした育て方をされているようにみえた。また卑屈なところはなにもない。この点は、アメリカ社会のもつ影響もあるのだろう。
——夫が軍人で転勤も多く、彼女たちはコミュニティーとの関わりが難しかったのでは?
江成: そうですね。ただ同じ出身地の繋がりはあった。たとえばサンディエゴは第七艦隊の寄港地で、長崎、佐世保とつながっていて、花嫁さんは長崎の人が多い。そこでは、長崎県人会ができて、花嫁同士の交流がある。ぼくもパーティーに招かれたことがあるが、彼女たちの夫も一緒に日本食を囲んでのパーティーだった。
サンディエゴには、日本の自衛艦が寄港するが、夫が海軍にいたナオミ・キャンベルさんという人は、夫の艦が出港するときは涙で見送ったことなどなかったけれど、日本の自衛艦がサンディエゴに寄港して去るときは涙が出るといっていた。
|
江成常夫(えなり・つねお) 1936年、神奈川県相模原市生まれ。写真家・九州産業大学名誉教授。1962年、毎日新聞社入社。64年の東京オリンピック、71年の沖縄返還協定調印などの取材に携わる。74年に退職し、フリーに。同年渡米。ニューヨーク滞在中に、米将兵と結婚して海を渡った「戦争花嫁」と出会い、78年カリフォルニアに彼女たちをたずねて撮影取材。以後、アジア太平洋戦争のもとで翻弄され、声を持たない人たちの声を写真で代弁し、日本人の現代史認識を問い続ける。写真集に『百肖像』(毎日新聞社、1984年・土門拳賞)、『まぼろし国・満洲』(新潮社、1995年、毎日芸術賞)、『花嫁のアメリカ 歳月の風景』(集英社、2000年)、『ヒロシマ万象』(新潮社、2002年)、『鬼哭の島』(朝日新聞出版、2011年)、『被爆 ヒロシマ・ナガサキ いのちの証』(小学館、2019年)など。著書に『花嫁のアメリカ』(講談社、1981年、木村伊兵衛賞)、『シャオハイの満洲』(集英社、1984年、土門拳賞)、『記憶の光景・十人のヒロシマ』(新潮社、1995年)、『レンズに映った昭和』(集英社新書、2005年)など。(論創社のプロフィールを参考) |
© 2023 Ryusuke Kawai