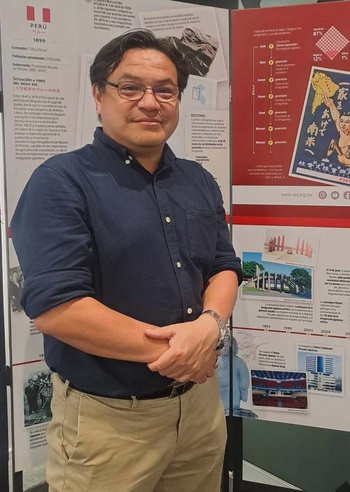立命館大学環太平洋文明研究センターは、二つの団体、ペルーカトリック大学のリヴァ・アグエロ研究所とペルー日本人移住資料館「カルロス・チヨテル平岡」を管轄しているペルー日系人協会と協定を締結した。この協定はペルー日本人移住と日本との関係について研究事業が促進するもので、ダニエル・サウセド・セガミ教授の多大な働きかけによるものである。
ダニエル・サウセド・セガミ博士はどのような方?
ダニエルはペルー生まれの日本在住22年になる研究者兼大学教員である。以前インタビュー1で、ニッケイ人的要素(またはアイデンティティ)について関心を持ったのは、ペルーで義務教育を受けていた時だという。「馬鹿タレ」、「仏壇」といった日本語を使うと、非日系のクラスメイトからそれはなんのことなのかとよく聞かれたことがきっかけだという。
大学に進学してからも、ニッケイとは何なのかといったことへの関心は続き、自身の家族史だけではなく、ペルーへの日本人移住者全般に興味を持つようになった。結果、これが自身の研究テーマとなった。
ペルーカトリック大学考古学科を卒業後、日本でさらなる学位を得て、現在立命館大学の准教授を務めるダニエルは、リマの母校のリヴァ・アグエロ研究所の研究コーディネーターでもある。ダニエルは、65年前に設立された著名なアンデス考古学日本調査団(参照:関雄二研究室サイト)の日本在住者の唯一のペルー人メンバーである(現在の研究事業は、「社会的記憶の観点からみたアンデス文明史の再構築」だという)。
日本定住前の大学院奨学生としての経験
ダニエルが日本を初めて訪れたのたは2001年で、ペルーカトリック大学考古学科の学部生の時だった。大阪大学との交流事業の一環として、一年間、日本で奨学生として勉強する機会を得た。
そのときの指導教官はアンデス文明史研究者の染田秀藤先生で、後にアンデス考古学日本調査団の代表となる関雄二博士を紹介した。ダニエルは、両氏から大学院進学についてアドバイスを受けたが、当時まだどのような道へ進みたいか決められず、学部を卒業するためにペルーに戻った。
2003年にペルーの大学を卒業したダニエルは、日本政府(内閣府)主催の「世界青年の船」に二ヶ月間参加した。その後すぐに、ペルー熊本県人会留学プログラムを通して、熊本大学で一年間留学した。こうした経験を経て、ダニエルは岡山大学大学院に進学することを決意した。
留学と失業がもっとも大きな心配事
「修士課程に入れば、奨学金がもらえると、世間知らずの僕は思っていました」とダニエル。しかし、奨学金の多くは学部か博士課程用だと知ったのは入学したときで、結局修士課程二年目まで奨学金を得ることができなかった。しかもその奨学金は「これまでで一番少なかった」と彼は振り返る。生活費が足りなかったので、「日本人学生と同じように」アルバイトをし、両親の支援を受けて、勉強を続けたという。
博士課程に進学すると、状況は好転した。文科省の日本学術振興会の奨学金を取得することができたので、大学で授業を受けるだけでなく日本でのフィールドワークにも従事することができるようになった。「この学術振興会の研究費は若手研究者を支援するドクターコース用の、奨学金で、二年間の生活手当と授業料を負担してくれる他、研究費も別途支給してくれた」とダニエルは嬉しそうに話してくれた。
博士課程終了後の一番の懸念は職を得ることだった。博士課程を取得した国立民俗学博物館には、学部生も修士課程院生もいなかったので、実習生の担当または教員としてのポジションはなかった。2013年、知り合いのツテで京都にある同志社大学でスペイン語講師として働くことになった。
日本考古学調査団、唯一のペルー人メンバー
日本はペルーの遺跡の保全や研究に、装備や技術の提供したり多くの専門家を派遣するなどし、投資・貢献してきた。
1958年からペルーで発掘調査等を行なっている「アンデス考古学日本調査団」は、最も長期的に発掘を行っている外国調査団として評価されている。ダニエルは唯一の日本在住のペルー人メンバーである。
ダニエルは、関雄二教授からこの調査団によるペルー遺跡研究について教えてもらった。関先生はこの研究事業の団長で、2008年から2014年の間ダニエルさんが博士課程に在籍していた国立民俗学博物館の名誉教授でもある。
博士課程は通常3年くらいだが、ダニエルはペルー北部ランバイエケ地方にあるシカン資料館(神殿発掘地)に定期的にフィールドワークへ行っていたので、博士論文を終わらすまでに7年もかかった。
“私はタコのように活動”
現在ダニエルは、複数の研究事業に同時に関わっている。一つは関雄二先生と共に遺跡分析センターを立ち上げて行っている、ペルーのカハマルカ県のパコパンパ調査である。、もう一つは、個人で参加しているパブリック考古学プログラム「Huacas de La Molina」(ラ・モリナ地区古代給水システムの研究)での歴史研究である。その他にも様々な団体との研究事業にも関わっている。
ダニエルは、外国語としてのスペイン語を教えてもいるが、考古学者、文化人類学者として、専門分野に関連したテーマについて多様な研究を行っている。
立命館大学での活動
複数の専門分野を網羅しているダニエルは、これまでいつくかの大学で教鞭をとってきた。関西学院大学、神戸市外国語大学、そして現在研究者及び准教授を務める立命館大学である。
立命館大学では、2017年にスペイン語やラテンアメリカ文化を教えるため嘱託教員として採用され、2020年からは政策科学部の准教授に就任した。それまでの研究者及びスペイン語ネイティブ教員としての経歴が、大学が求めていた人材と完全にマッチングしたのである。
今年(2024年)に入り、ダニエルはこの大学のスペイン語教育の主任として、スペインとラテンアメリカから9人、日本から23人になる合計32人の教員を束ねている。中南米出身は5名いるが、准教授は唯一のペルー人、ダニエルのみである。
立命館大学では、環太平洋文明研究センターと歴史都市防災研究所で研究者としても活動している。この環太平洋文明研究センターが、ペルーの二つの研究機関と研究協力協定を締結したのである。
注釈:
1. ダニエルのインタビューは、ペルー日系人協会の機関誌「KAIKAN」のエンリケ・ヒガ記者によって行われ、ディスカバーニッケイのサイトに掲載されたもの。
© 2024 Milagros Tsukayama Shinzato