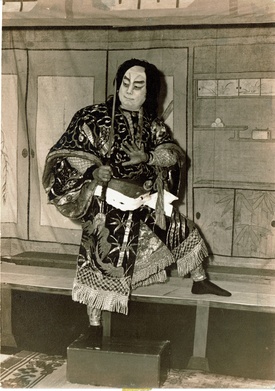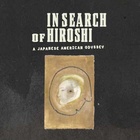ある三世は、日本に行ったとき、おとなしい人や内気な人、騒がしい人や攻撃的な人、礼儀正しい人や失礼な人など、いろいろなタイプの日本人がいて嬉しかったと私に話してくれた。「日本の日本人は、自分を表現する人間的行動のあらゆる範囲を持っています」と彼は言った。「私たちアメリカ人は、スペクトルの狭い範囲にのみ自分たちを限定しています。」
子供の頃、父と彼の一世の友人たちは酒好きで楽しいことが大好きなグループだったことを思い出しました。彼らは仕事と同じくらい一生懸命遊び、個々に個性がありました。全員が正直だったり、完全に信頼できるわけではありませんでした。グループとして彼らは、比較的静かでおとなしく、当たり障りのない二世の子供たちとは対照的でした。第二次世界大戦は一世にとって経済的な大惨事であり、彼らのほとんどはそこから立ち直ることはありませんでした。しかし、ほとんどの一世にとって、戦争は忠誠心に関する葛藤をもたらさず、自分自身に対する気持ちにも影響を与えなかったようです。
私が話を聞いた一世たちは、生き延びることが一番の心配だったと話した。白人に雇われていた日本人の多くは、戦争が勃発すると職を失い、生活の糧を失った。そして「疎開」が始まったとき、絶滅収容所に送られるのではないかと恐れた人もいた。殺される代わりに、食料と住まいを与えられたことは、彼らにとって大きな安堵だった。
戦争の政治的側面に対する彼らの感情は、ほとんどの場合明らかだった。シアトルに住むアメリカ教育を受けた一世の佐々木昭介氏は次のように語った。
「米国は日本を刺激し、日本に先制攻撃を強いることに成功したと私は感じました。日本は米国ほどの規模の国と戦えるほどの工業力はなく、打ち負かされる可能性が高かったので、私は悲しくなりました。私は日本人を責めませんでした。日本はこの国からの何らかの和解を求めてひざまずきましたが、この国の唯一の反応は私たちに唾をかけることでした。私は悲しくなりましたが、日本がこれ以上いじめや侮辱を受けることを拒否したことにある種の誇りを感じました。」
ササキ氏は、戦時中の日本人強制収容に協力した日系アメリカ人市民連盟を軽蔑していた。「彼らは四つん這いになって白人のブーツを熱心に舐めていた」と彼は語った。
私がインタビューした他の一世たちは、ササキほど米国や日系アメリカ人市民連盟に対して厳しい態度をとっていなかったが、戦争に関して恥や罪悪感、あるいは不安が消えないといった感情を表明した者はいなかった。戦争による精神的トラウマは、主に二世が受け継いだものと思われる。
カリフォルニア州ハリウッドで精神科ケースワーカーとして働く二世のベベ・トシコ・レシュケさんは、戦時中は子供だったが、収容所にいたころ、3人の憲兵が禁制品の捜索のために家族の車室に入ってきたことを覚えている。
「私は、侵害されたと感じました」と彼女は語った。「私は今でも、権威を信頼することに問題を感じています。誰でも、そのような支配力を持つことができ、それがあっという間に起こり得るのです。日本に関するこれらの否定的な記事を読むと、今でも感情的な反応が起こります。『ああ、なんてことだ、アメリカ国民がまた私たちに背を向けている』と思います。今回は行きません。それが私の方針です。今回は戦うつもりです。私はアメリカ自由人権協会に加入しました。それが、起こったことに対する私の恐怖に対処する方法です。」
私はどの収容所跡地も訪問したくなかった。しかし、最終的にナショナル ジオグラフィックの編集者が、ヒラ川移住センターの跡地を探してみるべきだと私を説得した。サビーヌが一緒に行こうと申し出てくれたときは嬉しかった。ヒラに行くのが怖くなってきたからだ。私は、文明から何マイルも離れた砂漠をランドローバーでさまよっている自分の姿を思い浮かべた。
四輪駆動車を借りようとしたが、フェニックスに着いたときには借りられなかった。ポケットナイフは必ず持参した。ヘビに噛まれたときに切開するのに必要になるかもしれない。コーラ6本パックを買って車のトランクに入れておくことを心に留めておいた。砂漠で迷っても、しばらくはこれで持ちこたえられるだろう。
ホテルに着いたとき、胸が詰まって気管支炎になりそうだと分かりました。大変なことになりそうです。病気で寝込む前にキャンプ場に行かなければなりませんでした。フェニックスに住む兄のニマシに電話すると、彼もキャンプ場を見たいと言いました。彼はフェニックスに40年近く住んでいて、一度もキャンプ場を訪れたことがありませんでしたが、道順を教えてくれる人を知っていると言いました。
私たちは朝食でニマシと妻のサダコに会った。私は戦後ニマシに数回しか会ったことがなかった。70歳になっても庭師として働いていた。痩せていて、日焼けして健康そうだった。
後で分かったことだが、キャンプ場はフェニックスの南約 30 マイルのところにあり、フェニックスからツーソンまでの高速道路はそこから数マイル以内の距離を通っていた。しかし、まず池田氏を訪ねて道順を尋ねなければならなかったので、遠回りをしなければならなかった。
池田さんは、私たちがヒラキャンプに集められた当時、フェニックスに住んでいました。40年前、電車の窓から外を眺め、ヤシの木陰にある赤い瓦の家々を見て、自分たちもそのうちの1軒に住めるのではないかと願ったことを思い出しました。当時、フェニックスにはそのような家に住んでいた日本人がいて、池田さんもその1人でした。池田さんは何度もその場所を訪れていたようで、私たちに良い道案内をしてくれました。
私たちはチャンドラーという町を通り抜けました。その名前は聞き覚えがありましたが、以前見たことはなかったのです。そして、ヒラ川インディアン居留地に入りました。道路の両側には灌漑用水路があり、レタス、アルファルファ、穀物の畑がありました。
ヒラにはキャンプが 2 つあり、1 つはカナル、もう 1 つはビュートと呼ばれていました。私たちがいたビュート キャンプの場所を見つけるのに苦労しましたが、あちこちに散らばっているコンクリートの基礎ブロックと、かつては食堂の床だった大きなコンクリートの板で場所を特定することができました。セージブラッシュはキャンプ地に再び広がり、高さ 7 フィートにまで成長していました。私たちは歩き回って見回りましたが、誰も言うことはありませんでした。
翌日、サビーヌと私はその場所に戻りました。私の胸の調子は良くなったので、子供の頃よく登った丘の頂上に行きました。ゴロと私が座っていた場所をサビーヌに見せたところ、ゴロは中国の人々がなぜ逆さまになっていないのかを説明してくれました。丘の頂上からは、耕作地の緑の四角い場所が見えました。近くには牛の牧場があり、馬に乗った男が数頭の雄牛を追っているのが見えました。私が子供の頃は、見渡す限り砂漠の荒野しかありませんでした。彼らが私の美しい砂漠を台無しにしていることに、私は強い憤りを感じました。その時、私は自分がヒラを愛していたことに気づきました。
最初の数週間は砂漠が怖かったのですが、新しい環境に慣れてくると、私が恐れていたのはギラではなく、むしろ外の世界、つまり私たちが追い出された世界でした。
私は、恐怖が私から消えることはなく、生涯私を悩ませてきたことに気づき始めた。なぜ私は知事に質問したかった記者に向かって叫んだのか?それは、彼が私を怖がらせたからだ。彼はノートを取り出し、どういうわけか私が言ったことをすべて書き留めていた。彼は事実上、私が知事と共謀して報道機関と国民を欺く裏切り者だと非難していたのだ。
1942 年、白人当局は日系アメリカ人全員が不忠誠者というわけではないことを認めたが、忠誠者から不忠者を選別する方法はない、と彼らは言った。不可解な東洋人という固定観念は西洋人の心に深く根付いていたため、誰も真剣に疑問を抱かなかった。そのため、私たち全員が容疑者とされ、家から連れ出されて強制収容所に入れられた。
ようやく書き始めると、当初書きたかった記事が書けなかった。つらく苦い過去を乗り越えた、現代のホレイショ・アルジェリア人であるアジア系アメリカ人の勇敢なグループの明るい物語だ。そのような成功物語を裏付ける証拠や資料はたくさんあり、書けたはずだが、私には無理だった。日系アメリカ人の経験の苦い部分から目をそらすものだっただろう。私たち、特に二世の多くが感情的に病んだり、不自由になったりしているときに、日系アメリカ人コミュニティに明るい顔を描くことはできなかった。
結局、ナショナル ジオグラフィックは、大量投獄とその心理的影響についてのみを扱った私の記事を拒否しました。その後、ニューヨーク タイムズ マガジンは「日系アメリカ人であることの不安」というタイトルの要約版を掲載しました。
サンセイ編集長のグラント・ウジフサ氏と話をしたとき、彼はハートマウンテン移住センターが開設され、何千人もの日本人がワイオミングに来たとき、祖父が大喜びしていたことを話してくれた。彼はキャンプに頻繁に通い、ようやく自分の仲間と交流することができた。
日本人を探して全国を旅したときも、同じような感動を味わいました。それは、いとこたちが私をすぐに家族の一員として受け入れてくれた日本への旅の延長のようでした。私たちは確かに、独自の個性、性格、歴史、人種的記憶を持つ民族であり、私たちのルーツは深く根付いていて、頑強であることを知りました。私が話した日本人の中に、私は自分自身を見ました。まるで故郷に帰ってきたような気分でした。
※ジーン・オオイシ著『ヒロシを探して』改訂版(2024年)より抜粋。
© 1988 Gene Oishi