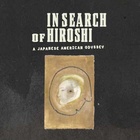自分やおそらく同世代のほとんどの日系アメリカ人は知的障害者だと長い間思っていたが、その障害の性質を正確に、あるいは明確に定義することはできなかった。1976年に初めて小説を書き始めたとき、私は執筆中に涙を流していた。自分が書いたものを見返してみれば、そのような反応を引き起こすほど感情的な文章ではなかった。私が胸を打たれた一節は、父親の死後、「私は日本人だ」と自分に言い聞かせた登場人物についてだった。
その頃、私は人々、特にグループと話すのが困難になり始めました。予期せぬ瞬間に唇が固まってしまい、極度の肉体的努力でしか話すことができませんでした。まるで全身が反抗して、私が話すのを妨げようとしているかのような時がありました。それは、私が報道官を辞任して間もない1981年6月、第二次世界大戦中の日系アメリカ人の強制収容を調査するために議会が設置した機関である戦時中の民間人の移住および強制収容に関する委員会の報告セミナーで論文を発表するよう招かれたときのことでした。
証言する前から、胸が締め付けられるような感覚が始まりました。証言中は、涙がこぼれないように演壇を掴まなければなりませんでした。胸が締め付けられ、言葉を発するのに全力を尽くしました。声はかすれ、ほとんど判別できませんでした。感情的な反応の激しさは私には謎で、不安になりました。なぜなら、自分の中に、自分では気づかない、自分では制御できない力が宿っていることが、次第に明らかになってきたからです。
私が委員会に何を言ったのかを検証し、私の中でこれほど激しい感情的反応を引き起こした本質を抽出しようとしたとき、それは「私は日本人である」という暗黙の発言に行き着きました。
私の証言の核心は、ヒラ川移住センターでの出来事でした。そこで私は友人たちと戦争映画を見ながら、日本軍の戦艦が沈没するのを歓声を上げ、拍手喝采しました。委員会にその出来事を説明した後、私は、それが今でも私を恥ずかしくさせると言いました。なぜなら、それは日本に対する憎しみの表現であり、事実上、自己嫌悪の表現だったからです。1960年代の黒人の闘争心を理解するのは私にとって難しいことではなかったと私は言いました。黒人が自分の人間としての尊厳を主張し、フランツ・ファノンが言ったように、抑圧者の目を通して自分自身を見ないのは、私には容易に理解できました。
日系アメリカ人にとって、人種だけを理由とした私たちの収容は、抑圧者である白人アメリカ人の目を通して私たち自身を見ることを意味していた。私たちは、日本船が爆撃され、乗組員が命からがら海に飛び込む光景に歓声を上げていた。
その後、委員会が数都市で公聴会を開いたとき、何百人もの日本人が証言に現れ、普段は控えめで控えめな二世たちが、涙をこらえたり、涙を流しながら自分たちの話を語った。聴衆の中の若い日本人たちは、自分たちの親世代の人々がこれほど感情的になるのを見て驚いた。「二世があんなふうに振る舞うのは初めてだ」と、彼らの一人は言った。多くの人が、この公聴会を、収容所以来、日系アメリカ人コミュニティーにとって最も重要な出来事とみなした。まるで、コミュニティー全体がついに過去を悼み、40年ぶりに本当の気持ちを明らかにしたかのようだった。
私はそれらの感情を本に書き記したいと思っていましたが、それができないことに気づきました。昔の記憶や感情を掘り起こすことは少しずつ進んでいましたが、私や私と同世代の日本人の中に湧き上がってくる感情をまだはっきりと理解していませんでした。
そして 1982 年、私は思いがけないところから助けを得た。ナショナル ジオグラフィックが、アメリカにおける日系人に関する記事を書く契約を私に持ちかけたのだ。同誌の編集者たちは、私がボルチモア サン紙に書いた、ルーズベルト大統領が大統領令 9066 号 (1942 年に日系人の強制収容を認可した法律) に署名してから 40 年目の記事を読んだのだった。私は議会委員会での証言を、同紙の「サンデー パースペクティブ」欄の新聞記事として書き直していた。
ナショナル ジオグラフィックの編集者は、どのような記事を求めているのか具体的には述べなかったが、社会科学者が長年主張してきたこと、つまり日系アメリカ人は並外れて成功した民族であり、実際「模範的マイノリティ」であるという主張を具体化することを望んでいるという印象を受けた。私はニューヨーク、シカゴ、ロサンゼルス、サンフランシスコ、シアトル、ホノルルを訪れ、あらゆる年齢、さまざまな職業の日本人 100 人以上にインタビューした。
最初は、大富豪、白人系企業で働く弁護士、テレビのキャスター、ロックバンドのリーダーといった成功物語を探していました。しかし、しばらくすると、模範的マイノリティについて書くことにもう興味がなくなりました。書くことにはまったく興味がなかったのです。私はただ、他の日本人と話したり、話を聞いたりしたいだけだったのです。
ニューヨークで、私は元音楽教師で、二世のみで構成される第442連隊戦闘団の曹長だった飯島健に会った。彼は1941年12月4日、真珠湾攻撃のわずか3日前に徴兵された。その後、陸軍は彼をどう扱えばよいか分からず、第442連隊が結成されるまで、彼はあちこちの駐屯地を転々とし、雑用を与えられたと、彼は語った。
自分は忠実なアメリカ人であることを証明したい人は他にもいたかもしれないが、自分には証明するものが何もなかったと彼は語った。「私は生き延びて家に帰りたかった。それが私の唯一の考えだった。」
彼はヨーロッパでの戦闘を生き延び、ニューヨークの自宅に戻った。音楽教育の学位は取得したが、教職はいくらあっても就職できなかった。4年間、非熟練労働者として働き、1950年にようやくサウスブロンクスの学校で教職に就いた。「校長は必死で私を連れて行ったのです」と彼は言う。「誰もそこに行きたがりませんでした」
26年後に引退した彼は、ブルックリンのトーマス・ジェファーソン高校の音楽部長を務めていたが、戦時中の経験と、軍隊から戻った後に受けた偏見について苦々しい思いを抱いていた。「もう一度やり直せるなら、『絶対にやらない』と言うだろう」と彼は語った。
私は、1960年代にコロンビア大学に通いながら反戦デモに参加していた息子のクリスと話をした。クリスは、路上で「絶対に行かない」と叫んでいたが、父親が第442連隊に所属していたことは想像もできなかったという。「彼らが何をしようとしていたのかようやく理解するまで、私は腹立たしかった」と彼は語った。
彼が日系アメリカ人の歴史と他の非白人の歴史に興味を持つようになったのは、反戦運動がきっかけだった。「私にとっては、啓示でした」と彼は言う。「人生の転機でした。私はアメリカ兵よりもベトナム人に共感するようになりました。プエルトリコ人、黒人、その他のアジア系アメリカ人に共感するようになりました。」彼はまた、父親の世代の日系アメリカ人を理解し始めたとも言う。「彼らは頭に銃を突きつけられていたのです。」
私は、ハーバード大学で学んだ日系三世のグラント・ウジフサ氏と話をした。同氏はニューヨークで大手出版社の編集者として働いていた。同氏はもともとワイオミング州ウォーランドの出身で、祖父母が移住したため、同氏と家族は強制収容所に送られることはなかった。しかし同氏は、「仮想的なトラウマ」のイメージは持っていたという。当時同氏は幼児だったため、強制収容所の個人的な記憶はなかったはずだが、同氏は次のように語った。
「それは私に傷を残したでしょう。私は4歳、10歳になった後もそれを経験していたでしょう。それは私の人生の一部だったでしょう。ほとんどの日系アメリカ人と同じように、私の血管にも流れていたでしょう。もし私の家族を断ち切ったなら、私も断ち切ったことになります。私の男らしさは祖父と父から受け継いだものです。もし彼らを去勢すれば、私も去勢されるのです。」
ロサンゼルスで、私は広島のロックバンドのリーダー、ダン・クラモトを訪ねた。このバンドは西洋と日本の楽器をミックスして演奏していた。明らかに西洋音楽だが、バンドの演奏には日本のリズムやメロディーの痕跡が残っていた。日系アメリカ人3世のクラモトは、内気で物腰柔らかな男性だった。
会話の中で、私は日本人が集団でいるのを見るのが嫌だと彼に話したところ、彼も同じように感じていると言った。彼も自分の人種と折り合いがつかず、他の日本人と一緒にステージで演奏したり、日本の楽器を使ったり、グループ名をヒロシマとしたりするのは、自分の生まれつきの臆病さと戦う方法だと言った。彼はライオンへの恐怖を克服するためにライオンの調教師になった男に似ていた。「それが難しい問題に正面から取り組む私なりの方法なのです」と彼は言った。
世代を超えて自分の二世の世代を見ることは、私にとって助けになりました。三世は私に希望を与えてくれました。なぜなら、彼らは二世よりもはるかに先に日系アメリカ人の謎を解いていたからです。私たちには何が問題なのか?なぜ私たちはそんなに恐れているのか?
ロサンゼルスの三世ジャーナリスト、ドワイト・チュマンは、1940年代の二世を「自己嫌悪を売り物にして主流の考え方の中に消えることで成功した混乱した若者たち」と呼んだ。彼は、笑顔で勤勉で信頼できるプロフェッショナルな「ミスター・ナイスガイ」という模範的な少数派のイメージ、「静かなアメリカ人」に言及した。
彼の話を聞いて、白人が私に会うと、彼らの知り合いの日系アメリカ人を知っているかとよく尋ねていたことを思い出した。「ジョージを知っていますか?」とある男性が答えた。「本当にいい人です。」私たちはみんないい人だと私には思えたし、意地悪で、頑固で、口うるさく、不誠実で、頼りない二世を見つけるとほっとするだろう。
二世の臨床ソーシャルワーカー、エイミー・イワサキ・マスさんは、ワイオミング州ハートマウンテンの収容所に家族とともに送られたとき、6歳だった。彼女は、収容所での体験を「楽しい」経験として何年も覚えていたが、精神分析を受けて初めて本当の気持ちが表に出てきたという。他の二世たちとセラピストとして働く中で、彼らもまた、その体験に関する感情の多くを抑圧していたことがわかったと彼女は語った。
抑圧は、政府が自分たちに敵対しているという恐ろしい認識から自分たちを守る手段だと彼女は言った。ほとんどの二世の、感じがよく、攻撃的ではない態度、きちんとした身だしなみや外見、大げさな心配や表面的な性質は、主に防御色だと彼女は言った。
続く…>>
※ジーン・オオイシ著『ヒロシを探して』改訂版(2024年)より抜粋。
© 1988 Gene Oishi