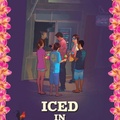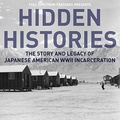神戸での酷暑の日々を思い出す。兄弟と何時間も畳の上に座り、脚を覆う熱く腫れたみみず腫れをだるそうに掻いたり叩いたりしていた。竹マットの上に長時間座り続けた圧力で膝や太ももにできたパッチワークの跡をなぞりながら、本のページを引きずって読み進めたり、しびれを切らしながらニンテンドーDSを触ったり、ソファのクッションに沈み込んでテレビ画面を見つめたりしていたが、私たちが見たいのはただ懐かしい赤、白、青、金色のオリンピックユニフォームだけだった。
横浜にいた頃を思い出すと、蚊がせっかちにひっきりなしに網戸をたたき、いとこと一緒にベッドに座り、午後には窓のまわりに霧のような湿気が雲となって降り注ぐ前に、雨が上がったばかりの珍しい涼しさを急いで吸収していた。また、筋肉がびしょ濡れになるような静けさもあった。庭に座り、のんびりとした7月の雨粒が広い緑のアジサイの葉の先を滴り落ちるのを眺めたり、ソーダを買うために小銭を数えながらカチャカチャと音を立てる山に硬貨を投げ入れたり、その間に苦い麦茶をすすりながら、甘い炭酸飲料への高鳴る渇きをなんとか満たしたりしていた。
そして、広島での息苦しい日々を思い出す。暑さが私たちを圧迫し、よどんだ空気を切り裂く扇風機を激しくパタパタと回すことでしか暑さを和らげることができない。それは、祖母から厳しい、突き刺すような視線を間違いなく引き起こすであろう、無作法な行為だった。その夏は、常に耳元でブンブンという音がしていた。通り過ぎるトロッコのガタガタという音、木々に隠れているセミの不協和な、キーンという鳴き声、そして、百貨店のエアコンのもろくプラスチックのような空気の中で座っていると、蛍光灯の低い脈動さえも。そのブンブンという音は、私たちの頬や顎をむず痒くさせ、一度も弱まることはなかった。
日本で過ごした最高の時の味、音、感触、色彩を思い出すのは難しいことではありません。結局のところ、最高の笑い、最高の話、最高の思い出は、いつも、舌の上で溶ける冷たい甘いアイスクリームを少しずつかじったり、手から水滴が転がったり、突然破れたプラスチックの包み紙のキーキーという音、そして緑のネオンサインの天国のような輝きで区切られていました。コンビニのアイスクリームはいつも最高でした。
それはたいてい、ある提案、つまり質問、アナウンス、あるいは習慣的な思い込みから始まった。「コンビニ?」。そして私たちは床から体をはがし、跳ね起き、スリッパを脱ぎ捨て、ドアまで降りて、ただでさえ不安な足を、丁寧に置いてあった靴に押し込み、頭から、鈍い空気の中に飛び出すのだった。
あるいは、濃い茶色のラーメンをがっつり食べた後や、市場でパリパリとしたセロハンのおにぎり、または甘く艶をかけてピカピカに輝く「屋台の」餅を食べた後に、ネオンサインを見て駆け寄るのは、私か私の兄弟たちだったかもしれない。セブンイレブン!ローソン!ファミリーマート!ドアは、濃厚な甘さのポテトチップス、コロッケ、アルミニウム、雑誌の匂い、白黒の後の色の爆発に似た贅沢な肺いっぱいの味をはにかむかのように、外に飛び出す。それは、私たちの瞳孔をきつく黒く丸め、腕の毛を必死に伸ばして、視界にあるすべてのテクスチャをかすめようとするような感覚への過剰刺激だった。
もちろん、私たちはガタガタと歩いて、おせんべいやコーヒーやラムネを休むことなく通り過ぎていった。私たちが欲しかったのは通路やガラス張りの冷蔵庫ではなかった。それは、まるで他の店に顧客に対する弱々しい握手を降ろすように命じるかのような、ありきたりのお世辞の間に挟まれた白い冷凍庫の中にあった。白い冷凍庫の中にあるものこそ、私たちが欲しかったものだったのだ!
その箱の前では、数分から数時間までが過ぎた。
「今回は何を買おうかな?」
「この味は美味しいですか?」
「この見た目が好きです!」
「何を買うか決めましたか?」
「なあ、あれ試してみたかったんだよ!」
「こんなの今まで見たことないよ!」
私たちは、くすくす笑いながらレジに駆け寄り、買い物を楽しみにしていた。そして、目の前に並んだ虹色の冷たいスナックと引き換えに、糸くずのついたポケットにため込んださまざまな汚れた硬貨を払い出すことでしか得られない、喜びの高揚感に浸っていた。
私たちは、都会の夏のべったりとした空気の中に足を踏み入れ、セロハンとビニールの甲高いキーキーという音に包まれながら、祖父母の非常に残念な思いにもかかわらず、日本の礼儀作法の枠を捨てて、痛む暑さから体を救うことを選んだ。
私たちはそれをかじりました。
オレンジ色のワッフルコーンは発泡スチロールのように軽く、歯でかみしめるときしむ。簡単に砕けて軽いフレーク状になり、すぐに冷たい抹茶クリームの固まった塊に追い抜かれる。クリームは小さくふわふわしたカールとなってバーの残りの部分から落ちてきて、歯に当たる冷たさが口の中を震わせた。固いチョコレートの殻の中心を一口かじって突然止めると、その感覚はさらに強まった。口の中に放り込んだアイスボールは衝撃的な冷たさで、その空間はすぐに冷たい蒸気で貫かれ、気管に染み込んで口が開く。そして外側が崩れると凍りついた息が抑えられ、さわやかで溶けたリンゴジュースがほとばしり、舌の上で冷たく溜まる。柔らかくて氷のようにサクサクしたクーリッシュにはバニラの風味が混じったクリーミーさがあり、喉を滑り落ちて口の奥を冷やし、濃厚な甘さで舌を包み込み、その日の残りの食事の間ずっと、一瞬のベルベットのような後味が残るほどでした。
残っているのは、滴り落ちるお菓子の小さな点、凍り付いた舌で徹底的に洗浄された残骸、一緒に共有した笑い、会話、甘いひとときの甘い思い出、受胎の瞬間からのゆっくりとした滑らかな滴りのような、鮮やかな夏の味のかすかな余韻だけです。
© 2017 Danielle Yuki Yang
ニマ会によるお気に入り
特別企画「ニッケイ物語」シリーズへの投稿文は、コミュニティによるお気に入り投票の対象作品でした。投票してくださったみなさん、ありがとうございました。