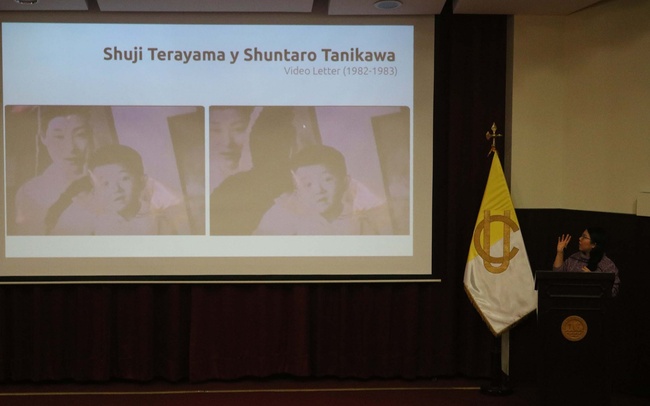すべての芸術の背後には、作品の作者を知るのに役立つ科学、方法、概念があります。多くの場合、この作品はその個人の個人的、親密、本能的な衝動に反応します。しかし、他の場合には、創造的な演習、反省的なエッセイ、何か、人、または場所を研究する挑戦となります。 2024年、日本に関心を持つペルー人のグループが、日本とのつながりを築く芸術的または知的コンテンツを制作するという明確な目標を掲げてコースを受講しました。
それはペルー・ポンティフィカ・カトリック大学の東洋研究センターで開催されました。テーマは現代日本文化でした。教授:メキシコ大学の三浦聡美博士。目的は、ここ数十年の文化的、芸術的表現に関する専門知識を活用し、国際舞台におけるそれらの相互関連性と関連性を示しながら、現代日本文化への理解を広げ、豊かにすることです。
感覚とデジタル技術が介在するグローバル化した世界において、現代日本の舞台芸術、写真、映画制作、音楽表現、ハイブリッドアートは、日系人であろうとなかろうと、今日広く行われている交流と人間の移動から生まれた異文化研究や芸術実践を追求したいと考えるペルー人にとって、より身近で学びやすいものになりつつある。
東洋研究センター教授のアロンソ・ベラウンデ・デグレゴリ氏は、この講座は国際交流基金の日本研究プロジェクト刺激プログラムの支援によって実現できたと説明する。 10 回にわたる集中的な学習セッションを通じて、これらの芸術的なアイデアを学生の創造的想像力に取り入れることを促進することが目的でした。彼らの芸術作品はこの教育機関のウェブサイトでご覧いただけます。
芸術と反省
知念勝比嘉氏は哲学を学び、学校レベルでの教育に専念しています。彼は「アートと日系人のアイデンティティ」と題する学術論文を作成することを選んだ18人の参加者の1人でした。他の参加者は、ゴジラから黒澤明の作品まで幅広い映画をテーマに選び、アニメ、舞踏、俳句、作家の三島由紀夫などをテキストに引用した人もいた。
「幼い頃から、私は芸術の世界と非常に密接な関係を築いてきました。この関係と私の性格的な特徴が相まって、今日に至るまで、古典的な芸術への揺るぎない忠誠心を育んできました」とマサルは記しています。 「PUCPの提案は、私がずっと興味を持っていた地域に焦点を当てた授業を受ける初めての機会だったので、現代アートに対する私の視野を広げる理想的な機会でした。」
沖縄の文化は、ダニエルの両親と祖父母を通して常にダニエルと結びついており、彼らは主要な儀式を執り行い、祖先の伝統と価値観をダニエルに教え込んだ。 「昨年、幸運にも北中城フェローに選ばれ、沖縄に2ヶ月滞在する機会に恵まれました。飛行機を降りた瞬間から、すべてが不思議なほど馴染み深いものになりました。空港ではディアマンテスが演奏し、温かい社交の雰囲気、そして食べ物や伝統も故郷と変わりませんでした。一瞬一瞬、おじさんを思い出しました。」
この自己発見の経験は、芸術作品を第三者の視点から観察するという課題を克服するのに役立つコースへの彼の興味の鍵となりました。 「作品を外から批判したり評価したりすることは不可能であり、作品との直接的な関係性が必要なのです。」これを念頭に、彼は展覧会に出席し、作家たちと話して彼らの動機や願望について学びました。その結果、日系人のアイデンティティとペルーへの日本人移民について言及したエッセイが生まれました。
クリエイティブな見た目
アナ・ソフィア・ヴィラヌエバ・イマフクは、グラフィックデザイナー兼イラストレーターです。壁画提案を含む個展やグループ展に参加。 「日本の文化生産を通して、そして曽祖父母の時代の農業と現代日本の文化現象を結びつけることを通して、日本の近代史に興味をそそられました。この授業の学際的な性質を活用することで、文学、映画、舞台芸術におけるプロセスと著名人を描く機会を得ることができました」とアナ・ソフィアは述べています。
それは、個人的かつ親密な談話の中で彼の芸術的実践を豊かにする方法でした。 「最も困難だったのは、視覚芸術以外の分野からアイデアを取り入れ、プロジェクトの立ち位置を決めることでした。今回はドキュメンタリー的なアプローチを取り、紙と墨を通して捉えた物語の断片を織り交ぜ、家族的なノスタルジアを表現しようと試みました。」彼の作品のタイトルは「一瞬が無限になる。日常の家族生活についてのビジュアルエッセイ」 1 です。
アナ・ソフィアにとって、日系人であることはペルー人としてのアイデンティティの一部であり、周囲の物事の観察や理解に影響を与えています。 「それは私の視覚言語にも反映されています。おそらく、墨や身振り、そして統合と機敏なストロークで瞬間の感情を捉えるというアイデアへの私の好みに反映されているのでしょう」と、第4回日経ヤングアートサロンに参加し、自身の作品に影響を与えたアーティストは語る。家族レベルでは、彼女は、熊本県人会の初代会長の一人である曽祖父の今福大六氏と、家族の中で日系文化の「世話人」としての役割を担った叔母のロサ氏の物語に影響を受けた。
再検討
マルレーヌ・メリノ・モンタニさんは、日系文化と言語の教育サービスに重点を置いた日系機関、ラ・ウニオン教育サービス協同組合で働いています。 2023年にPUCPから招待状を受け取ったとき、彼女は参加できませんでした。しかし、同僚はそれを受け入れ、各授業の後に学んだ内容を持って興奮した様子で出席しました。これが、日系人ではないにもかかわらず、彼女が翌年も参加する動機となった。
「一番大変だったのは、芸術的なレベルでの日本文化の知識がほとんどないことに気づいたことです。授業で、芸術について深い知識を持つ学生がたくさんいるのを見て、最初は圧倒されましたが、クラスメイトと共有できる貴重な情報が得られるので、ワクワクしました。」彼女は、芸術的な提案をするために、自分が共感できるもの、日本の社会について十分に社会的かつ客観的なものを探しました。
選ばれたのは、日本社会における女性の役割に触れ、受賞歴のある映画にもなった平子和香の漫画「マイ・ブロークン・マリコ」だった。そこで彼女は出発点を見つけ、コミュニティとの関係によって補完されました。そこで彼女は多くの興味深い物語に出会い、一連の価値観と習慣に感銘を受け、女性を疑問視する役割に置くパターンを特定するようになりました。
芸術のための人生
このコースに提出された 20 件のプロジェクトは、ペルーと日本の文化的、歴史的なつながりにより、驚くべきテーマの多様性を示しています。ペルーのポピュラー音楽、俳句、ディアブラーダ(アンデスの踊り)の仮面、折り紙は、野島康三、北園克衛、エウロジオ西山など両国の数多くのクリエイターを含むリストの一部です。芸術とこのペルー人のグループとの関係は、芸術がどのように生活に浸透しているかを示しています。
知念勝氏は、ラテンアメリカ哲学の授業でイグナシオ・ロペス=カルボ教授と出会い、教授の文献のおかげで日系人が自分たちのことをいかに知らないか理解できたと語る。 「ニッケネスは、人それぞれに異なって経験される現象です。状況が各個人のアイデンティティを形作ります。」この観点から、彼はナルミ・オグスク、ヘルマン・チネン、アウグスト・ヒガなど、さまざまな日系アーティストの作品における自己表現のプロセスを分析しました。
アナ・ソフィア・ビジャヌエバ・イマフクは、アイデンティティ遺産の伝達者としてのこの女性の役割に、創造する理由を見出しました。その結果、2024年の初めにペルー日本文化センターで個展「 花の王朝」を開催しました。この展覧会の共通点は、彼女の家族の女性の名前の選択と、日系家庭における物質的および文化的生活の世話人の役割との関係性にあります。
別の視点から見ると、マーリーン・メリノは心の中に日系人の気持ちを感じます。 「私は多くの日系人と仕事をしており、ある意味では彼らの習慣に溶け込んでいます。日系人との私の関係は、私たち皆が心から愛し、彼らの誠実な友情と価値観を尊敬する友人たちから始まりました。アートは様々なデザインを表現する媒体であり、それを望む人々の感情や興味を伝えるために存在します。」
注記:
1. アナ・ソフィア・ビジャヌエバ・イマフク「一瞬は無限かもしれない:日常の家族生活についてのビジュアルエッセイ」6月27日(木)「現代日本文化」講座芸術・学術プレゼンテーション(YouTube)
© 2025 Javier García Wong-Kit