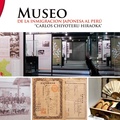幽霊とは、記憶、沈黙、郷愁、そして秘密です。メキシコの映画監督スミエ・ガルシア・ヒラタが監督したこのドキュメンタリーは、主人公たちが子孫に隠してきた、伝えられていない経験が特徴的な、メキシコへの日本人移民の歴史を掘り下げています。
アメリカやペルーと同様に、第二次世界大戦によって特徴づけられた歴史。
「幽霊という言葉は、過去の亡霊、語られていない物語、何世代にもわたって受け継がれ、現在も悩まされている沈黙の記憶を表しています」とスミエさんは言う。
「こうした痛ましい瞬間の多くは、一種の集団秘密として公に語られることはなく、埋もれたまま人々のアイデンティティに影響を与え続けている」と彼女は付け加えた。
しかし、沈黙がすべて否定的なわけではありません。また、参加者の先祖の楽しい思い出(彼らの証言は作品に集められています)も、文化や家族の伝統を通して表現されています。このドキュメンタリーでは、そうした沈黙を破り、メキシコの日系人の幅広い経験を語ろうとしています。」
歴史の振り返り
歴史について言えば、メキシコの人類学者ダヒル・メルガル・ティソックの権威ある声がある。彼はメキシコへの日本人移民に関する著書を数冊執筆しており、幽霊の実現を可能にした研究を担当した人物である。
ダヒルは、戦争中、ラテンアメリカの13か国が「日本人とその子孫に対する残虐な政策」を実施したと明らかにした。
そのうちの一つ、メキシコでは、「財産権の禁止、資本の所有と管理、移動の制限、監視政策、100キロ以内の居住の禁止」などがあった。太平洋沿岸から200km以内。メキシコとアメリカの国境から撤退し、最終的に認可された都市(そのほとんどは国の中心部)に即時集結するよう命令が下された。」
抑圧的な措置の結果、多くの日本人家族が家や事業を失い、文字通り寒さの中に取り残されました。
地元の権力者とのつながりのおかげで何とか嵐を乗り切った者もいたが、大半はわずかな資産を出し合って過密な空間で他の日本人と屋根を共有したり、「日本人植民地相互扶助委員会が提供した」農場に移らなければならなかった。
その最初の建物はメキシコシティにあり、日本人建築家の松本辰五郎氏が所有するエル・バタンでした。その後、ハリスコ州カストロ・ウルディアレスとモレロス州テミスコからの避難民を収容するために特別に購入されました。
ダヒル氏は、前述の施設の居住者は日中は施設から出ることが許されており、それが米国の強制収容所とは異なる点だと説明する。しかし、「多くの家族にとって、当時の反日的な風潮から身を守る唯一の選択肢だったが、何よりも共同農業労働を通じて住居を確保し、食糧の自給自足を確保することが唯一の選択肢だった」
海の向こうで起こっていた、自分たちとは何の関係もない戦争の罪のない犠牲者であり、「敵国」で生まれたというだけの理由で汚名を着せられた移民たちは、亡命と虐待の記憶を葬り、過去を振り返りながら前進することを決意した。
彼らの沈黙の結果、後の世代はコミュニティの過去を知らずに育った。
しかし、彼らの経験は伝えられ、子孫に影響を与えたり、痕跡を残したりしました。 『幽霊』では、日系人は「経験は遺伝する」とか「写真花嫁(写真でしか知らなかった一世と結婚し、その後、彼が移住した国に渡った女性)の孫娘であることに驚いている」などと言っている。
女性たちは保存活動において重要な役割を果たした。
「インタビューの中で、家族の歴史は多くの場合、女性を通じて口伝えで伝えられていることがわかりました。 「日系家族に限らず、多くの場合、共同体や家族の意識は女性によって築かれると思います」とドキュメンタリー監督は語る。
日経のインタビュー対象者の一人は、「記憶と郷愁はアイデンティティにおいて重要な役割を果たしており、郷愁は受け継がれ、構築される」と述べている。
澄江さんはこう説明する。「郷愁は、一種の感情的な遺産のように、子孫の記憶に浸透します。私たちがインタビューした人々のほとんどは、移住や戦争時代を直接体験したわけではありませんが、祖父母や父親、母親から伝えられた記憶の重みを背負っています。」
「それは必ずしも過去の経験から来るものではなく、感情や漠然とした記憶、直感から来る懐かしさです。このノスタルジアは、現在の世代と過去を結びつけるものとなることが多いため、アイデンティティの構築に役立ちます。 「それは共有された記憶であり、私たちが自分自身をどう捉え、歴史とどう関わるかを形作る一種の感情的な遺産なのです」と彼は付け加えた。
さて、メモリは事実を忠実に記録する電子機器ではありません。私たちが自分自身に語る過去は、私たちが覚えている過去であり、必ずしも実際にあった過去ではありません。私たちが自分自身に語る物語は、弾力性があり、変化に富み、時が経つにつれて大小さまざまな変化を経る物語です。
「私は映画や視覚芸術の仕事を通じて、記憶とそれを構成するさまざまな要素を探求してきました。 1 つの側面は、特定の記憶を思い出す方法です。何かを思い出すとき、その記憶について最後に考えたときのことは覚えていて、その瞬間そのものは覚えていません。つまり、時間が経つにつれて、すべては私たちが保存しようとする瞬間の記憶の記憶の記憶になります。この繰り返しの中で、変化が起こるのは自然なことです。このため、私たちは出来事を実際に起こった通りには思い出すことができず、出来事は私たちの感情、経験、そして他人から聞いたことというプリズムを通してフィルタリングされるのです」と彼は言う。
ドキュメンタリーでは、「記憶の創造的な再構築を見せようとしている。多くの日系人にとって、先祖の過去には空白と沈黙が満ちているが、それらの空白は感情的かつ想像的に受け継がれてきた物語で埋められており、たとえそれが完全に正確で直線的でなくても、その過去とのつながりが生き続けることを可能にしている。」
記憶はアイデンティティの基盤であり、ユウレイは参加者を通してこのテーマを取り上げている。参加者の一人は「アイデンティティの演劇性」について語っており、これは人々が姓、人相、民族的起源に基づいて社会が付けるラベルに従うよう促すものだ。日本人の祖先を持つ人は必ず空手家になる、といった感じ。
ユウレイは、柔軟性と個人の自主性、そして民族に縛られることなく、生まれたままの自分や望むままの自分を表現することの擁護者です。
「このドキュメンタリーは、特定のアイデンティティを表現するときに私たちが感じる期待について、私たち全員に考えてもらうための反省であり、共感的な招待状です。 「ドキュメンタリーでは日系人の特定の要素について語りながら、アイデンティティの演劇性を指摘することで、私たちが想定するアイデンティティに扮するという考えに、観客全員が共感できるのではないかと思います」とスミエは言う。
「アイデンティティは固定されたものではなく、私たちが常に構築し、適応していくものです。私たちが何を表現しようとしているのかを考える際、固定観念や社会的な強制ではなく、私たち自身の自由意志でそうする自由があることを願っています」と彼女は結論付けています。
言葉では言い表せないこと
『幽霊』は、証言が次々と直線的に続く典型的な物語、つまり従来のドキュメンタリーではない。語り手のいない物語や、それぞれの喚起に新たな要素が加えられた物語、想像力で埋められた空白、ぼやけた記憶は、例えば日本美術に見られるような他の表現形式を招きました。
ダヒルは、「物語は、記憶の地理の糸であることに加えて、沈黙と忘却の地理の役割も加える必要があった」と説明する。これらは、時が経つにつれて細部がぼやけてきた過去の物語の中に存在していたが、物体の特徴を消し去った埃の緑青や湿気の痕跡、家族写真に写っている人々の顔、墓石に漢字で書かれた名前など、素材の詩情の中にも存在していた。
「こうした複数の地域を訪れ、コミュニティのさまざまな人々の体験を聞くというプロセスそのものが、チームとして、これらの記憶を複数のインタビューで構成されたオープンな物語で表現するべきか、それとも抽象化された記憶の言語そのもの、沈黙と忘却の重み、そしてその微妙なウィンクやジェスチャーを尊重すべきか、という問いを私たちに課しました」と彼女は付け加えた。
そのため、彼らは「言葉で表現できることと表現できないことの間の物語を、ダンス(能、舞踏、田舎のダンス、お祭りのダンス)、風景、記憶の地理、遺物、そしてこの物語が象徴される場所など、他の言語を使って表現する」ことを選択しました。
このプロジェクトは、スミエさんとダヒルさんが2019年に始めた、メキシコへの日本人移民の歴史とコミュニティの発展についての会話から生まれました。
2019年から2020年にかけて、2人はドキュメンタリーを制作したチームのメンバーとともに、北米各地を探検旅行した。
「私にとって、視覚的かつ物語的な旅を、メキシコへの日本人移住の歴史が1897年に始まった南の国境、ソコヌスコ(チアパス州)から始めることが重要でした。そして、そこから、この起源の起源の国境である北の国境、エンセナダ・ティファナを掘り下げていくのです。漁業ブーム、アメリカの禁酒法によって促進された商業観光開発、そしてメキシコとアメリカの常に複雑な関係に惹かれて、1920年代から1930年代にかけて日本人が定住した場所です」とダヒルは回想する。
旅の途中で、チアパス州メキシコ日本人会やエンセナダ日本人会などの団体、そして西川清子さん(エンセナダ)、ヨシオ・クルス・ナカムラさん(タパチュラ)、ミゲル・ナカムラさん(エスクイントラ)、マルティン・ノムラさん(アカコヤグア)などの人々の協力を得て、証言を集め、家族の古い写真や遺品にアクセスし、開拓者の遺骨が眠る墓地や最初の日本人移民の家や会社を訪問した。

歴史についての議論を締めくくるにあたり、ダヒルは、1897 年にメキシコを目的地とした、ラテンアメリカへの最初の公式日本人移住計画について語ります。それは榎本植民地でした。
「この移民は、発起人の榎本武揚子爵にちなんで名付けられ、コーヒー熱の時代とポルフィリアート(メキシコがポルフィリオ・ディアスによって統治されていた時代)によって約束された富と土地の約束に惹かれ、現在のエスクイントラ市とアカコヤグア市の間に定住した36人の日本人男性の移住でした」と彼は説明する。
この取り組みは、マラリア、黄熱病、コーヒー栽培(日本人にはほとんど知られていない穀物)の経験不足、そして飢餓のために失敗した。榎本植民地の終焉時には、この地域に残った日本人移民はわずか16人だけで、メキシコ人女性と家族を築き、他の作物、家畜、サービスを通じて経済を多様化していた」と彼は付け加えた。
こうした挫折にもかかわらず、メキシコへの日本人移住は止まらず、1903年に2度目の一世の集団が到着した。これは、ドキュメンタリー映画『幽霊』が厳密さ、芸術性、そして繊細さで描き出す、125年以上にわたる力強い歴史における新たな節目である。
予告編:幽霊
© 2025 Enrique Higa Sakuda