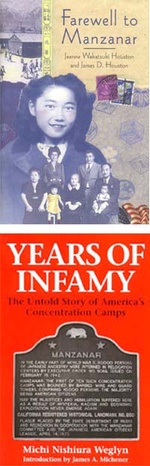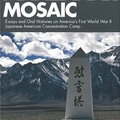パート4を読む>>
芸術として作り直された歴史:亡命と追放に関するドキュメンタリーとフィクション
こうした見方は、日系アメリカ人の戦争体験を描いた芸術、文学、ドキュメンタリー、ノンフィクションによって形作られていった。 『自由にして平等に生まれて』は、戦後の建築ブームの中で忘れ去られ、歴史のこの章に沈黙の幕が下りた。初期の例外の一つは、アーティストのミネ・オクボの力強い本『 Citizen 13660』で、1946年にコロンビア大学出版局から出版された。オクボは、カリフォルニア州の違法な「集会」センターであるタンフォランとユタ州トパーズ強制収容所での生活を描いた206点の自作のイラストを掲載し、強制収容を微妙かつ間接的に批判する、悲しげで、時にはユーモラスな描写を添えた。言葉と力強い絵を通して、オクボは写真では表現できない方法で、その経験のほろ苦い本質を捉えた。彼女の本は出版された当時は波紋を呼んだが、オクボは後に「50年代には戦争は忘れ去られていました。国中の人々が生活の再建に忙しかったのです」と認めている。

ミネ・オクボは「Citizen 13660」のこのイラストについて、多くの女性がオープントイレに慣れるのに苦労したことを次のように説明している。「彼女たちはカーテンをピンで留めたり、板を立てたりしてプライバシーを保とうとした。」 (出典: ミネ・オクボ財団、全米日系人博物館 [2007.62])
1960年代後半から1970年代前半にかけて日系三世が成人すると、ほとんどの人がほとんど聞いたことのない捕虜収容所に対する好奇心から、収容所についてのより批判的な議論が起こり、補償運動が始まった。1972年、リチャードとメイジー・コンラットは、ドロシア・ラングの写真の多くを選び、『大統領令9066』と題した写真集を出版した。これは、それまでに明らかにされていたことよりも真実に近いと思われる、日本軍の強制収容の実態を提示するためだった。同年、ジーン・ワカツキ・ヒューストンと夫のジェームズ・D・ヒューストンは、画期的な回想録『マンザナーへの別れ』を出版した。これは、ワカツキ・ヒューストンの7歳から17歳までの人生をありのままに感動的に綴ったもので、マンザナーでの投獄と民間人としての生活への復帰を詳細に描いている。
ワカツキ・ヒューストンの回想録、特に収容所の初期の頃の回想録は、アダムズが描写したマンザナー収容所のより以前の状況(「誰もが前向きに忙しく、機敏で、陽気だった」)とは非常に異なっている。彼女は「頻繁に病気になった」と描写しているが、最初は大量のチフス予防接種を受けたため、次に食事のせいだった。「…満員の寝室、共同の食堂、開放されたトイレ。これらすべてが、もう一人の自分への公然たる侮辱であり、反抗する力のない平手打ちだった。」
『さらばマンザナール』を基にしたテレビ映画が1976年に放映されたが、同年はミチ・ウェグリンのノンフィクション『悪名高き日々:アメリカの強制収容所の知られざる物語』が出版された年でもある。ウェグリンは著書の中で、アメリカ政府が強制収容所を「軍事上必要」と評価していたことを暴露し、日本人外国人および日本人に対する扱いはあからさまな人種差別と経済的搾取によるものだと主張した。ベトナム戦争とウォーターゲート事件に対するアメリカ国民の幻滅は、活動家である二世、三世による賠償運動に拍車をかけ、彼らの努力により1988年に公民権法が可決され、生き残った収容者全員に公式謝罪と2万ドルの賠償金が支払われた。この歴史的事件のメディア報道は、アラン・パーカー監督による1990年のハリウッド映画『楽園を見よ』への関心を高めるのに役立った。
マンザナー収容所の記録写真が初めて公開されて以来、強制収容に対する日本人コミュニティの態度は、沈黙の恥辱から不正義の認識へと、そして補償を求める闘争へと、そして現在では、現代の公民権侵害に対する警告の物語として収容者の物語を保存したいという願望へと変化してきた。
© 2011 Nancy Matsumoto