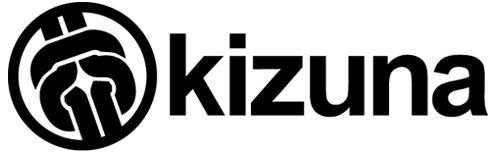私の母、ナオミ・ボーズ(旧姓田口)は、日本の岡山県津山市で育ちました。母は主婦で、父は郵便局員でした。母は4人兄弟の末っ子で、一番上が女の子、その次に男の子が2人いました。母は高校を卒業しましたが、家族には大学に行かせる余裕がなかったので、岩国にある米軍基地の職員になりました。
母は1955年から57年の間に、父セルウィン・ボーズと出会いました。父は朝鮮戦争に従軍し、ニュージーランド軍から除隊したばかりでした。父は岩国基地のクラブの副店長として働きました。母は食堂で働いていました。父は母とダンスをしているときに恋に落ちたと言っていました。彼らは1957年に結婚しました。母は23歳、父は33歳でした。
私の母の本名はアツコでしたが、日本名と西洋名の両方に通じるナオミという名前を採用しました。父の髪は雪のように白かったので、みんなは父を「スノー」と呼んでいました。日本でも父は「ユキ」と呼ばれていました。
彼らの結婚の許可は、家族の中で一番年上の男性、つまり母の兄(彼らの父親は亡くなっていた)から得る必要がありました。父とその家族は外国人だったため、兄は彼らの通常の身元調査を行うことができず、複雑な状況でした。結局、母は断固として、兄の許可なしに父と結婚すると宣言しました。
私は1957年、真珠湾攻撃の16周年に岩国の米軍基地病院で生まれました。1958年に私たちはニュージーランドに移住しました。それが、今や「戦争花嫁」となった私の母が日本を見た最後の時でした。
私たち家族は北島の東海岸にあるホークス ベイに定住しました。父は南島のマールボロ サウンズで育ち、その後ホークス ベイのヘイスティングスに家族で引っ越しました。1960 年代半ばから 1970 年代の終わりまで、両親はホークス ベイ ファーマーズ ミート カンパニーの冷凍工場に併設された独身男性用の宿舎と食堂を経営していました。そこでは労働者が輸出用の肉を加工し、冷凍していました。母と父は週 7 日働き、温かい食事を提供しました。昼食時には、食堂で何百人もの空腹の男性に食事を提供していました。
母は宿舎に住む男たち(「息子たち」)にとって、いわば代理母のような存在でした。下宿人の何人かはダイビングに行って、キナ(ウニ)、ザリガニ、パウア(アワビ)、そして時々ウナギを母に持ってきました。当時ニュージーランドではほとんど食べられなかったこれらのごちそうを母が喜んで食べるのを見て、彼らは大喜びしました。
母が日本で子供だった頃、母の家にはほとんどの家政婦がいて、料理のほとんどをこの家政婦がやっていました。ニュージーランドでは、母は料理の仕方だけでなく、それまで見たことのない食べ物の調理も学ばなければなりませんでした。母の最初のやり方は、すべてを茹でて、塩とコショウを加えるというものでした。やがて母は、労働者のために、ローストした肉や野菜、ボリュームのあるとろみのあるスープ(繊細な香りのする澄んだスープはここにはありません!)、イギリス風のプリンなど、典型的なヨーロッパの重たい食事の作り方を学びました。食堂でカレーライスが作られると、男たちがライスに砂糖と牛乳を入れてライスプディングを作っているのを見て、母はびっくりしました。
姉のパトリシアは1959年生まれ、末の妹のドラは1961年生まれ。私たちは幼いころから、玄関、お便所、メリケンコなどの日本語を使っていました。母は私たちに、一寸法師や桃太郎などの日本のお話を聞かせてくれました。私たちが幼稚園に入るまで、母は英語を使うように切り替えませんでした。その方が混乱が少なくなり、私たちが馴染みやすくなると考えたからです。しかし、耳かきで耳を掃除する儀式など、日本の古い習慣もいくつか残っていました。
正月には、母は私たちに浴衣と下駄を着せて、日本の友人に送る家族写真を撮らせてくれました。ちらし寿司も作りました。母がちらし寿司や他の料理の材料をどうやって思いついたのかはわかりません。日本食は入手が難しかったからです。日本の友人が昆布や海苔、漬物を送ってくれることもありました。私たちは主に中国の青果店で買った中国産の醤油と椎茸を使いました。米はいつも短粒種でした。
母のお気に入りの午後のおやつの一つは、梅干しをのせたご飯に緑茶かお湯をかけることでした。私たちが体調を崩すと、母はおかゆ、つまり生卵と少量の醤油、砕いて焼いた海苔を上に散らした温かいご飯を食べさせてくれました。これが私のお気に入りでした。冬には特別な食事、すき焼きがありました。
このように、私の幼少期は母の努力によって日本文化に浸りきっていました。その後日本に住んだとき、多くのことが馴染み深くもあり、同時に外国のものでももありました。
私はニュージーランドのマッシー大学で理科を専攻していましたが、日本語を学ぶために文系に転向しました。母の文化をより深く、より客観的に理解したかったのです。義理と義務(義務/責任の概念)について学び、それが今でも私の人生にどれほど影響を与えているかを学びました。
1979 年に大学を卒業した後、私は 1 年間の交換留学プログラムの一環として日本に行きました。これが私にとって初めての日本訪問で、京都産業大学近くの女子寮に住んでいました。典型的な朝食は温かいご飯、生卵、そして醤油でした。これは子供の頃からの私のお気に入りでした。外出するときはいつでもきちんとした服装をすることが求められました。これは問題ではありませんでした。なぜなら、母は簡単な用事のときでも常にきちんとした服装をするように私たちを育てていたからです。
私はその後も2年間日本に留まり、大阪で英語を教えました。私は日本人の血を引くカメレオンのような性質を受け入れ、時には日本人の友人たちに溶け込み(友人グループとタクシーに乗っていると、運転手が時折、私が日本人だと思い込んで私の英語が上手だと褒めてくれた)、また時にはクラブへの無料入場など外国人に与えられる特典を楽しみました。快適で幸せな生活でした。ニュージーランドに帰国した後、日本への恋しさがあまりにも強くて、まるで肉体的な痛みのように感じるほどでした。
母はニュージーランドを故郷と感じていたため、日本に帰ることはありませんでした。1960年に国籍を取得しました。母はホークスベイで週7日働き、年に2週間しか休まないという厳しい生活を送っていましたが、子供たちに日本の文化と伝統に対する誇りを教え込むために多大な努力を払いました。
母は1995年に61歳で亡くなりました。父は母の遺骨の一部を日本に返還したいと考えていました。そこで私は1998年に夫と生後10ヶ月の赤ちゃんを連れて母の故郷を訪れ、叔父に母の遺骨の一部を家族の墓に埋葬する許可を求めました。彼らは私たちを暖かく迎え入れ、数日間泊めてくれたので、私は恩義を感じました。2002年に父と私の末の妹は母の遺骨を持って津山に行き、手続きを完了しました。
私は小さな方法で日本の伝統を守っています。娘のマチルダ(現在24歳)と一緒に、母に教わったのと同じ方法で竹の葉の船を作りました。また、唐揚げ(私たちは「JFC」と呼んでいます、日本のフライドチキン)などの日本食も作ります。2019年に家族と一緒に日本に戻り、母方の祖父と曽祖父の家族の記録と写真を見つけました。
60 年代に私たち家族がホークス ベイ ファーマーズ ミート カンパニーの冷凍工場に初めて移り住んだとき、家の裏庭は真っ白なキャンバスでした。日本らしさを感じさせるため、両親は庭の景観を変え始めました。両親は長方形の芝生を桜並木で区切ったほか、フェンスの一部に竹を植えました。残った芝生には、両親が土を盛り上げて 2 つの優美な「山」を作りました。一方には、針葉樹の長い松の木と、「平和」と「愛」の 2 種類のバラの木を植えました。松とバラ、日本とニュージーランド、この 2 つの要素は非常に異なっていましたが、なぜかうまく調和していました。
© 2021 Joanna Boese
ニマ会によるお気に入り
特別企画「ニッケイ物語」シリーズへの投稿文は、コミュニティによるお気に入り投票の対象作品でした。投票してくださったみなさん、ありがとうございました。