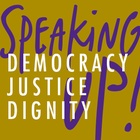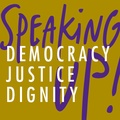1.はじめに
19世紀末から20世紀始めにかけて、アメリカ西海岸と同様、ハワイにも多くの日本人移民が渡った。そして1900年にはすでにハワイ全人口の40パーセント近くを日系が占めるまでになっていた。

オアフのカワイロア砂糖プランテーションで働く福島県出身の一世女性。1906年。Collection of Barbara Kawakami, Japanese American National Museum (NRC.1997.41.1)
1910年代までは、砂糖プランテーションの労働者の多くが日本人移民であった。19世紀末から20世紀初頭は労働条件が特に悪く、砂糖プランテーションでは、日本人移民が中心となった特に大規模なストが1909年と1920年の2回にわたって行なわれた上、他のエスニック・グループのストも行なわれた。しかし、砂糖産業を握る5大企業Big Fiveの力は大きく、労働者側の勝利になることはほぼなかった。労働争議を起こすことは、労働者にとってはかなりのダメージになったのである。1920年のスト以降、オアフ島ではストに参加した日本人労働者が元のプランテーションに戻らず、ホノルルの街に出て仕事を始めたり、借地をしてキビ作りをしたり、別の仕事につくものもいた。
この報告では、1930年代の短歌、俳句、川柳の中から、まずサトウキビ畑の労働の様子や情景を詠ったものをざっと見る。次に、当時の世相や労働状況を一世の歌人がどう見ていたのか、それがわかる歌を紹介する。
そして、1930年代から40年代にかけて、ハワイの労働状況はどうだったのか、その概略を述べ、第二次世界大戦後、平等をめざして立ち上がった労働運動家やその中での二世の活躍を一世がどう見ていたのかが窺われる歌や句を紹介したい。二世の行動に対する一世の晴れやかな気持ち、誇り、さらに複雑な心情に思いをはせてみたい。
2.サトウキビ・プランテーションでの労働
蔗伸びて 町遂に見えず なりにけり
(横山松青1939年作品『アイカネ』所収)
人語らず カチケンの音 聞こえけり
(横山松青1930年作品『アイカネ』所収)
黍畑の様々な労働を詠った歌句はたくさんある。サトウキビは育つととても背が高くなる。黍に穂がでてくると、サトウキビは甘さをましていく。穂蔗も季節をあらわしていた。そしてそれを刈り入れる。カチケンとはcut caneのことである。
蔗(きび)流す 高樋視張る 日永かな
(玉兎 ヒロ蕉雨会 互選句 1935年3月)
蔗切って 長蛇の樋や五月晴れ
(横山松青1930年作品『アイカネ』所収)
春立つや 樋を流るる 蔗の音
(紫洞 ヒロ蕉雨会 互選句 1933年1月)
黍切りし山畑にゆるうフルームのうねりがみえて夏の朝ばれ
(増田玉穂 『銀雨』1925年出版に所収)
刈り取られたサトウキビは黍畑に張り巡らされた樋(これを「とい」とか「かけひ」と呼んだが、英語のflumeを使ってフルムやフルームといったこともあった)にサトウキビを流して、砂糖工場へ運ぶための集積所に集めたという。「長蛇の樋」と詠われているように、長い蛇のように、黍畑を樋がくねくねと曲がって通っていた。樋には、非常に高いところを通っているものもあった。
また黍を運び積み上げる仕事はハパイコーと呼ばれ、大変力のいる仕事であった。そうした姿も歌に詠まれている。
蔗積みや 声頑丈に 陽は強く
(紅流 ヒロ蕉雨会 互選句 1933年5月)
砂糖を積んで本土へ船出した砂糖船を詠った歌も多い。
砂糖船 島の夜を出る汽笛かな
(横山松青 『アイカネ』所収)
砂糖船は、『布哇歳時記』によると春の季語となっている。カチケンが終わり、ハワイの製糖工場へ運び込まれたサトウキビは、煮詰められ糖分が抽出されて粗糖ができる。それが砂糖船に積まれて、アメリカ本土の砂糖精製工場へと送られて行った。この句は、砂糖船が何隻も本土に向かって行く収穫の季節を詠っている。一方刈り取られた畑は焼き畑にされた。
蔗焼(きびやき)や 夜目(よるめ)にはラバの 流れとも
(夕鳥 ヒロ蕉雨会 1934年2月例会句集)
甘蔗を這ふ 野火(のび)の煙や 春暑し
(静雅 ヒロ蕉雨会 1934年3月例会句集)
これらの句は、焼き畑の様子をうたっている。枯れた黍畑に火を放ち、焼く風景は、やはり俳句のよき題材だった。ラバとは、火山の溶岩のことである。この句はハワイ島の黍焼きの様子をうたっており、黍焼きの火が、夜になると、火口から熱いラバが流れている様子にも見えるということである。
秋、製糖場の煙突から立ち上る甘い香り。これも歌詠みの心をくすぐっている。
製糖場(せいとうば)の甘きほめきや 秋暑し
(豊村 ヒロ蕉雨会 互選句 1933年11月)
3. 1930年代の日系コミュニティと30年代の労働争議
こうした歌を見ると、ハワイの砂糖プランテーションでの労働はのどかで豊かなイメージを持たれるかもしれない。もちろん、家族や写真花嫁の呼び寄せによって、移民一世の生活も潤いのあるものになっていったことは事実である。1930年代のハワイ日系コミュニティは、実は「ハワイ日系文化」を謳歌した時代でもあったのだ。だが実は仕事は厳しく、砂糖プランテーションキャンプでの生活は楽なものではなかった。もちろん、ハワイでも1930年代になると、世界恐慌の影響を受けた。そしてこの時代、労働者は待遇を改善するためにともに立ち上がらんとした者たちもいた。だが、1930年代に、他のエスニック背景を持つ労働者たちとコミュニケーションの壁なく、一緒に活動できた日系といえば、二世世代になるのだが、この時期成年に達していた二世の数はまだまだ少なかった。
また、俳句、短歌を楽しむ日系は、日本語話者である一世であったため、自ら労働者として立ち上がらんとする声を表す歌や句は、まだあまり見つけられていない。しかし、スト(罷業)を客観的に見たり、罷業の影響を受けて読まれた句や歌は見受けられる。
ハワイの砂糖産業は、プランテーションを持つ大会社が、砂糖生産、つまり土地を耕して甘蔗を植え付け、世話をし、収穫し、アメリカ本土の製糖会社へ積み出すところまでの、その生産行程全てを取り仕切っていた。運搬手段となる砂糖列車や先ほどの樋の設置と見張り、灌漑、砂糖船の整備から操縦、労働者の食料調達、住居の整備と、何から何までである。
ハワイでは主に5つの企業がこの産業を支配していたことから、Big Fiveと呼ばれていた。これまで見てきた歌や句は、サトウキビを育てるプランテーションを見ての句であったが、実は日系が従事した砂糖の仕事は、多様であり、どれもがBig Fiveの傘下にあったといっても過言ではない。農場労働者だけでなく、波止場の労働者もまた、多くのエスニック背景を持つ移民一世、二世であり、その労働条件は厳しいものだった。
また、ハワイの商品作物は砂糖とパイナップル、コーヒーが中心で、一般的な食料(野菜、果物)、生活必需品はアメリカ本土から船で取り寄せていた。そこで、もし、港湾労働者がストにはいるとハワイの日常生活はダメージを受けることになった。
実は、1930年代、ハワイ社会は変化の中にあった。本土西海岸で盛んになってきた労働運動の洗礼を受けた白人の労働運動家が次々にハワイをおとずれ、ハワイの労働者の状況をつぶさに見て、エスニックを越えた労働者の組織化に着手したからである。そして不況の中の1930年代、実はハワイのあちこちで小規模なストがおこっていた。1936年には、港湾ストも行なわれた。それまではストが行なわれても単一のエスニック背景をもつ労働者のスト(つまり日系だけとかフィリピン系だけというスト)であったし、地域的にも限定された上、5大企業Big Fiveの力が官憲側に及んでいたこともあって、なかなか成功しなかった。それが少しずつ変化を見せ始めたのが1930年代だったのである。
ハワイ島に住む一世歌人らが詠んだストの様子をあらわす歌や句を紹介しよう。
<罷業断行>
ただならぬ海の匂ひや 秋曇り
(夕鳥 ヒロ蕉雨会 互選句 1936年11月)
秋霖に 警吏護衛の 荷揚(にあげ)かな
(芙蓉 ヒロ蕉雨会 互選句 1936年11月)
罷業船の 煙細しも 秋の雨
(紅嵐 ヒロ蕉雨会 互選句 1936年11月)
秋霖や 罷業者 警吏と対陣す
(芙蓉 ヒロ蕉雨会 互選句 1936年11月)
以上のように罷業者つまりストライカーが波止場や街で見受けられる様が語られている。ハワイ島のヒロは雨が多い場所なので、ストライカーが雨にぬれて警官とにらみ合いになっている姿は、歌詠みの心に響いたのではないか。
<船舶の大罷業について>
かんづめにされし旅客や 島の秋
(一星(横山松青) ヒロ蕉雨会 互選句 1936年11月)
ハワイでは、ホノルルのあるオアフ島が政治経済の中心であるから、離島つまりハワイ島、カウアイ島、マウイ島などいると、船でホノルルに向かわねばならないことがよくある。しかし船舶がストをすればホノルルへの交通手段はそれしかないので、結局離島にかんづめにされることになったというわけである。
<罷業繋船>
芋の芽の 船にはびこる 小春かな
(紫洞 ヒロ蕉雨会 互選句 1936年12月)
罷業終結の号外飛んで街うらら
(葉洗 ヒロ蕉雨会 互選句 1937年1月)
食料品として芋を積んでいた船がストで港にずっと足止めを食らっている間に、芋から芽がでてそれがはびこっている様がうたわれている。それだけ長い間ストが続いていたのである。スト終結を詠った歌句からは、スト自体の勝敗より不自由な生活から解放される喜びが感じられよう。
*2013年7月4日から7日にかけて行われた全米日系人博物館による全米カンフェレンス『Speaking Up! Democracy, Justice, Dignity』での日本語セッション「一世の詩、一世の声 (Issei Poetry, Issei Voices)」のセッションでの発表原稿です。
© 2013 Mariko Takagi-Kitayama