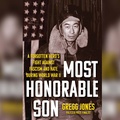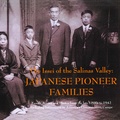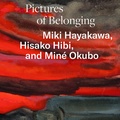パート2を読む>>
私が次にエンブリー氏に会ったのは 1973 年 6 月 5 日、カリフォルニア大学アーバイン校でアジア系アメリカ人にとっての戦時中の強制収容所体験の象徴的な意味について彼女が行った講義に合わせて行われた。
講演の後、彼女はマンザナー委員会のもう一人の二世女性、エイミー・ウノ・イシイとともに、私とカリフォルニア州立大学フラートン校歴史学部の二世の同僚で友人のキンジ・ヤダとキャンパス近くのパブで食事と飲み物を楽しみ、会話を交わした。(ちなみに、エイミー・ウノ・イシイは、いわゆる日系アメリカ人補償の父で原田家の一員であるエジソン・ウノの姉である。)
その晩私と一緒にいた3人の二世は、全員1920年代生まれで、ロサンゼルスの日系社会で育ち、多くの知り合いや思い出を共有していた。エンブリーとヤダは以前に会ったことはなかったが、戦時中はマンザナーで隣同士のブロックに住んでいて、お互いの家族のことを知っていた。
彼らの過去は複雑に絡み合っていたため、ほんの数分で私たちは戦前と戦中の二世の世界について夢中になって話していた。数ヵ月後、ライマンの学問のスクリーンを通してその夜の会話を振り返ったとき、私たちの会話の大部分がスポーツ、映画、音楽、そして純粋な郷愁といった些細なことに費やされていたことに気づいた。
しかし、実のところ、私の二世の会話相手、特に二人の女性たちが、婉曲表現、婉曲表現、作話、沈黙、あるいはライマンが言及した感情管理のその他の手段を使っていたとは思い出せなかった。むしろ、彼らの会話の私の記憶は、それとは反対の、開放性、親密さ、率直さ、表現力、主体性へと向かっていた。
私はエンブリーと二度直接対面していたため、彼女の性格はライマンの理想の二世のタイプと矛盾しているという観点から、オーラル ヒストリー インタビューに臨んだ。ライマンの構築から、それがほぼ完全に二世の男性との会話に基づいていると推測した。ある時点で、彼は「二世の男性の主な関心事は、自分の感情を経済的に管理し、制御することだ」とさえ明確に述べた。さらに、私はライマンが述べた警告を真剣に受け止め、理想のタイプについて繰り返した。理想のタイプは、より乱雑で複雑な現実を説明するのではなく、表現するために設計された精神的な構築物であるため、あらゆる面でどの個人にも当てはまるわけではない、と。「特定の二世は、説明されたすべての特性を備えているわけではありません。また、この類型論は、日本人コミュニティの外で育った二世や、主に非二世の仲間グループと付き合っていた二世には当てはまらないかもしれません」とライマンは説明した。
講演後の会話で、エンブリーは日系社会で育ったことを知ったが、彼女の姓がエンブリーであることから明らかなように、彼女は異人種間結婚をしていたことも知っていた。さらに、マンザナー巡礼での彼女の「パフォーマンス」から、彼女の過去の交際は主に世代内(二世二世)のものだったかもしれないが、マンザナー委員会への参加により、最近の主な交流は活動家である大学生の三世三世との世代間交流になっていることに気づいた。実際、これらの三世の何人かは、第二次世界大戦の日系アメリカ人の強制収容所体験に関する世代的な視点を表明するために、彼女を私の講演シリーズに含めるよう強く勧めていた。
インタビューが始まると、エンブリーの態度は、録音された会話に対する私のアプローチが適切だったことを証明した。彼女の世代的「逸脱」は、彼女の話の内容とスタイルの両方に表れていたからだ。岡山県の同じ村に住む一世の両親の8人兄弟の6番目として生まれた彼女は、自分のルーツを探ることをためらうどころか、家族の歴史を熱心に語った。同様に、ロサンゼルスのリトル東京地区(日本町)での幼少時代や、戦前の日系コミュニティの内部事情についての私の探りを入れる質問にも、彼女は機敏かつ詳細に答えてくれた。
エンブリーの率直な話し方はインタビュー全体を通じて貫かれていた。例えば、会話がマンザナーのさまざまな政治派閥、特に日系アメリカ人市民連盟(JACL)の「準管理者」や、エンブリーが勤務していた収容所の新聞(マンザナー・フリー・プレス)の編集部を牛耳っていた左翼の「進歩主義者」に移ったとき、彼女のメッセージと話し方は再び彼女の世代的周縁性を示した。
AAH:マンザナー・フリー・プレスの初代編集者だった女性の名前は何ですか?
SKE: 森千恵さん。戦前は民主クラブ(二世青年民主党)でかなり活動していたと思います。JACLで活動していたかどうかはわかりません。
AAH: 避難当時、彼女は何歳くらいでしたか? 彼女はあなたと同世代だったのですか?
SKE: いいえ、彼女は私より年上だったと思います。私は彼女のことをよく見ていました。というのも、私にとって彼女はとても珍しい二世だったからです。彼女のように政治について語り、私たちの国の指導者を非難する人には出会ったことがありませんでした。私はそのような話を聞いたことがありませんでした。彼女は私が出会ったことのないようなとてもリベラルな考えを持っていて、私は彼女の話をよく聞いていました。
AAH: [チエ・モリ以外に] [マンザナーの] 中道左派グループに属する特定の人物を思い浮かべることはできますか?
SKE: はい。現在ホノルルに住んでいる有吉孝二さんとカール・ヨネダさんがいました。他にはどんな人がいましたか?
AAH: 彼らは、戦争前にあなたが「赤」と表現したグループの一部でしょうか?
SKE: 国民はそう考えていたと思います。彼らがどれほど活動的だったかはわかりません。カールもコージも戦前は労働組合で非常に活動的で、少数派グループにも労働組合を開放しようとしていたことは知っています。彼らの思想は、まずファシズムと戦わなければならないという考えに基づいていたと思います。そして、彼らは避難を、戦争中に起こらなければならない些細なことの一つとして受け入れていました。
AAH: 彼らはマンザナーの日本人[アメリカ人]コミュニティからJACL派と同じくらい嫌われていたと言えますか?
SKE: そうだと思います。はい、彼らの中にはJACL関係者だけでなく暴行の被害者もいたと思います。しかし、彼らは戦前にやっていたことと全く違うことをしていたわけではないと思います。
4か月後のエンブリーとの2回目の録音セッションで初めて、私は、彼女が同世代の慣習的な行動からどれほど大きく、多様に逸脱していたかを知り、比較的物静かな二世から公民権、社会正義、人間の尊厳を声高に主張する戦後の彼女の変貌の理由を知ることになった。
* これは、2012 年 10 月 20 日にカリフォルニア州リバーサイドのリバーサイド メトロポリタン美術館で行われたプレゼンテーションで、レーン ヒラバヤシ編集の NIKKEI IN THE AMERICAS シリーズとしてコロラド大学出版局から出版された、マーク ハウランド ラヴィッチの 2012 年の著書『 The House on Lemon Street: Japanese Pioneers and the American Dream』の出版記念プログラムの一環として行われたものです。
© 2012 Arthur A. Hansen