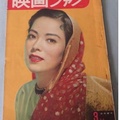>>パート2を読む
受け入れられている教義と新しい現実の間に違いがあることを発見したことを正統派に納得させるために一生を費やすのは、ひどく苛立たしいことだろう。文化的フジツボが科学的教義という理論船から取り除かれるまでには、しばしば何億年もかかる。ベティ・ジェーン・メガーズ博士の叙事詩は、フジツボ除去の最も優れた試みの一つである。おそらく人類学の最も著名な異端者メガーズは現在、良い仲間がいるが、それは彼女がエクアドルで精力的に働いてから何年も経ってからだった。
少し歴史を調べてみれば、1930 年代半ばにメキシコの人類学者エウラリア・グスマンが、メキシコのいくつかの文化、特に彼女が深く研究したオトミ族1 には中国の影響が強く残っていると強く感じていたことがわかります。当時のメキシコの複雑な政治は教育にかなり悪影響を及ぼし、グスマンは自分の主張を証明するために個人的な旅に出ることを思いとどまりました。
1950年代、メキシコの民族学者で芸術家のミゲル・コバルビアスは、メキシコ・インディアンの歴史はコルテスよりわずか1500年前に始まっていたという説を主張した。コバルビアスは、その優れた著書『メキシコ南部』 2 、特に『鷲、ジャガー、蛇』 3で、オルメカ文化におけるアジア人の存在を強く主張した。当時、南西部とメソアメリカの人類学の第一人者であったアルフレッド・V・キダー(1885-1963)は、同僚らがより良い理論を展開しようとする努力を文化的閉塞感として批判した。
数年後(1992年)、メキシコ生まれの人類学者セリア・ヘイル4は、メキシコ南西部のミチョアカン州のプレペチャ5文化を長年研究した後、南アジアから来たものとよく似た工芸品(宝飾品、儀式や祈りのための銅鐸、道具など)に彼らが冶金技術を巧みに利用していたことに関する重要な論文を発表しました。彼女は、メキシコ南西部の文化の中に、初期の製紙技術など、他の多くのアジア文化の特徴を発見しました。6
1995 年、彼女はプレペチャの漆器の技法に関する記事を書き、日本 (および中国) の実用的および装飾的な作品で使用されている技法と比較しました。プレペチャはスペイン人が到着するずっと前から漆器細工に携わっていました。彼女は『メチュアカン州の先住民の儀式、儀式、民衆、政府との関係』の中で、プレペチャの長老たちがフランシスコ会宣教師マルティン・デ・ラ・コルーニャとヘロニモ・デ・アルカラに 1541 年にこの件について書いた報告書を引用しています。7
ヘイルは、プレペチャの漆塗り技法を示す「マケ」という語が日本の漆塗り技法である蒔絵によく似ていること、また、漆の一般的な日本語である「ウルシ」とプレペチャの漆塗り生産の中心地である「ウルアパン」の響きが似ていることを指摘した。3番目の記事9で、ヘイルは日本の草履であるワラジとメキシコのワラチェの類似点について述べている。
次にご紹介するのは、著名なイエズス会の科学者エウセビオ・キノ神父の遺骨を発見したメキシコの人類学者で建築家のホルヘ・オルベラ博士です。粘り強さと決意、そしてソノラ砂漠での長く困難な日々を経て、オルベラ博士と彼の探検隊は、ピメリア・アルタの奥地にあるソノラ州マグダレナの荒涼とした小さな礼拝堂で墓を発見しました。オルベラ博士はまた、メキシコとスペインの忘れ去られたが重要な教会に関する重要な研究をいくつか行いました。
オルベラは、メキシコ南西部の先住民文化であるミシェ・ソケ族の文化人類学者として 10 年間勤務した後、スペイン語で 80 ページに及ぶ小冊子を執筆し、その長いタイトルは「ミシェ・ソケ族と古代日本語の間のいくつかの語彙の類似点」でした。この本は、メキシコのチアパス州の文化機関 CONACULTA から 2000 年に出版されました。オルベラはソケ語を流暢に話せるようになり、ソケ語の特定の単語と文法構造が古代日本語に似ていることに気づきました。彼は、その疑念を、メキシコ駐在の日本大使の息子で親友の建築家アルベルト・アライに伝えました。アライも同意し、オルベラは 600 近くの語彙を収集してリスト化し、古代日本語と祖語の専門家によるさらなる分析に提供しました。
しかし、オルベラを困惑させ、魅了した別のものがあった。会話や社交の際のゾケ族の姿勢、年長者への敬意、儒教の教えに近い孝行、そして古典的なお辞儀。これらすべてが、まるで古代日本の文化を観察しているように感じさせた。11 驚いたことに、ゾケ族の世界創造神話には、イザナギ、イザナミ、その他の神に似た人物が登場した。12それらは古事記や日本書紀から抜き取られたかのようだった。彼らの伝説の一つは、桃太郎の物語にさえ似ていた。
多言語(スペイン語、英語、日本語、ソケ語)のオルベラには、この小さな作品を英語に翻訳する時間も機会も意欲もなかった。CONACULTA はこの作品を 1,000 部に限定したため、手に入れるには奇跡が必要であり、そのためオルベラの作品は無名のまま、同業者によるレビューも受けず、認知されていない。
もちろん、グスマン、コバルビアス、ヘイル、オルベラについて最初に挙がる意見は、植民地時代以来、メキシコ人は強い、抑えることのできない親日感情に感染しているということだ。日本、その文化、そして日本国民に対する愛着は、マニラ・ガレオン船の全盛期、1610年に最初の日本商船団がメキシコに到着したときに始まった。13 1614年、仙台の伊達政宗は支倉六右衛門常長を大使として派遣し、メキシコ(ヌエバ・エスパーニャ)との直接通商を開始した。支倉は大勢の随行員を連れてきた。14その集団のメンバーの多くは、メキシコに留まり、その社会に溶け込むことを決めた。やがて、多くの日本人の姓が、名高いメキシコ人一家(メキシコの名家)のリストに名を連ねるようになった。この相互の尊敬の念は年月をかけて高まり、太平洋戦争の恐ろしい時代にも変わらなかった。
しかし、考古学者、人類学者、民族学者、言語学者の発見は、相互の好意を超えたものである。
私はオルベラの考えを、著名な学者(前近代日本研究の会員)であるPMJS-Google (日本文化に関する話題を扱う興味深いインターネットサイト)に検討してもらうよう提案した。残念ながら、反応は期待外れだった。私の問い合わせに回答してくれた 2 人の言語学者のうち、1 人は最初の 10 語の概要分析を行った後、オルベラの選択を却下した。もう 1 人は、いくつかの語は日本語というよりも古代中国語に似ており、他の語は現代日本語と古代日本語が遠く混ざったもののように思える、と考えた。しかし、日本語の起源、特に原史時代の起源は依然として謎に包まれており、興味をそそられるものであることを忘れてはならない。したがって、ここでは鵜呑みにしないことが非常に役立つ。
アラスカ生まれの人類学者ナンシー・ユー・デイビス博士の並外れた研究に光を当ててみましょう。彼女は彼女の興味深い著書『ズニ族の謎―アメリカ先住民と日本人のつながりの可能性』で丹念に詳細に説明しています。15人類学の文献を読み進めるのを困難にする学術用語を一切使わない彼女の著書は、読者を虜にし、一度読み始めると止められないほどです。人類学の魚雷が浮上しそうになると、デイビス博士は穏やかな説明で読者を苛立ちから救い出します。
デイビスは、日本人とズニ族の接触があったとされる原因を、鎌倉時代にアメリカ西部に上陸した仏教伝道団に限定している。16彼女は自分の理論を証明するために、伝説、神話、伝統、行動、遺物、言語を検討している。それだけでは十分ではないかのように、遺伝子、病気、寄生虫、植物など、接触の可能性を強く証明するハードサイエンスの成功を分析している。野次が来るかもしれないことを賢く予測して、彼女は自分の選択のすべてについて賛否両論を細かく分析し、読者に彼女があらゆる断片を徹底的に調べ上げたという確信を与える。この本を読み終える頃には、「はい!…そういうことだったんですね」とつぶやくことしかできないだろう。
他の多くの著名な科学者も、当初は太平洋横断接触説を支持して拡散論陣営に加わったり参加したりしました。これについては次の章で詳しく説明します。
ノート:
1. オトミ族は、自らをHñähñuと名乗る、メキシコ中央高原の部族です。
2. ニューヨーク:アルフレッド・A・ノップフ、1946年
3. ニューヨーク:アルフレッド・A・ノップフ、1954年
4. ハイル氏は元国立科学財団に所属し、1979 年の米国北極圏研究遠征隊の一員として南極で活動した初のメキシコ人女性でもあります。
5.プレペチャ族はタラスコ(父、義理の兄弟)としても知られているが、これはスペインの征服者がその文化の人々に対して付けた誤った呼び名である。
6. (1992); Across Before Columbus . エッジコム、ME.
7. (1995); NEARAジャーナル; 第XXX巻、1&2号; pp. 32/39
8.蒔絵は、芸術家が装飾を豊かにするために対象物に金粉や銀粉を撒いたり、どちらかで飾ったりする日本の漆芸技法です。
9. 日本とメキシコのサンダル。(2004)プレコロンビアナ、第3巻#1-3
10. アルベルト・アライは、メキシコで最も著名な建築家の一人となった。社会主義者であった彼は、熱帯地域の居住環境には土着の材料を使うことを重視した。彼の最も有名な作品は、メキシコ国立大学 (UNAM) のフロントネス(ハンドボール コート) で、溶岩を使って切り取られたピラミッドを作った。
11. ゾケ族は、お尻を足の上に置き、背筋をまっすぐにした日本人特有の姿勢で座ります。敬意を表すために行うお辞儀は、昔の侍が主君にお辞儀をするのと似ています。
12. 神—神道の信仰における神聖な力。
13. 歴史上、商人の田中正助とその仲間22人は太平洋を渡ってアメリカに渡った最初の日本人であると考えられています。
14. 侍60人と商人130人。
15. (2000); ニューヨーク: WW ノートン。
16. 西暦1250年頃。
© 2010 Edward Moreno