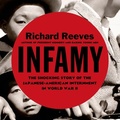私のようにJAで育った人なら、子供の頃にJタウンに行ったことを覚えているでしょう。両親やおばあちゃんと一緒に日本食を買いに行ったり、地元の「チャイナメシ」で焼きそばやパッカイを食べたり、地元の劇場やお寺でサムライ映画を見たり、毎年恒例の教会のバザーで「ダイムピッチ」や「金魚投げ」をしたりしました。
そして、ある人たちにとって、Jタウンへの旅行は、地元の和菓子屋に行き、お気に入りの饅頭を食べることを意味しました。ピンクと白の餅(豆なし)を覚えている人もいれば、栗饅頭、または滑らかな餡の入った白い饅頭、または上にきな粉が乗った緑の饅頭が好きな人もいます。そして、ボタンライスキャンディーの箱も忘れないでください!
覚えていますか?
昔、一世と二世はこの特別な場所を「日本人町」と呼んでいました。現在、サンフランシスコでは「日本町」と呼ばれています。ロサンゼルスでは「リトル東京」、サンノゼでは単に「ジャパンタウン」と呼ばれています。
何と呼ぶにせよ、日系アメリカ人にとって J-Towns は、物理的に居るべき場所であり、精神的にも感情的にも居るべき場所でしたし、今もそうです。仕事、遊び、教会や寺院、あるいは友人と日本食を食べながら過ごすときなど、J-Town、つまりあなたの J-Town はまるで我が家のようです。
私の J-Town の家はサンフランシスコにあり、1970 年から 1971 年頃、母は私と兄弟を日本コミュニティ青年協議会 (JCYC) のサマー デイ キャンプ プログラムに登録しました。それがサンフランシスコの J-Town との最初の出会いだったことを覚えています。また、国際劇場で映画を観たこと、古いアメリカン フィッシュ マーケットに入ったときの独特の匂い、ピース プラザ近くで地域の餅つきを見たこと、毎年恒例の桜祭りのパレードに参加したことも覚えています。
高校時代と大学時代、私はいつも日本町の近くにいました。アメリカンフィッシュで働き、サンフランシスコ仏教教会YBAのメンバーで、一時はキモチシニアサービスで皿洗いをしていました。私はローウェル高校とサンフランシスコ州立大学に通いましたが、放課後と週末は日本町にいました。
私が初めて日本町に足を踏み入れてから約37年が経ち、ロサンゼルスを拠点とする劇団「ザ・グレイトフル・クレイン・アンサンブル」を通じて日本町の物語を語る機会が与えられました。
カリフォルニア州公民権公教育プログラム(CCLPEP)からの助成金によって資金提供され、北カリフォルニア日本文化コミュニティセンター(JCCCNC)を通じて運営されているこのプログラムで、昨年私に与えられた課題は、物語と音楽と歌を通して、2時間以内でジャパンタウンの100年の歴史を語るというものでした。
「サンフランシスコの J タウンとその 100 周年についての話にすべきですか?」と私は尋ねました。最初は、答えはイエスでした。2006 年はサンフランシスコの 100 周年であり、私たちのショーはその祝賀行事の一部となるはずだったので、それはまったく理にかなったことでした。
「よかった」と私は思いました。「少なくとも、焦点を当てる特定の場所がある」。しかし、その後、焦点が一般的なカリフォルニアの J-Town に関する一般的なストーリーに変更されたという電話を受けました。「それは違いますね」と私は言いました。そして、「わあ、これは非常に特定の J-Town からカリフォルニア全体の 40 を超える J-Town に変わった。どうやってそれを実現すればいいのだろう」と考えました。
そこで私はジャパンタウンに関する本や記事を読み始めました。ジャパンタウンを「グーグル」で検索し、インターネットでさまざまな情報を見つけました。そして、サンフランシスコ、サンノゼ、ロサンゼルスに残る3つのジャパンタウンや、サンペドロのターミナルアイランド、ワシントン州シアトルの旧ジャパンタウンなど、他の旧ジャパンタウンも訪れました。戦前のジャパンタウンで育った古い住民に話を聞いて、しばらくするとその場所のイメージが形になり始めました。
私が発見したのは、初期の一世によって設立され建設された J タウンには多くの共通点があることでした。戦前、それらは一世とその二世の子供たちにとって、自給自足で繁栄し、活気にあふれた小さな村であり、安全な避難所でした。通りを歩けば、小さな商店があふれていました。洗濯屋やクリーニング店、ホテルや下宿屋、食料品店、果物屋や魚屋、和菓子屋やパン屋、ドラッグストア、衣料品店や仕立て屋、理髪店や美容院、教会や寺院など、JA 家族の基本的なニーズを満たすものがすべてありました。
しかし第二次世界大戦後、収容所から戻ったのはわずか50%ほどの住民だけとなり、Jタウンはかつてのような姿に戻ることはありませんでした。そして最後のとどめを刺されたのです。1950年代、60年代、70年代の再開発により、州内のJタウンの残っていたすべてが文字通り消滅し、たった3つのJタウンだけが残りました。
こうしたことをすべて知った後、私が本当に興味をそそられたことの一つは、日系アメリカ人の饅頭屋がJタウンで数少ない存続している商売の一つであるように思えたことだ。サンフランシスコには、昨年100周年を迎えた「勉教堂」があり、ロサンゼルスには今年104周年を迎える「風月堂」がある。サクラメントでは、「玉川堂」が72周年を迎えた。そしてサンノゼの「秀栄堂」は53年間続いている。
私も饅頭、餅、鍋が大好きで、子どもの頃から大人まで食べた楽しい思い出がたくさんあります。だから、饅頭屋というアイデアは魅力的な出発点になりました。その時に、3世代100年続く饅頭ビジネスを通じてJタウンの物語を語るというアイデアが浮かびました。
私たちの番組は「日本町:The Place to Be」というタイトルで、物語は2005年の架空の日本町を舞台にしています。私たちの町の饅頭屋「さくら堂」は、99年間の営業を経て閉店することになりました。三世のオーナー、アラン・イワタとジョイス・イワタは19年間この店を経営してきましたが、最近は体力的に負担が大きくなりすぎてきました。
アランは57歳で、腰が悪く、膝も痛い。ジョイスは56歳で、饅頭の箱に紙を巻く作業で手根管症候群になった。2人は引退して、まだできるうちに人生を楽しみたいと願っていた。しかし、アランの祖父で桜堂の創業者である岩田三吉の霊がJタウンに戻ってくる。三吉はアランがなぜ店をたたむのかを問い詰め、アランをあの世、1928年の日本町へと連れて行く。
アランは三世なので、自分の経歴についてはあまり知りません。そこでじいちゃんは、彼をジェイタウンに連れて行き、家業について「教える」と同時に、自分が何者で、どこから来たのかを感謝するように教えます。
旅の途中で、彼は英語の汚い言葉以外は日本語しか話せない元気な一世の祖母と、若い頃の父親に出会う。また、大恐慌時代、戦時中の収容所生活(祖父が饅頭を焼いていた時代)、そして 50 年代と 60 年代の再定住/再開発時代を過ごした家族の様子も描かれる。
また、彼の母親に会ったり、両親の初デートを見たり、新婚旅行で彼が妊娠したジェイタウンのホテルの部屋に招待されたりもするが、彼は「情報量が多すぎる」と言ってその招待を断る。最終的にアランは60年代を追体験し、おばあちゃんの親友が町のホテルから追い出されるのを拒否するのを見る。彼は私たちを70年代のアジア系アメリカ人運動、80年代の補償と賠償を求める戦いと勝利へと連れ戻す。また、アランが家業を引き継ぐこと、そして店を経営しようとして父親と対立し支配権を握ろうとする様子も見る。
これらすべてを知った後、アランは現代に戻り、そこでインスピレーションを得て、店を 100 周年まで続けることを決意します。最後のシーンは、ホテルの宴会場で家族が 100 周年を祝う場面です。アランは、皆の支援に感謝し、100 周年を迎えた今、自分と妻があとどれだけ続けられるか分からないと発表します。しかし、そのとき、誰かが発表をします。それを聞くには、ショーを見に来なければなりません。
ショーの随所には、懐かしい日本とアメリカの古典的歌、故・美空ひばりへのトリビュート、そして、今は亡き一世の先駆者たちへの懐かしい回顧などが散りばめられており、彼らは私たちのショーを通して蘇ります。
そして最終的に、アランの旅は私たちの旅となり、彼の物語は私たちの物語となり、主なメッセージは「Jタウンを死なせてはいけない。100年以上もの間、日本町は「私たちの居場所」だったのだから」です。
ロサンゼルス/南カリフォルニア地域にお住まいの方は、ぜひお友達に伝えてください。ご家族もお連れください。3 月 24 日と 25 日は、J-Town に帰ります。ぜひご参加ください。
* * *
注: 「日本町: 行くべき場所」は、日系アメリカ人文化コミュニティセンター (JACCC) の資金調達イベントとして、2007 年 3 月 24 日 (土) 午後 7 時 30 分と 2007 年 3 月 25 日 (日) 午後 2 時に、ロサンゼルスのダウンタウン、リトル東京の 244 S. San Pedro Street にある Aratani/Japan America で上演されます。(日曜日のオーケストラ席は完売しました。) チケットは、オーケストラ席 35 ドル、バルコニー席 30 ドル、JACCC 会員、10 歳以上のグループ、シニアは 30 ドル、JACCC 会員、10 歳以上のグループ、シニアはバルコニー席 27 ドルです。学生および 15 歳未満の子供は 20 ドルです。チケットと情報については、月曜日から土曜日の正午から午後 5 時までに劇場のチケット売り場 213/680-3700 までお電話ください。
* * *
(cc) DN site-wide licensing statement