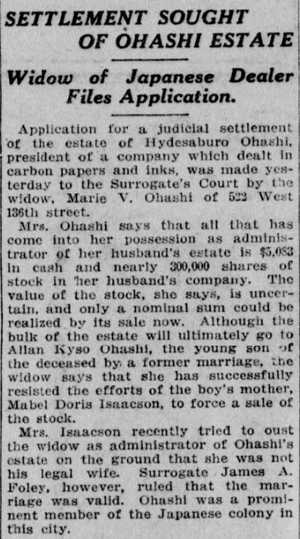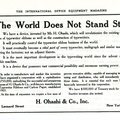大橋がアメリカにいた間、日米の政治関係は着実に悪化していた。1905年に日本がロシアに勝利した後、日本は次にアメリカと戦うだろうと一般に考えられていた。太平洋の両側で、日本がアメリカの代理として戦争に臨んだと考える人がいたことは問題外だった。1905年、アメリカ労働総同盟は、議会に対し、日本人労働者をアメリカとその海外領土から排除する法律を直ちに制定するよう要請した。1906年、カリフォルニアで日本人児童の公立学校への通学問題で反移民運動が激化したため、セオドア・ルーズベルト大統領は介入せざるを得なかった。1 1907年頃、アメリカと日本の軍事戦略家はそれぞれ相手側を次の戦争の敵と見なし、両国は移民管理について交渉した(すぐに「紳士協定」が結ばれ、日本人のアメリカ入国を制限した)。特に西部と南部における日本人に対する法的、社会的差別は、画期的な移民排斥法が議会で可決された1924年にピークを迎えた。
人種差別(当時は多くの人が科学的根拠があると信じていた)と移民問題はさておき、大橋が事業を展開し社会改革を促そうとした日米関係のより大きな環境には、問題を引き起こす経済、産業、商業上の問題があった。つまり、第一次世界大戦が紛争を引き起こし、それを表面化させたのだ。1902年にイギリスと同盟条約を結んだ日本は、ウッドロウ・ウィルソン大統領よりずっと前にドイツに宣戦布告した。日本はヨーロッパへの兵隊派遣を断ったが、輸送船を派遣し、太平洋の海上交通路を哨戒し、ロシアに軍需品を提供し、青島(現在の秦島)のドイツ海軍基地にあったドイツ太平洋艦隊のほとんどを損傷、沈没、または拿捕した。ウィルソンは、パリ講和会議で交渉された国際連盟規約に日本が盛り込むよう提案した人種平等条項を抑制したが、日本は青島の管理権と赤道以北のドイツ領土に対する委任統治領を獲得した。
これらは間接的な利益に比べれば取るに足りない。日本は戦争中に主要な労働年齢の国民の大部分を失ったわけではなく、商船隊も失わなかった。日本はインフラや工業能力も失わなかった。日本は海外市場も植民地も失わなかった。日本はドイツからの化学製品やその他の製品の供給を断たれたが、それが代替品の開発を促した。間接的な利益には、軍事経験の少量化だけでなく、大国とともに戦争に臨んだ軍事大国の一員であるという意識の強化も含まれていた。日本は連合国に加わるのにほとんど犠牲を払わず、交戦国が支配する市場に進出したために紛争が起きた。多くのアメリカのビジネス界や産業界は警戒した。戦争に注目が集まっているときに日本が中国に21ヶ条要求を課したと聞いたとき、日本はアメリカからの好感度を失った。これがなくても、アメリカには親日感情はほとんどなかった。1917年7月、熱狂的な保護主義と関税支持の防衛雑誌「アメリカン・エコノミスト」は「日本に気をつけろ!」と警告した。 「中国の政治と産業を支配することが日本の政策の要である」など、同様の主張が次々と展開されている。2
成功の見込みがどうであれ、親日派が組織化して声を上げることには確かに正当な理由があった。ボストンでクラブを結成しようとした以前の試みからもわかるように、大橋はアメリカの日本に対する政治的、社会的疑念を確かに認識していた。これらは日本クラブと日本協会の会員にとって現在関心のある話題だった。日本政府は金子健太郎男爵をアメリカに派遣し、彼の能力と人脈を利用して「黄禍論」の恐怖に対抗し、ロシアとの戦争で日本への支持を募らせたので、金子健太郎男爵はおそらく大橋を支援または奨励しただろう。
金子は1874年にハーバード大学に4年制大学に入学し、その2年後にロースクールに入学したセオドア・ルーズベルトと時期が重なっていた。この日本人外交官がルーズベルトと(初めて)会って自分の主張を述べるには、これで十分だった。ニューヨーク滞在中、金子は少なくとも1度はボストンを訪れ、1904年4月28日にハーバード日本クラブの会合で講演した。金子は大橋と会うこともできただろうし、大橋も可能であればその会合に出席していたはずだ。後に、ルーズベルトは、日本国内の野党が戦争を求めるに至った日米関係の悪化を懸念し、金子に日本に関する情報を求めた。金子が送った本は、新渡戸稲造の『武士道』だった。
ニューヨーク・タイムズ紙によると、日米関係の個人的な面では、大橋未亡人は、大橋氏から「日本人はアメリカ人に好かれておらず、アメリカ人に訴えられてもアメリカの裁判所で公正な裁判を受けることはできない」と言われたと語ったという。ライバル紙のニューヨーク・トリビューン紙は、ほぼ同じ記事で、大橋氏が、アメリカ人女性と結婚した同胞の中には、女性の気まぐれに左右され、ちょっとした口実で女性が離婚訴訟を起こす可能性があると語ったと伝えている。3マリー氏は、大橋氏が離婚の際の慰謝料を避けたかったため、婚前契約を提案したと述べた。実際、彼はアメリカにおける日本人の状況をよく理解していた。それは、1914年に日本人フランチャイズ連盟を設立したことからも明らかである。年会費1ドルのこの組織の目標は、日米相互理解を深めるための教育システムを作り、「ここに永住する日本人に、最終的にはすべての憲法上の権利とそれに付随する特権を保証する」ことであった。4しかし、日本人移民が米国市民権を取得できるようになったのは1952年になってからであった。秘書が任命され、ブロードウェイ395番地にあった大橋の会社に事務所が開設されたものの、残念ながら、公平な扱いを求めるためのさらなる努力、そして最終的には市民権を求める権利につながる可能性があったこの試みは、大橋の早すぎる死により実現することはなかった。
ここに、日本の近代化が始まったばかりの頃に始まり、日本とその国際環境に大きな変化をもたらした 3 つの戦争 (中国、ロシア、ドイツとの戦争) での勝利で終わった、特異な人生がある。文化的、経済的に有利なスタートを切り、質の高い教育を受けた大橋は、潜在的なエリートの地位に就き、アメリカ人と 4 回も出会い、起業家精神と創造性で苦難を乗り越えた。この創造性によって、詩を書く知識人であった若き大橋は、当時の日本とアメリカの対立を体現する成功したビジネスマンになった。そして、病気で短くなった彼の人生は、タイプライターとそのリボンに革命を起こしたり、国民のために社会正義と人種平等のために物事を動かしたり、ましてや個人的な夢を追求する前に終わった。パンデミック インフルエンザに屈したため、それらはすべて無駄になった。大橋の刀は現在、ペンシルバニア州に住む大橋の曾孫、アニタ 大橋の手に渡っている。
注記
- 関与したのは23校の生徒93人だけだった。
- 「日本を監視せよ!」アメリカンエコノミスト、1917年7月13日、17ページ。
- 「日本人が2番目のアメリカ人と『紳士協定』で結婚」ニューヨーク・トリビューン、1920年12月8日、4ページ。また「大橋邸宅の和解を求める」ニューヨーク・ヘラルド、1921年9月4日、5ページも参照。
- 「簡潔な平和ノート」『平和の擁護者』第74巻第3号(1914年3月):56。
© 2025 Aaron Cohen