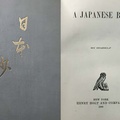2010 年に私が初めて出席した日系カナダ文化遺産委員会の会議では、メイン イベントの前夜に招かれ、歴史的背景を説明するウォームアップを行いました。昨年の Keisho 会議では、出席して最後に感想を述べるよう依頼されました。今回は、初日の朝にキックオフ スピーカーとして、その後は審査員として、両方の立場で出席しました。会議に対する私の個人的な感想を正直に評価し、それについて考えるという任務を引き受けることができて、とてもうれしく思っています。

グレッグ・ロビンソン教授(右から2番目)が、Keishoカンファレンスの最終日のパネルに出席。講演者は日系カナダ文化センターのSedaiプロジェクトのコーディネーター、エリザベス・フジタ氏(日系カナダ文化センター提供)
まず、私にとってこの会議はとても満足のいく経験だったと言えます。週末を通して、私は何人かの新しい人々と会い、話をしました (持参した名刺のストックを全部使い切りました)。また、以前の会議で会った人々とも会いました。私は語り手の話を聞いて、知らなかったことをたくさん学びました。実際、私は会議でとても元気づけられたので、最初の夜の夕食の時間後も、残っていた何人かと帰るまでそこにいておしゃべりし、その後、何人かと飲みに行きました (私はまだ勤務中だったので、ノンアルコールでした)。会議のまとめのために自分の考えを整理しようと部屋に行ったときには、もう遅くなっていましたが、興奮の余韻がまだ残っていました。
会議に出席できなかった方々のために、そしてさらに重要なことに、会議の意味を理解していただくために、会議の感想をまとめたいと思います。週末の活動は、日系カナダ文化会館事務局長のジェームズ・ヘロン氏と元事務局長のマイク・オイカワ氏による素晴らしい開会の辞で始まりました。ジェームズ氏は英語だけでなく日本語でも話しました。私自身、日本語がほとんど話せないので、その流暢さにうらやましく思ったことはさておき、これは新日系人(新一世)と彼らの戦後の生活経験を認める素晴らしい発言だと思いました。日本からカナダへの移民は、この会議の最終年である1967年まで厳しく制限されていましたが、戦争花嫁として渡った人々を含め、戦後、何人かの日本人がカナダに渡りました。
その後、私は講演を依頼されました。私は、日系カナダ人の戦後の経験は歴史文献の点でまさに「ブラックホール」であり、私にとってこの会議は、私たちの一般知識の穴を埋めるために、語り部とつながる貴重な機会であると述べました。私が最近出版した本「AFTER CAMP」で詳しく扱った日系アメリカ人の戦後の経験(それ自体あまり研究されていないテーマ)との類似点をいくつか指摘した後、戦後の日系カナダ人に関する私自身の研究、特に彼らの再定住、家族生活、仕事と住宅、スポーツ、公民権についていくつか話しました。
私は、ドキュメンタリー資料を読んで知ったこと、そしてそれを補うために個人からどのような情報が必要かを説明しました。私の結論は、人々の物語を見つけることが家族や地域社会のメンバー、そしてカナダ社会全体にとって重要であるため、この会議は人々の物語を見つけるために開催されたというものでした。
聴衆は非常に熱心に聞いていましたが、後になって私が言ったことを聞き取れなかった人もいたことを知りました。また、後になって私に近づいてきて、さまざまな点について役立つ情報を提供してくれた人もいました。たとえば、私は都市対抗野球やボウリングリーグなど二世スポーツの人気について話しました。後になって知ったのですが、戦後、トロントの二世野球チームはシカゴまで遠征して、地元のチームとトーナメントで対戦したそうです。
また、ボウリングが二世の間でなぜそんなに人気があるのかと尋ねられた。私の推測では、ボウリングは一年中できる室内競技であり(冬のカナダでは些細なことではない)、良い運動になるからだろう。また、平均的にそれほど背が高くも体重も重くもない二世にとって、他の人たちと対等にプレーできるスポーツだった。(実は、私はつい最近、日米ウィークリーの定期コラム「偉大なる未知」に、1940年代後半に日系アメリカ人市民連盟が労働組合やアフリカ系アメリカ人団体と力を合わせ、ミネアポリスの若き市長ヒューバート・ハンフリーが率いる全国ボウリングフェアプレー委員会で、アメリカボウリング協会の白人限定政策に異議を唱えることに成功したという記事を掲載したばかりだ。)
私のスピーチの後、その日の活動の中心となった 3 回のストーリーテリングの第 1 ラウンドが行われました。ストーリーテリング セッションは形式が同じだったので、全体についてお話しします。ストーリーテリング セッションは、戦後の経験の地理的多様性を非常に示していると思います。戦争中に移住させられたスローカン バレーの「ゴースト タウン」の 1 つであるニュー デンバーに留まり、病気の家族の世話をするために追放を免除された人もいました。
1949 年半ばに西海岸が再開すると、一部の人々はそこへ戻りました (語り手の 1 人は、西海岸が再開すると父親が家族を連れてスティーブストンの漁村へ戻りましたが、数か月後にボート事故で亡くなったという感動的な話を語りました)。他の人々は東へ、ウィニペグ、トロント、モントリオール、ハミルトン、またはもっと田舎の地域へ向かいました。日本へ行った人々もいましたが、その多くはその後数年の間にゆっくりとカナダに戻っていきました。
カナダ全土に散らばった人々の多くが、すでに親戚がいるという理由で移住を選んだという話に私は衝撃を受けた。到着すると、彼らは農業労働者、ガソリンスタンドの係員、家事手伝いなど、見つけられる仕事は何でも引き受け、低賃金で長時間働いた。
住宅不足は驚くべきものでした。ある家族は3寝室のバンガロー内のスペースを借りていましたが、所有者が1つの寝室に住み、所有者の子供たちが別の寝室に住み、別の家族が3つ目の寝室に住み、話し手と父親がリビングルームに住み、さらに別の家族が地下室の階下に住んでいました。
ある二世はトロントに引っ越した時のことを話してくれた。やがて日本食が恋しくなり、友人と一緒に西トロントで日系人の家族を見つけた。その家族は手頃な料金で自分たちを受け入れてくれた。彼と友人の部屋代と食事代が週 13 ドルだった。問題は部屋にダブルベッドが 1 つしかなかったことだ (この少しきわどい話にリスナーの笑いが起こったが、実は昔はストレートの男性同士がルームメイトやベッドメイトになることは珍しくなかった。最近のスティーブン スピルバーグの映画「リンカーン」では、大統領の秘書 2 人、ヘイとニコライがホワイト ハウスでベッドを共にしている。)
驚いたことに、ファシリテーターから直接質問されても、語り手のほとんどは自分たちに対する直接的な偏見を思い出せなかった。ただし、1943年にモントリオールに移住したある二世は、日本に敵対的なオーナーの中華料理店で日系カナダ人の一行がサービスを拒否された話をしてくれた。
しかし、屈辱はさまざまな形で存在した。二世の退役軍人であるフランク・モリツグは、1946年にカナダ軍から除隊し、家族のもとに戻ったときのことを語った。その後すぐに、カナダ連邦警察の職員が彼を訪ね、古い「外国人身分証明書」を渡し、写真を更新するよう命じた。日本から祖国を守るために戦った後でさえ、フランクは公式には敵国人のように扱われたのだ。
別の二世は、カナダ軍の迎撃機アブロ アローを製造したアヴェリル エアロスペース社でエンジニアとして働いていたときのことを話してくれた。1958 年にディーフェンベーカー政権がこのプロジェクトを中止したとき、彼は他のエンジニアとともに解雇された。シアトルで 747 の開発に携わったり、フロリダの NASA で働いたりして米国でもっといい仕事に就くことができた同僚たちと違い、彼は「日本人」移民枠が少なかったため米国への入国が制限され、一時ビザを取得することさえ困難だった。
別の二世は、1940年代後半にブリティッシュコロンビア大学に奨学金を得て入学したが、入学担当官が彼が日本人であり西海岸から締め出されていることを知ると、免除や他の手配をする手助けをするどころか、奨学金を取り消したと私に話してくれた。
語り手たちはまた、内面化した恥を勇敢に明らかにした。ある語り手は、戦時中に定住したアルバータ州レスブリッジで日本人以外の少女たちに歓迎されたが、友人たちのように金髪で長髪だったらよかったのに、と痛烈に語った。

閉会式では、参加者、ボランティア、企画委員会メンバー全員を対象に、公開パネルの質疑応答でストーリーテラーのアーノルド・アライ博士が感想を述べました。アライ博士は、年長者が失われるにつれて徐々に失われつつある過去を記録する会議やアーカイブの取り組みの重要性、そして同世代の人々が自分たちの体験について声を上げることがいかに重要であるかについて、熱のこもったスピーチをしました。(日系カナダ文化センター提供)
© 2013 Greg Robinson