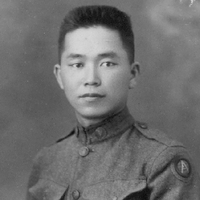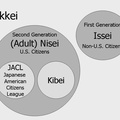パート9を読む>>
価値メッセージと非公式教育の力
以上のことから、青年期から成人期まで価値観が継続していることが分かります。栗原の場合、学生時代や青年期に培われた特定の価値観を受け入れており、その価値観は成人期後半に劇的に発揮されました。第二次世界大戦中の反体制派としての彼の行動は、模範的な学生や青年からマンザナーでの「トラブルメーカー」へと、ある意味では急激な変化と見なすことができます。しかし、表面下には、驚くほど強靭であることが証明された価値観と信念の継続がありました。
前述のことは、思想や価値観の力、そしてその思想や価値観に基づいて行動する人々の現実生活への影響も示している。栗原の場合、彼は公民権と民主主義の概念を非常に熱心に吸収していた。このため、彼は罪のない男性、女性、子供たちの投獄を暴挙であり、米国憲法の重要な保障を侵害するものと見なした。彼とマンザナーでの抗議活動仲間は、投獄は戦時中であっても異議を唱えなければならない犯罪であり、我慢すべき行為ではないことに同意した。
米国政府が理想を果たせなかったことで、栗原は幻滅し過激化した。彼は、かつて自分を拒絶した祖国を拒絶することで応じた。信頼を裏切った国にこれ以上留まることはできないと感じ、彼は米国市民権を放棄した。彼の放棄は、米国社会への完全な統合を目指す彼の目的ある運動の終わりを意味した。戦争が終わって2か月後、彼は戦後初の船に乗り、日本へ向かった。日本は彼がそれまで一度も訪れたことのない国であり、彼はその後一生日本に留まり、米国に戻ることはなかった。
マンザナーにいた栗原氏と日系人の仲間たちは、自分たちが監禁されていることの意味に苦悩した。彼らは、米国政府が政府機関を通じて、祖先に基づいて特定の集団を即座に選別し、彼らの自由と公民権を否定し、正当な手続きなしに彼らを社会の残りの人々から隔離することができるという考えに苦悩した。
この研究は、組織が伝える価値メッセージの力を思い出させ、私に次のような疑問を投げかけています。
· 私たちの組織は、意図せず無意識のうちにどのような価値観を伝えているのでしょうか?
· 彼らが発信する価値メッセージの意味と予期せぬ結果は何でしょうか?
· 社会がその制度が支持する価値観を守れなくなったら何が起こるでしょうか?
これらの疑問は、非公式教育の領域を調査することの重要性を指摘しています。
2 つの文章 (1 つはリチャード・ストーのエッセイから、もう 1 つはドナルド・ウォーレンのエッセイから) は、この研究で私が採用したアプローチを明確に示しています。1961 年、ストーは、学校教育を超えて教育のプロセスに目を向けるというベイリン=クレミンの呼びかけをさらに明確にしました。ストーは、教育が行われた事例を特定するための帰納的アプローチを提案しました。彼は、教育史家が「人間の経験を調べて、教育的であると合理的に説明できる要素を発見する」ことを提案しました。彼らは「[彼らの] 探求が終わるまで完全には特定できない何かを追求する」ことになります。ウォーレンはこれらのアイデアを取り上げました。「歴史教育の素晴らしい世界」で、彼は次のように書いています。「これは、「経験の特定の性質」を探し、「学習の場所を明らかにするように見える現象に警戒し」、「埋もれた結果でさえも探り」、「教育として正当に分類されるプロセスのさまざまな事例を明らかにする」ことを意味します。 1他の教育史研究と同様に、本研究では帰納的アプローチを用いて、正規教育と非正規教育の影響を調査します。さらにこのアプローチを使用して、非正規教育の否定できない力を明らかにします。
(終わり)
ノート:
1. リチャード・ストー、「歴史教育:いくつかの印象」、ハーバード教育評論 31:2 (1961 年春)、1、強調は筆者。ドナルド・ウォーレン、「歴史教育の素晴らしい世界」、アメリカ教育史ジャーナル 32:1 (2005 年春)、109。バーナード・ベイリン、「アメリカ社会の形成における教育」(ニューヨーク: ヴィンテージ・ブックス、1960 年)。ローレンス・A・クレミン、「エルウッド・パターソン・カバリーの素晴らしい世界」(ニューヨーク: ティーチャーズ・カレッジ・プレス、1965 年)。教育史における帰納的アプローチに関する完全な議論は、ドナルド・ウォーレンの「未来形における教育の歴史」(近日刊行予定) で行われる。ベイリンの『アメリカ社会の形成における教育』に対する洞察に満ちた批評については、ミルトン・ゲイザー著『アメリカ教育史再考』(ニューヨーク:ティーチャーズ・カレッジ・プレス、2003 年)の特に 91-104、138-164 ページを参照してください。ストーは 2 つの歴史家作業グループに参加しており、その努力が最終的にベイリンの講演のきっかけとなった会議につながりました。この講演は後に『アメリカ社会の形成における教育』として出版されました。ゲイザー著『アメリカ教育史再考』158 ページを参照してください。
* このエッセイは、2009 年 10 月にフィラデルフィアで開催された年次総会で行われた教育史学会会長演説であり、教育史季刊誌第 50 巻第 1 号 (2010 年 1 月) に掲載されました。
** 最終版はwww.blackwell-synergy.comでご覧いただけます。
© 2010 The History of Education Society