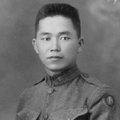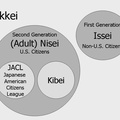>> パート2を読む
サンフランシスコの小さな日本人カトリック教徒のコミュニティは、栗原が新しい環境での生活に適応するのを助け、サンタクララとセントイグナティウスという2つのカトリック高等教育機関を紹介してくれた。栗原はまず、西側諸国におけるイエズス会の最高峰の教育機関であるサンタクララ大学を訪れた。そこで受けた対応に満足できなかった栗原は、セントイグナティウスで教育を受けることにした。高校の卒業証書がなかったため、彼はセントイグナティウス大学付属の高等部に入学した。1
セント・イグナティウスは、カトリック教徒になった数少ない日系アメリカ人のほとんどが入学したカトリック学校とは大きく異なっていた。たとえば、ロサンゼルスのザビエル・ミッションは、1921 年に日系アメリカ人の若者のための学校を開校した。メリノール修道女会が率いるこの学校は、生徒たちにバイリンガルかつバイカルチュラルな人間になってもらうことを目的として、日本語と英語の両方で教えた。同様に、ポートランドの日系アメリカ人のための別の学校であるセント・ポール・ミキ・スクールも、生徒たちに日本語と英語の両方で教えた。この点で、これらの学校は、19 世紀から 20 世紀初頭にかけて何百万人ものヨーロッパ移民の子供たちを教育した民族教区学校と目的が似ていた。2
対照的に、栗原は、徹底して西洋中心の聖イグナティウス学校に通っていた。彼はその学校で唯一の日系人で、その学校では「古代[西洋]古典が第一に扱われた」。同時に、19世紀後半に始まり、米国が第一次世界大戦に参戦する前の数年間に熱狂的ピークに達した、移民とその子供たちを「アメリカ化」しようとする全国的な動きと、カトリック学校にアメリカらしさを示すよう求める挑戦に応えて、聖イグナティウスは、いわゆるアメリカの価値観を生徒に植え付ける学校の努力を反映したカリキュラムを提供した。3
大学進学準備高校として、聖イグナティウス高校は 4 年間のコースを提供していました。1 年目と 2 年目の両方で、栗原は宗教、ラテン語、歴史、朗読法、英語修辞学、代数、初等科学の授業を受けました。さらに 2 年目には、デッサンか現代語のいずれかを選択することができました。4 聖イグナティウス高校に通い始めたとき、栗原はすでに 20 歳の若者でしたが、非常に意欲的な生徒でした。
1 年生と 2 年生の宗教の授業では、トーマス・キンキードの『ボルチモア教理問答の解説』を読んだ。1884 年にボルチモア第三総会で委託されたボルチモア教理問答は、カトリックの若者の教育に統一性をもたらした。キンキードの『解説』の最初の部分には 10 の祈りが示され、それぞれの祈りの詳細な説明が続く。本の残りの部分は、キリスト教の教えを質疑応答形式で論じ、詳細な説明が続く 37 のレッスンから構成されている。カトリックに改宗した栗原は、宗教的信仰に真剣だった。彼はこの本を熱心に学び、セント・イグナティウスでの 1 年生と 2 年生の宗教の授業では平均 96 パーセントと 97 パーセントの成績を収めた。5
宗教的学習が「学校全体の雰囲気に浸透する」という考えのもと、聖イグナチオ学校の教育者は「キリスト教徒としての男らしさの育成」を強調した。これは、学校が生徒の人格の育成を重視していたことを意味する。学校が期待していたのは「時間厳守、厳格な服従、勤勉な学習、非の打ち所のない行動」であり、生徒は毎月「行動」の成績を与えられる。模範的な行動を示すことに真剣だった栗原は、2年間の在学中、毎月100点満点の成績を取ることに成功し、クラスメートの中で唯一それを達成した。聖イグナチオ学校を卒業してからも、彼は正義の考えを持ち続けた。6
人格形成に重点を置いたことに加え、アメリカ主義の考えと合致するセントイグナティウス校の西洋中心のカリキュラムは、栗原に強い影響を与えた。大学進学志望者と将来のリーダーのために設計され、ヨーロッパのイエズス会の教育モデルに由来するセントイグナティウス校の生徒の学習課程には、ラテン語とギリシャ語の徹底した基礎教育が含まれていた。他のイエズス会学校と同様、セントイグナティウス校のカリキュラムは、「スタジオルム」として知られるイエズス会の教育規範を体現していた。16世紀にヨーロッパで開発されたこの文書は、健全で自由主義的かつ人間味あふれる教育の基礎として、ラテン語とギリシャ語、およびキケロ、オウィディウス、ウェルギリウス、ホメロスなどの主要な弁論家、政治家、作家の作品の研究を定めていた。「ルネッサンス時代の理想を体現したイエズス会の学校は」と歴史家ジェラルド・マクケビットは述べている。 「[西洋の]古典文学を好んだのは、それが倫理教育と効果的な修辞法やリーダーシップスキルの育成を中心とした教育に理想的な手段だと思われたからだ」。米国のイエズス会教育者の間では、より現代的なカリキュラムを提供する努力がなされたが、それでも栗原が聖イグナチオ学校に通っていた間、ヨーロッパの影響は強く残っていた。さらに、イエズス会教育で強調された倫理、修辞法、リーダーシップというテーマは、マンザナーでの彼の行動に反映されることになる。7
ノート:
1. McKevitt, Brokers of Culture 、276 ページ;Gerald McKevitt, The University of Santa Clara: A History, 1851-1977 (Stanford: Stanford University Press, 1979)、170-71 ページ;William J. McGucken, The Jesuits and Education: The Society's Teaching Principles and Practice, Especially in Secondary Education in the United States (New York: The Bruce Publishing Co., 1932)、276 ページ。Joe から Harry Y. Ueno への 1965 年 4 月 7 日付の手紙、著者所蔵。1855 年に設立されたこの学校は、当初はヨーロッパのモデルに倣い、6 歳から 18 歳の男子が入学できるセント イグナティウス カレッジと呼ばれていました。19 世紀後半に高校および高校卒業後のクラスが開講されました。20 世紀初頭に初等クラスは廃止されました。 1918年に7年生と8年生が終了しました。1909年に高等学校部門はセントイグナティウス高等学校と呼ばれ、1912年に高等学校後の部門はセントイグナティウス大学(後のサンフランシスコ大学)と名付けられました。ジョン・バーナード・マクグロイン著『ゴールデンゲートのイエズス会:サンフランシスコのイエズス会、1849-1969 』(サンフランシスコ:サンフランシスコ大学、1972年)、134-37ページ、ポール・トータ著「スピリトゥス・マギス:セントイグナティウス・カレッジ準備校の150年、第1部」ジェネシスIV、同窓会誌、歴史補足42:1(2005年春):3、7、30、42ページ、www.siprep.org/genesisIV/index.cfm33-36(2005年5月10日アクセス)を参照。
2. ヤマザキ「聖フランシスコ・ザビエル学校」54-73ページ、リリアン・A・ペレイラ「カトリック教会とポートランドの日本人:時期尚早な聖ポール・ミキ学校プロジェクト」オレゴン歴史季刊誌94(1993-94年冬):399-434ページ。メリノール聖フランシスコ・ザビエル学校には、幼稚園、小学校、中学校の学年が含まれていた。1937年に開校した聖ポール・ミキ学校には、幼稚園から2年生が含まれていた。これらの学校は栗原が成人してから開校したため、栗原がこれらの学校について知っていたとしても、栗原がそこに通うことはできなかっただろう。しかし、私が言いたいのは、彼が通ったハワイとサンフランシスコのカトリック学校は、日系アメリカ人の生徒のためのバイリンガル・バイカルチュラル学校ではなく、西洋中心の学校だったということである。民族教区学校については、ティム・ウォルチ著『教区学校:植民地時代から現在までのアメリカのカトリック教区教育』 (ニューヨーク:クロスロード出版、1996年)3-4、76-81ページで説明されています。
3. 引用元は、セント・イグナティウス大学カタログ、 1916-17、p. 113、RG4カタログ、サンフランシスコ大学アーカイブ。アメリカ化の概念は明確に定義されたことはなかった。一般的には、アングロ・コンフォーミティ(英語への順応)を意味していたが、移民とその子供たちが英語でコミュニケーションを取り、いわゆる外国の習慣を捨て、愛国心、キリスト教(つまりプロテスタント)、勤勉、ハードワークの考えを植え付けられることも意味していた。カトリックの指導者たちは、キリスト教がプロテスタントを意味するという考えに激しく抗議したが、アメリカ化の推進力の他の側面には同意した。この時期のアメリカ化の考えについては、Tamura, Americanization, Acculturation, and Ethnic Identity 、52-55ページ、およびWalch, Parish School 、28-29ページを参照。カトリック学校への挑戦については、Walch, Parish School 、72-73ページを参照。
4. 高校の 4 年間のコースと基本教科書は、セント イグナティウス大学のカタログ、1916-1917、114-115、RG4 カタログ、サンフランシスコ大学アーカイブに記載されています。高校はセント イグナティウス大学に付属していました。
5. Thomas L. Kinkead, An Explanation of the Baltimore Catechism of Christian Doctrine (New York: Benziger Brothers, 1891); Berard L. Marthaler, “Baltimore Catechism,” The Encyclopedia of American Catholic History , ed. Michaels Glazier and Thomas J. Shelley (Collegeville, Minn.: Liturgical Press, 1997), 122-23. コースの成績については、「Scholastic Records, 6th Grade 1912-1913 to Senior High School 1925-1926」、St. Ignatius High School、RG1 Box 9、University of San Francisco Archives および「Scholastic Records, 7th Grade 1916-1917 to Senior College 1920-1921」、St. Ignatius High School、RG1 Box 9、University of San Francisco Archives を参照。
6. マクガッケン『イエズス会と教育』 150、165 ページ。学校での生徒の行動に対する期待については、『聖イグナティウス大学紀要』1916-17 年、10-11 ページ、RG 4 カタログ、サンフランシスコ大学アーカイブを参照。カトリックの社会教義には正義や人間の尊厳といった考えが含まれていたが (ダニエル A. オコナー著『カトリックの社会教義』 (ウェストミンスター、メリーランド州、ニューマン プレス、1956 年)、28、50 ページを参照)、カトリックの社会思想は本質的に伝統主義的かつ保守的であった。カトリックには急進的な流れもあるが、それが顕著になったのは栗原がカトリックの学校に通っていた時代よりずっと後になってからである。社会改革の考えからなる急進的な流れは、1920 年代から 30 年代にかけてカトリック教徒の少数派の間で生まれ、1960 年代にはヨーロッパや北米での運動やラテン アメリカでの解放神学など、非常に目立つようになった。栗原が日系アメリカ人の強制収容以前の1920年代から30年代にかけてカトリックの社会思想によって急進的になったという証拠はない。カトリックの社会思想に関する議論については、「社会思想、カトリック」、新カトリック百科事典、第2版、第13巻(デトロイトおよびワシントンDC:トムソン/ゲイルおよびカトリック大学、2003年)、255-66ページ、およびアンソニー・S・ブリュック、ヴァレリー・E・リー、ピーター・B・ホランド著『カトリック学校と公益』 (ケンブリッジ、マサチューセッツ州:ハーバード大学出版、1993年)、41-46ページを参照。
7. Allan P. Farrell, The Jesuit Code of Liberal Education: Development and Scope of the Ratio Studiorum (Milwaukee: The Bruce Publishing Co., 1938), 342-57; Philip Gleason, Contending with Modernity: Catholic Higher Education in the Twentieth Century (New York: Oxford University Press, 1995), 5-6, 51-53; “Ratio Studiorum,” The Catholic Encyclopedia , vol. 12 (New York: Robert Appleton Co., 1911), www.newadvent.org/cathen/12654a.htm, 2007年8月7日にアクセス。Farrellによれば、 The Jesuit Code 、xi、 Ratio Atque Institutio Studiorum Societatis Iesu (Ratio Studiorum) はThe Jesuit Code of Liberal Educationと翻訳できる。栗原はセント・イグナティウス校での2年間で、毎年6コマのラテン語を履修した。アメリカ主義者と伝統主義者の対立に関する議論については、マケビット著『文化の仲介者』264-67, 276-78ページを参照。引用はマケビット著『文化の仲介者』211ページから。1920年代になっても、カトリック系高校の教育者は西洋古典の研究を続けることを選択しており、それが「生徒の推論能力」を発達させ、「学校教育の中心的な道徳的目的」を促進すると信じていた。ブリュック、リー、ホランド著『カトリック学校と公益』 31ページを参照。またメアリー・ジャネット・ミラー著『アメリカのカトリック中等学校における一般教育』 (ワシントンDC:カトリック大学アメリカ出版)も参照。
* このエッセイは、2009 年 10 月にフィラデルフィアで開催された年次総会で行われた教育史学会会長演説であり、教育史季刊誌第 50 巻第 1 号 (2010 年 1 月) に掲載されました。
** 最終版はwww.blackwell-synergy.comでご覧いただけます。
© 2010 The History of Education Society