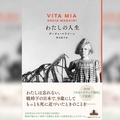アメリカへの留学体験(1970年代)からアイデンティティの問題を意識し、以後、マイノリティーや異文化コミュニケーション考察の旅を続け、近年は、自らのルーツである伊豆の知半庵を拠点に、アートプロジェクトを仕掛けるあわやのぶこさんに、その活動内容や意図などをたずねた。
* * * * *
過去と未来、日本と外国がクロス
川井:生まれ故郷の伊豆の「知半庵」で、あわやさんがおこなっている「知半アートプロジェクト」というイベントには、さまざまな分野の海外のアーティストがこれまで参加されてきたと聞いてます。これまでのあわやさんの研究や活動とこのプロジェクトとの関係、そして、このプロジェクトの狙いを教えてください。
あわや:知半アートプロジェクトは、いってみれば、異文化コミュニケーションの実践版みたいなものですね。私の生家「旧菅沼家住宅:知半庵」をフル活用し、展示やコンサートなど、とにかく質の良いオリジナル企画をと、「チーム知半」と呼ばれるスタッフたちと共に開催しています。知半アートを見たことない人には「あ〜、古民家でアートね」とまとめられたリするのですが、そういうことではないのです。
江戸時代の家だから尺八コンサートをやるとか、古民家にただ現代アートを持ち込む、という発想は皆無で、伊豆という場とのコラボで毎回のアート企画を練り上げているサイトスペシフィック企画(site specific art)なので、実施までに3年はかかります。毎年、3年先のことばかりを考えています。当初から「文化交差」というテーマで、過去と未来、日本と外国、伊豆と江戸などさまざまなものがクロスするような企画を立てています。
川井:具体的に、これまでどのようなアーティストが参加して、どのようなイベントを行ってきたのでしょうか。
あわや:いやぁ、これ難問! 13回のプロジェクトから何をどう話したらいいものやら・・・。代表的な回をいくつか説明しますね。
日米共同コンテンポラリーダンス公演「伊豆の家」(Izu House)はごく初期に開催したのですが、これはアジア系アメリカ人研究会でロコ・カワイ(Roko Kawai)に講演を依頼したところから発生しました。彼女は幼い時に、頭脳流出で渡米した心臓外科医の父親と共にアメリカ暮らしになった自称1.5世。踊り手として文化の狭間を表現していました。彼女が知半庵を訪れた時、何かの創作スイッチが入ったのでしょう。
いつも一緒に踊っているフィラデルフィアの舞踊団の代表リア・スタインに即連絡し、数年後、伊豆の知半庵という場に即したダンスを作り上げ、アメリカの助成金で再来日、彼らのほかに日本からはボイスきむらみか、踊り手の新井英夫、アメリカからはもう一人パーカショニストTOSHIが参加しました。家の内外を巡って踊る作品は、障子や襖が自在に開閉する幕となり、観客は小さいグループに分かれて踊り手を追いかける形で進行するという楽しい公演となりました。『International Herald Tribune』紙にも取り上げられ、その翌年、国際交流基金を得て、同じメンバーでアメリカ公演を果たしました。
「沈黙の鼓動」(Silent Pulse)は、言葉をテーマに制作しているフランス人作家セシル・アンドリュ(Cecile Andrieu)の展示。彼女はシュレッダーにかけた辞書や新聞などを材料として作品を作っていました。知半庵に何度も来てもらい、江戸時代の家の機能、ライフスタイルの話などもしました。というのも、私はギリギリ最後の“お産婆世代”で、知半庵の奥座敷の障子と襖を閉めきって母とお産婆さんが入って私が生まれたのですね。
奥座敷は最も重要な客間ですが、出産にも使われました。出産を待つ間、父や祖父は内心ドキドキしてるのに、広間でゆっくりと囲碁をしていて、「おぎゃあ」と聞こえたら、やっと囲碁の手を止めるという具合。いずれにせよ、昔の日本の家は、出産も祝言、葬式も家で行っていた。人の移動、流動性もあまりなく、人は家で生れて、家で死に、死んだら裏の先祖代々の墓に入るという具合でした。現代では出産も結婚式もお葬式も外注産業ですよね。
というわけで、セシルは知半庵で作品を作るなら、人の誕生、活動、死というサイクルを作品にしたいと言い、部屋ごとにグラデーションをつけた紙で、一連の人生の出来事を表す計画でした。私は家の材料を使ったらどうか、と提案をして、結局、誕生の部屋には庵にある赤ちゃんのおべべ、活動を表す部屋には定期的に開かれていた句会の短冊、死の部屋は、曾祖父の遺言証書、とそれぞれにちなんだものをスキャンした用紙を6800枚ずつプリントして、全部をシュレッダーにかけてアート材料として使いました。
この時、フランス大使館に後援申請をしたのですが、大使館が興味を持ってくれて、後援だけでなく「日仏文化協力90周年」の記念行事に指定してくれました。
「墨のこえ」(Voice of Sumi)という展示は墨がテーマで、静岡を代表するアーティスト青木一香に立体作品を依頼し、書家で現代美術家のフランス人ドミニク・エザールは書と野外で樹に和紙を張るインスタレーション、そして、なんと何十年越しでアラン作品を日本初で展示しました。私は墨は繊維の重なりの中を分け入っていくメディアだという概念で、絵も裏と表では浸透度が異なるので、アラン作品は部屋の真ん中につるし、裏からも表からも見られるようにしました。
知半アートでは、現代邦楽のコンサートを開くことも多いのですが、「エア・コンサート」と名付けたシリーズの初回で、ハンガリーのペーター・エトヴォス作曲「HARAKIRI」を彼に直接に許可を得て演奏しました。この曲はヨーロッパの音楽祭ではよく演奏される現代音楽なのですが、日本でほとんど演奏されない。曲が知られていない上に、語り以外に演奏者は3人、吹奏楽器二人と木こり役が必要なのです。
この木こりが薪を割る音が打楽器の役目をするというシロモノで、ヨーロッパでも舞台の上に木こりを上げるのは困難なので、よく日本の拍子木を使っています。でも、知半庵は家ですから、庭に面した部屋を会場にして、外では木こりが竹を百本以上割り、音を出し、手前の部屋では尺八をクリストファー遙盟が、木管フルートを木埜下大祐が吹きました。リアルな迫力です。
クリストファーはテキサス育ちのアメリカ人ですが、日本で尺八と出会い、藝大大学院で人間国宝の山口五郎に習い、琴古流の御名前をもらった人。木埜下はドイツの音楽大学で修業し、中国でも活躍した若手です。語りは出光音楽賞など数々の賞に輝く現代三味線の旗手、本條秀慈郎でした。
2023年の「日本の庭で」(In the Gardens of Japan)は、ベルリン在住のアメリカ人ケニー・フリーズ(Kenny Fries)が書いた日本庭園の8編の英詩に、現代邦楽で知られる作曲家、高橋久美子が曲をつけ、きむらみかが歌い、箏、尺八、三味線、能管など和楽器演奏のコンサートで、知半アートが初演披露でした。カナダ政府アートカウンシル助成を受け、無料公開にしました。ケニーは障がい者で、ベルリンから、車椅子で伊豆の会場に現れ、詩の朗読もしてくれました。同性愛者でありユダヤ系あることを公にしている素晴らしい小説家で、彼の友人で聴覚障害を持つ映像作家アリソン・オダニエル(Alison O'Daniel)も来日して撮り下ろした無声映像を提供してくれて、コンサートと並行して見せるという贅沢なコンサートでした。
世界の中の日本の音楽
あわや:現代邦楽というと、妙に難しく聞こえるジャンルかもしれませんが、知識ではなく、音そのものが、こちらに響くか届くかどうか、の話です。それに、例えば、三味線は日本のものと考えている方が多いと思いますが、トルコの三弦楽器がその発生だという知見もあります。ちなみに、以前、ヨーヨー・マのインタビューをした時にチェロも中東が起源だと言っていました。
和楽器の中で、特に尺八は国際化された和楽器だと思います。前出のクリストファーは、コロラドやチェコで国際尺八フェスティバルを創設した尺八音楽家の一人です。国際化って、と疑問に思われるかもしれませんが、単に、日本出身者以外の演奏者が世界で多いというだけでなく、尺八音楽の作曲者も海外にたくさんいます。そういう作り手が多くいることは、尺八の国際化の証ですね。ほかに、落語「牡丹灯籠」に曲をつけて演奏してくれたコリーン・シュミコーは三味線音楽そのものの研究もしていて、西欧での学会発表もよくしています。日本人が思うほど、和楽器は日本のモノでもなくなっていて、世界の皆が楽しむものになっています。
そもそも、日系コミュニティーの中では多くの人が箏や太鼓を演奏し続けていますし、アメリカでも「HIROSHIMA」などいち早く新しい音楽ができて久しいですよね。
コンサートなどではないのですが、2つ、忘れられない出来事があります。ある時、クリストファーがマーク・イズ (Mark Izu、妻ブレンダ・アオキ [Brenda Aoki]と共にアジア系アメリカ文化をけん引してきた。今年初めに逝去)一家を知半庵に連れて、半日、ゆっくり過ごしたことがあります。ちょうどマークが来日する前にカルフォルニアの美術館で映画「伊豆の踊子」の上映があり、彼が音楽をつけたと言うのです。
「伊豆の踊子」は時代により色々な版がありますが、初期の無声映画のものに音楽をつけた、と言うのです。私はびっくりしました。それは1933年、五所平之助監督による主演が田中絹代のバージョンなのですが、五所さんと祖父が親しく、よく知半庵に来られていました。知半(家の登録名の由来でもある祖父の雅号)が庵で開く句会の仲間です。また、戦争中は、小津安二郎と同様、戦争を鼓舞するような映画を作る人ではない五所さんをささやかながら祖父は面倒を見ていたようです。マークも偶然ながら、この場に導かれたようでとても驚き喜んでいました。
もう一つはロン・チュウ(Ron Chew)のことです。長い間、会っていませんが、彼が2020年に出版した「My Unforgotten Seattle」になぜかシアトル滞在中の私とのやりとりの記憶が生き生きと書かれていて、感激しました。なによりもこの短い章の最後に、彼が館長を務めるウィングルーク博物館(Wing Luke Museum)と知半アートプロジェクトが出てきます。『生きた形で過去と未来をつなぐ』という精神が、遠く離れた彼と私の仕事に通底していて、パラレルなんだ、と。アジア系アメリカに触れて学んだことが私の中にしっかり入っていて今の私があるんだと思うと胸がいっぱいになりました。
今年は、伊豆にある尺八の聖地「旭滝」で尺八演奏をしようと伊豆市と話し合っています。日米の尺八演奏者がこの滝の前で、この滝から生れた江戸時代の名曲「滝落」を吹きます。また、知半庵では富士山と城山という展示が11月1日から開催予定です。「富士山」という世界に知られた日本の象徴のような山と伊豆の人の拠り所となっている低山「城山」を平行に扱った面白いアート展示を開催します。
知性で心の自由を守る
川井:今後、文化交差というテーマや多文化共生との関係では、どのようなイベントを手がけていきたいと考えていますか。
あわや:私は、何よりも、知半アートプロジェクトが伊豆発信の「文化の玉手箱」でありたいと願っています。地方文化再生、サイトスペシフィックなアートなど理屈は色々ありますが、一番の基盤に「文化の裾野を広げたい」という一心があるのです。「チーム知半」と呼ばれるさまざまな背景をもったスタッフたちと一緒に頑張っています。文化は不要不急ではなく、心の基盤になるもの、緊急の時にも自らを救ってくれるものだと思います。
川井:時代とともに、日系が意味するものも変わってきたと思いますが、あわやさんは日系が意味するもの、日系は文化面でどのような意味をもつと思いますか。その他、文化交差、異文化コミュニケーションという点でなにご意見がありましたらきかせてください。
あわや:そうですね、これだけ多様性、流動性のある世界では、マジョリティ、マイノリティの区別も単純にはできませんし、日系という概念も自らをどう認識するか、に委ねられてもいるわけですね。そもそも、日本人とか日系人とかの概念も、異文化コミュニケーション領域でも定かなものはないのです。それぞれの個人の小さな物語が、ある集団の大きな物語を形成するだけです。
基本的には、「文化」は「政治」よりも大きな概念だと私は信じています。でも、政治によって文化が規制、制限されてしまうことは、歴史の中で多々あったことで、これからも繰り返されることでしょう。日本の戦争時代、世界の局部戦争から大戦までを考えてもそうです。個々の人間の力、知性でどう心の自由を守っていくのかが、これからの課題だと思います。私も伊豆という場を大切に力を尽くしたいと思います。
|
あわやのぶこ 静岡県中伊豆(現在の伊豆の国市)の庄屋、菅沼家の「知半庵」(国の登録有形文化財)の奥座敷で生まれる。東京女子大学文理学部英米文学科卒、同大学院現代文化(コミュニケーション専攻)修了。大学時代にRI奨学生として、南メソジスト大学芸術学部に留学。帰国後、通訳を経て雑誌記者となり、1979年から86年までジャーナリスト・ビザで再渡米。シアトルの『The International Examiner』紙、国連協会のスタッフとして活動。在米中、アフリカや香港などに短期滞在した後、帰国。ジェンダーを含めた異文化領域の取材、著作、翻訳を多く手がける。2000年、神奈川の私大にできた異文化コミュニケーション学科の教員に着任。異文化コミュニケーションを20年間教える。助教授時代に、200年の歴史で、初めて空き家になりかけた知半庵をアートの場として「知半アートプロジェクト」を立ち上げ、現在に至る。静岡県文化財団より2017年度「地域文化活動奨励賞」受賞。 著書、訳書多数。英語の共著にカルフォルニア大学出版局「Re-Imaging Japanese Women」(Anne E. Imamura 編)がある。平成15年より文部科学省検定教科書「現代文」(大修館刊・高校現代国語)、平成23年より「国語」(学校図書・中学校国語)などにエッセイが収録されている。 |
© 2025 Ryusuke Kawai