en ja es pt

community

スポーツは、音楽のように言葉や文化の壁を超えるものです。競技者として、またはファンとして、誰もがスポーツを楽しむことができます。団体競技であれ、ジョギングや釣りといった個人活動であれ、スポーツは私たちを日常生活から解放してくれます。チームスポーツは、現代の他のどの活動より、喜びの中(または失意のうちに)コミュニティをひとつにしてくれます。
ニッケイ物語第9弾として、ディスカバー・ニッケイでは、2020年6月から10月までスポーツにまつわるストーリーを募集し、同年11月30日をもってお気に入り作品の投票を締め切りました。全31作品(日本語:6、英語:19、スペイン語:7、ポルトガル語:1)が寄せられ、数作品は多言語による投稿でした。
本シリーズへ投稿してくださった皆さん、どうもありがとうございました!
このシリーズでは、編集委員とニマ会の方々に、それぞれお気に入り作品の選考と投票をお願いしました。下記がお気に入りに選ばれた作品です。
日本語:

田中裕介さんのコメント
嶋洋文氏の「バンクーバー朝日投手、土居健一と家族の物語」を読みながら、過去30年にわたる「朝日軍」とのお付き合いの日々が走馬灯のように巡ってきました。この家族史研究は貴重なものです。1914 年から1941年までの「朝日軍」の歴史が、社会に投げかけた投網によってたぐり寄せられた成果です。チーム誕生から百余年を経ても、なお裾野が広がり続けるとは誰も予想しなかったでしょう。
編集委員としては、客観的に作品を読まなければならないのでしょうが、日系ボイス編集者として1989年に雇われてから22年間、フリーになってからの9年間、振り返ると、「朝日軍」の名が頭をよぎらなかった日はなかったのではないかとさえ思います。日系史のどこを輪切りにしても、断面のどこかに朝日野球と繋がっている事例があるからです。
嶋洋文氏の記事に即して言うと、「健一は12歳の時にすでに朝早くに起きてロイストン近くの岸本牧場で牛の世話をしてから学校へ通った」という文章がありますが、カンバーランドの歴史に詳しいトクギ・スヤマさんによると、この牧場主の岸本さんは、強制移動後にオンタリオ州に再定住し、そこでも岸本牧場を営んでいたのです。起業能力を持っている人は財産を失っても、すぐに立ち直る力があったということでもあります。
他の作品にアスリートとして卓越した能力を持つ方の立派な自伝もありましたが、既に他の機関紙に発表された作品でもあり、今回は僕のキャリアの特殊性に鑑みて、嶋洋文氏のエッセイを特に選ばせていただきました。
英語:

なぜコーチをするのか:ジュニアスポーツコーチとしてのボブ・コダマの遺産
マイケル・コダマ
ブライアン・ニイヤさんのコメント
マイケル・コダマ氏による、父親のボブ・セイコウ・コダマ氏と2人の人生におけるスポーツやコーチとしての役割をたたえる感動的なこの作品は、一般的な、そして日系社会におけるスポーツの重要性を豊かに捉えています。ボブは子供時代にミニドカ強制収容所で野球を学びました。父と息子の関係の中心には、野球などのスポーツのコーチングがありました。そしてその関係性は、次の世代にも受け継がれていきます。コダマ氏の物語は、彼の父を含む人々の、コーチを務めることを選ぶ理由について触れながら、スポーツやコーチング、そして何世代もの若者の人生において、コーチが果たしてきた役割の最良の部分に光を当てています。コダマ氏の物語が、人々がコーチという崇高な使命を引き受けるきっかけとなることを願います。
スペイン語:

60周年を迎えて:あなた達の心の近くに
ルイス・イグチ・イグチ
マリオ・キヨハラ・ラモスさんのコメント
次世代の日系人(そしてすべての読者)に向けて書かれたこの作品には、AELU(Asociación Estadio La Unión: ラ・ウニオン総合施設・通称アエル)がどのように誕生したか、それは多くの人の心温まる気持ち、事業に関わった人たちの連体感、そしてはじめはとても質素なスタートであったこと、さらには、この60年間に及ぶ成長と施設の近代化が良く描かれている。AELUは、特にこの30年は、昨年(2019年)日本人移住120年を迎えたペルーの日系社会とともに歩んできたともいえる。また、AELUは地元ペルー社会の中でも重要な団体としてのプレゼンスを誇り、成長してきたが、社会と同じ目的のために力を合わせてくれた多くの無名の人の姿がある。著者は、間接的とはいえ我々の子供たちににこのAELU創設の理念や価値観を伝承していくよう求め、AELUの創設のために多くの人が資金を提供し、石を除き、レンガを積んだことが人々の記憶に残るよう願っている。AELUは、我々日系社会にとって大きな誇りであり、充実感を与えてくれる立派な施設である。
ポルトガル語:

アルド・ワタオ・シグチさんのコメント
エドナ・ヒロミ・オギハラ・カルドゾさんは日本で始まった体操、ラジオ体操について詳細に書いています。日本移民70周年記念祭(1978年)の折にブラジルに導入されたこのラジオ体操は、時とともに、日系人だけでなく非日系人をも含め数え切れないほど多くの人々に親しまれています。エドナさんの作品を通して、私達は、ラジオ体操が行われる体育館に導かれ、皆さんと一緒に体操を楽しみ、会話に参加し、参加者の人柄も知りうることもできます。
また、ラジオ体操の効果についてもよく描かれています。特に、ラジオ体操教室は皆さんの社交の場としての役割を果たしているようですが、パンデミックの影響で今は中止され、皆さんは残念に思っています。それを紛らわすために電話やインターネットで、幸せな時間を少しでも取り戻すようにしておられる様です。
We have closed submissions for this series, but you can still share your story on Discover Nikkei. Please check our Journal submission guidelines to share your story!
編集委員の皆さんのご協力に、心より感謝申し上げます。
 田中裕介:札幌出身。早稲田大学第一文学社会学科卒業。1986年カナダ移住。フリーランス・ライター。グレーター・バンクーバー日系カナダ市民協会ブルテン誌、月刊ふれーざー誌に2012年以来コラム執筆中。元日系ボイス紙日本語編集者(1989-2012)。1994年以来トロントで「語りの会」主宰。立命館大学、フェリス女学院大学はじめ日本の諸大学で日系カナダ史の特別講師。1993年、マリカ・オマツ著「ほろ苦い勝利」(現代書館刊)により第4回カナダ首相翻訳文学賞受賞。
田中裕介:札幌出身。早稲田大学第一文学社会学科卒業。1986年カナダ移住。フリーランス・ライター。グレーター・バンクーバー日系カナダ市民協会ブルテン誌、月刊ふれーざー誌に2012年以来コラム執筆中。元日系ボイス紙日本語編集者(1989-2012)。1994年以来トロントで「語りの会」主宰。立命館大学、フェリス女学院大学はじめ日本の諸大学で日系カナダ史の特別講師。1993年、マリカ・オマツ著「ほろ苦い勝利」(現代書館刊)により第4回カナダ首相翻訳文学賞受賞。 ブライアン・ニイヤ:日系アメリカ人史を専門とする公共史学者。現在Densho(第二次世界大戦中の日系アメリカ人強制収容の体験を継承する活動を行う団体)のコンテンツディレクターとオンライン「デンショウ・エンサイクロペディア」の編集者を務めている。カリフォルニア大学ロサンゼルス校アジア系アメリカ人研究センターや全米日系人博物館をはじめ、ハワイ日本文化センターで職務経験を持つ。ハワイ日本文化センターではコレクション管理や展覧会キュレーション、イベントの企画の他、映像・書籍・ウェブサイト制作に関わった。彼の論文等は、学術誌や一般誌、オンライン誌などに幅広く掲載されており、第二次世界大戦中の日系アメリカ人の強制退去や収容についての講演やインタビューにも頻繁に応じている。 .
ブライアン・ニイヤ:日系アメリカ人史を専門とする公共史学者。現在Densho(第二次世界大戦中の日系アメリカ人強制収容の体験を継承する活動を行う団体)のコンテンツディレクターとオンライン「デンショウ・エンサイクロペディア」の編集者を務めている。カリフォルニア大学ロサンゼルス校アジア系アメリカ人研究センターや全米日系人博物館をはじめ、ハワイ日本文化センターで職務経験を持つ。ハワイ日本文化センターではコレクション管理や展覧会キュレーション、イベントの企画の他、映像・書籍・ウェブサイト制作に関わった。彼の論文等は、学術誌や一般誌、オンライン誌などに幅広く掲載されており、第二次世界大戦中の日系アメリカ人の強制退去や収容についての講演やインタビューにも頻繁に応じている。 . マリオ・キヨハラ・ラモス:リマ在住の日系三世。ペルー日系人協会(APJ)のコミュニケーション&マーケティング担当理事を務める。22年間東京で生活する中で、日本社会が他国から学び改善できる点を認識すると共に、この世界をより良い場所にするためにどのように貢献できるか、多くを学んだと感じている。
マリオ・キヨハラ・ラモス:リマ在住の日系三世。ペルー日系人協会(APJ)のコミュニケーション&マーケティング担当理事を務める。22年間東京で生活する中で、日本社会が他国から学び改善できる点を認識すると共に、この世界をより良い場所にするためにどのように貢献できるか、多くを学んだと感じている。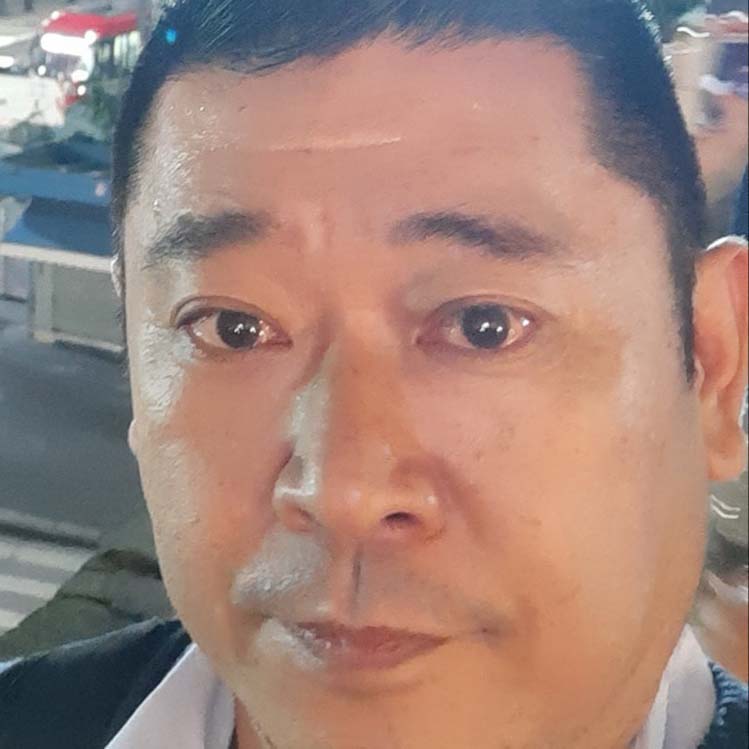 アルド・ワタオ・シグチ:1967年サンパウロ州ロザナ生まれ。約30年にわたる記者としてのキャリアを持ち、ブラジルの日系コミュニティの主要3紙「パウリスタ新聞」、「ニッパク新聞」、「サンパウロ新聞」で、ポルトガル語の編集者を務めた。大学一年生の時にパウリスタ新聞グループで働き始め、すでに廃刊となった「パウリスタ新聞」の週刊紙「Japão Agora」に2年、日刊紙「パウリスタ新聞」で6年ほど編集にかかわった。その後、「ニッパク新聞」から「サンパウロ新聞」へと移籍し、1998年からは「ニッパク新聞」と「パウリスタ新聞」が統合した新しい新聞「Jornal Nikkey」に勤務し現在に至る。
アルド・ワタオ・シグチ:1967年サンパウロ州ロザナ生まれ。約30年にわたる記者としてのキャリアを持ち、ブラジルの日系コミュニティの主要3紙「パウリスタ新聞」、「ニッパク新聞」、「サンパウロ新聞」で、ポルトガル語の編集者を務めた。大学一年生の時にパウリスタ新聞グループで働き始め、すでに廃刊となった「パウリスタ新聞」の週刊紙「Japão Agora」に2年、日刊紙「パウリスタ新聞」で6年ほど編集にかかわった。その後、「ニッパク新聞」から「サンパウロ新聞」へと移籍し、1998年からは「ニッパク新聞」と「パウリスタ新聞」が統合した新しい新聞「Jornal Nikkey」に勤務し現在に至る。
今回ロゴをデザインしてくれたジェイ・ホリノウチさん、提出原稿の校正、編集、掲載、当企画の宣伝活動などをサポートしてくれている素晴らしいボランティアの方々やご尽力いただいた皆さん、本当にどうもありがとうございます!
免責条項:提出された作品(画像なども含む)に関しては、DiscoverNikkei.org および本企画と連携する他の出版物(電子または印刷)に掲載・出版する権利を、ディスカバー・ニッケイおよび全米日系人博物館に許諾することになります。これにはディスカバー・ニッケイによる翻訳文書も含まれます。ただし、著作権がディスカバーニッケイへ譲渡することはありません。詳しくは、ディスカバーニッケイの利用規約 または プライバシー・ポリシーをご参照ください。




