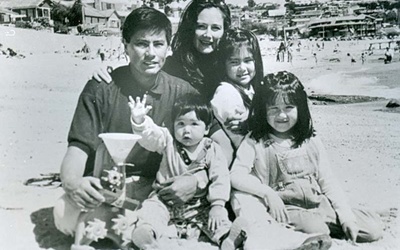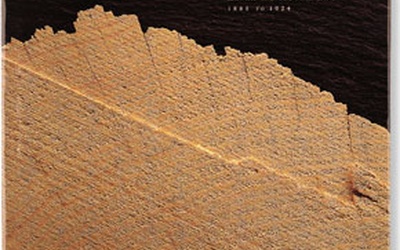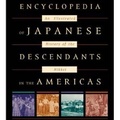アケミ・キクムラ・ヤノ
(Akemi Kikumura Yano)
アケミ・キクムラ・ヤノは、カリフォルニア大学ロサンゼルス校アジア系アメリカ人研究センターの客員研究員です。カリフォルニア大学ロサンゼルス校で人類学の博士号を取得しており、受賞歴のある作家、キュレーター、劇作家でもあります。著書『過酷な冬を乗り越えて:移民女性の人生』で最もよく知られています。
2012年2月更新
この執筆者によるストーリー
日系アメリカ移民略史
2014年5月2日 • アケミ・キクムラ・ヤノ
1885年から1924年にかけて、約20万人の日本人がハワイに、また18万人が合衆国本土に移民しました。そのほとんどは干ばつ、飢饉、人口過多に苦しむ日本南部の県の出身者でした。 ハワイでは初期の一世達はサトウキビ農場で働きました。本土に着いた移民達はアラスカの鮭缶詰工場、ユタの鉱山キャンプ、オレゴンの製材所や、カリフォルニアの農園へ送られました。 人種差別 日系人の生活にはいつも人種主義の影がつきまとい、これが結果として1907年から1908年の日米紳士協定の形と…
日系ペルー移民略史
2014年4月25日 • アケミ・キクムラ・ヤノ
ペルーの日系人の物語は1899年に始まります。日本からやって来た最初の移民の集団は中央沿岸部の渓谷地帯の砂糖や綿農園で働きました。その多くはやがてリマやカリャオの都市部へ移動し、散髪屋やレストランなど、小さな商売を営むようになります。それは1920年代の前半のことでした。 農村から都市への移住 1924年から1936年にかけて、日本人移民の第2の波が訪れますが、この時には農場よりも都市部へ向かい、移民達は商売や、近郊農業での可能性を追求しました。1920年代に向けて、リ…
日系パラグアイ移民略史
2014年4月18日 • アケミ・キクムラ・ヤノ
公式のパラグアイへの日本人移民の歴史は、最初の移民集団が農業定住者として到着した1936年までさかのぼることができます。最初の農業定住者134世帯がラコルメナに落ち着きました。なかにはもっと良い機会や仕事を求めて他の都市や国へ移った人たちもいましたが、マラリアの流行、自然災害、戦時中の社会、教育活動の制限などの困難に直面しつつもラコルメナにとどまった人達もいました。 戦後:日本人移民の流入 その次に日本人移民が多くパラグアイにやって来るようになったの…
日系メキシコ移民略史
2014年4月11日 • アケミ・キクムラ・ヤノ
1897年5月10日、最初の日本人移民がチアパス州でコーヒー農園を始めるためにメキシコに到着しました。この試みは失敗に終わりましたが、この移民達の多くは地元の女性と結婚し、メキシコへの日本人移民の礎を築きました。 この初期の移民達と異なり、1901年から1907年にかけてメキシコ北部から中部にやってきた日本人は主にデカセギ労働者でした。彼らは移民会社を通じて鉱山、鉄道、農場などと契約しました。この労働者たちの大部分はメキシコを足場にして米国へ再移民しました。これは1907…
日系チリ移民略史
2014年4月4日 • アケミ・キクムラ・ヤノ
1910年から1940年の間、チリに入国する日本人移住者の数は900人を超えることは決してありませんでした。専門職を持つ人やビジネスマン、近隣諸国から入って来る労働者など、チリにやって来た日本人の経歴は実に多彩でした。日本人が主に定住したのは硝石の豊富な北部と、中部のバルパライソとサンチアゴに多く集まりました。日本人はいろいろな職に就きました。サラリーマンになったり、小さな商売、特に散髪業に従事した人もいました。初期の移民は圧倒的に男性でした。日本人移民男性のほとんどはチリ…
日系カナダ移民略史
2014年3月28日 • アケミ・キクムラ・ヤノ
日系人の大部分は1890年代から1920年代にかけてカナダへやって来ました。最初に記録されている日本人のカナダ移民は1877年です。初期の移民は、ブリティッシュコロンビアで材木業や鉱業、漁業、農業などに従事しました。日本人のカナダへの移民は1905年から1907年にかけて頂点に達します。これが反日感情を大きく刺激することになりました。 日本人排斥の要求が通って、1908年に林=ルミュー「紳士協定」となり、日本人労働者は年間400人しかカナダに移民できなくなりました。それで…
日系ブラジル移民略史
2014年3月21日 • アケミ・キクムラ・ヤノ
日本人移民が初めてブラジルに到着したのは1908年のことでした。この時やって来た家族は、低賃金で働く労働者を求めていた農園経営者と結んだ契約のもとで、コーヒー農園で働きました。1924年に合衆国が日本人移民に対してその門戸を閉ざすと、日本政府は日本人のブラジルへの移民を促進しました。 でも、農園での生活はとても耐えられるようなものではなかったので、ほとんどの日本人は農園を去って、都会や郊外、または新しい日本人農業移住地へ移りました。サンパウロ市とその郊外が主な日本人移民の…
日系ボリビア移民略史
2014年3月14日 • アケミ・キクムラ・ヤノ
ボリビアに最初の日本人移住者が入国したのは1899年でした。それから約100年の歴史を刻んだボリビアの日系社会には、現在2つの異なる日系人 グループが存在しています。 その1つのグループは第二次世界大戦前に移住した日本人の子孫たちで、もう1つのグループは戦後に移住した日本人とその子孫た ちです。しかしいずれのグループからも、弁護士や医者などの専門職に就く日系人が誕生しています。 戦前の日本人移民 第二次世界大戦前にボリビアに入国した日本人の多くは、出稼ぎ労働者とし…
日系アルゼンチン移民略史
2014年3月7日 • アケミ・キクムラ・ヤノ
日系アルゼンチン人の歴史は1908年から1909年にかけて、沖縄と鹿児島から移民が到着したときに始まりました。 アルゼンチンではこの2県出身の日系人が多くいます。初めてアルゼンチンに着いた日本人はブラジル経由で入国しました。その後も、近隣の国へまず入ってからアルゼンチンへ入国する日本人移民が多かったのです。 戦前には、日系アルゼンチン人の大部分は都市部で小さな商売を営んでいました。特にブエノスアイレスでドライクリーニング業とカフェを営む人が多かったのですが、ほかに、奉…
一世の開拓者たち -ハワイとアメリカ本土における日本人移民の歴史 1885~1924- その26 (最終回)
2011年6月27日 • アケミ・キクムラ・ヤノ
>>その25一世の開拓者たち多くの一世たちにとって一時的であったはずのアメリカ生活は、いつの間にか10年、20年と長引き、アメリカへ来た頃の若さも過去のものとなってしまった。 青雲の夢も呆けて五十年1 なかには「金の成る木」を見つけて、成功して日本へ帰った者もいた。また或る者は、さらにチャンスを求めてメキシコや満州へ移住して行った。しかし、多くの者はアメリカに根を下ろし定住したのである。 住み馴れてアメリカ一番よいところ2 一世の多くは、遺骨を引き取…