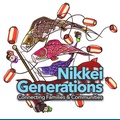サンパウロに生まれる。 サンパウロカトリック大学を卒業、経営学修士号を取得。現在は日本に在住し、キョウダイ・レミッタンスにてブラジルマーケットや日系ネットワークを担当するほか、法務翻訳や通訳などを担っている。弁護士としての資格も有しているが、財務責任者として活躍することを選び、日本では金融機関にてキャリアを全う中。スポーツ、特に走ることとサッカーが好き。コロナ禍に、ロードバイクに目覚める。
(2021年10月 更新)
この執筆者によるストーリー
第61回海外日系人大会の舞台裏
2021年12月29日 • 早田 幸太郎・アントニオ
2021年10月30日と31日の二日間に亘り、第61回海外日系人大会が「新時代への挑戦:時空と世代を超えてつながる日系」というテーマで開催されました。大会中、2018年にハワイで開催された大会で創設された記念日「国際日系デー」のシンボルマーク(ロゴマーク)が発表されました。 海外日系人協会が主催する海外日系人大会は、日本人移住者を受け入れてくれた国々の全般的な状況を日本政府に伝えると同時に、国際交流、国際理解、国際親善を深めることを目的としています。大会期間中、友人と…
私と日本語の関係
2021年10月13日 • 早田 幸太郎・アントニオ
日本人のルーツを持つ人のほとんどは、子供の頃から日本語やコロニア語に触れてきたと思います。これはブラジルの日系方言の一種で、ポルトガル語と古い日本語が混ざったもので、移民の出身地である日本の多くの地域(方言)の特異性や俗語が受け継がれています。その結果、どの本にも載っていない独自の方言ですが、私たちはお互いに非常に簡単に理解できます。日本人移民がいる他の国でも同じようなことがあるのか、とても興味があります。二世である私の両親は、最初から日本語学校に通わせたり、リベルダー…