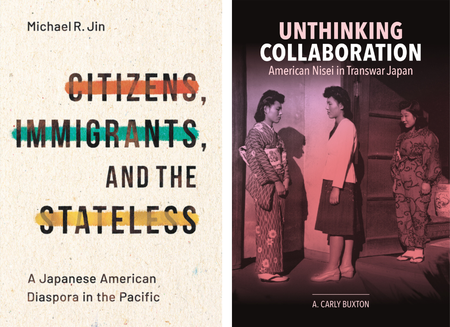私は、さまざまな意味で、自分はやや典型的な三世ではないと常に思ってきました。その主な点は、私の両親のうちの片方、つまり私の母は、戦前、戦中、戦後に日本でかなりの時間を過ごしたため、より「日本的」だったことです。その結果、私は日本に何人かの親戚と連絡を取り合っています。その中には、ハワイで生まれ育った二世の母の一番上の兄もいます。彼は第二次世界大戦中に日本軍に強制的に徴兵され、その結果米国市民権を失い、日本で一生を過ごしました。彼の「三世」の子供たち、つまり私のいとこたちは日本人です。
私の妻も似たようなもので、彼女にはトゥーリーレイクの反体制派だった叔父が二人いて、戦後アメリカ国籍を放棄して日本に渡りました。彼女にも日本人の「三世」のいとこがいます。そうそう、彼女の母方のいとこの一人はワシントン州タコマで生まれ育った二世の少女で、1937年に祖母の世話をするために日本に送り返され、アメリカに二度と戻ってきませんでした。彼女の日本人「三世」(この人たちを3回も言及しているので、この人たちを表す言葉を発明する必要があるでしょうか?)の娘は、世界中の平和博物館の著名な学者になりました。
日系アメリカ人研究をしている私の三世の友人や同僚の多くは、典型的な帰米(経済的および文化的理由により、子供のころに日本の親戚に育てられた二世)の両親を持ち、一方で、満州や日本帝国の他の辺境地で生まれた両親を持つ人、戦前に日本で大学に通っていた人、または被爆者(原子爆弾の生存者)の両親を持つ人(不釣り合いに多いように思われる)も知っている。
すると、次のような疑問が湧いてきます。私たちは実際には非典型的ではないのでしょうか?
2 冊の新刊、マイケル・R・ジンの 『Citizens, Immigrants, and the Stateless: A Japanese American Diaspora in the Pacific』と A・カーリー・バクストンの『Unthinking Collaboration: American Nisei in Transwar Japan』は、その質問に明確に肯定的に答えています。(情報開示: ジンはDensho Encyclopediaの寄稿者です。) ジンは、約 5 万人の二世 (全体の約 4 分の 1) が戦前に日本または日本帝国でかなりの時間を過ごしたと書き、2 人の著者は戦時中に日本にいた二世の数を 2 万人から 3 万 5 千人としています。ジンとバクストンは協力して、これらの二世の物語 (つまり私の家族の物語) は珍しいケースでも異常なケースでもなく、二世の経験全体の一部であり、たとえその一部がしばしば抑圧されてきたとしても、不可分であるという説得力のある主張を展開しています。
二人の著者は、タイトルが違いを示しているように、異なる補完的なアプローチをとっています。日本語と英語の幅広い資料を参考にして、ジンは、戦前の日本における二世に2章、戦時中の強制収容中の米国での帰米に2章、そして戦時中に日本に捕らえられた二世に2章を割き、このテーマについて広範かつかなり率直に概観しています。バクストンのアプローチは、最後のグループ、特に戦時中の日本帝国の臣民としての彼らの生活と、戦後直後の米国による日本占領下での米国人としての彼らの生活の矛盾に焦点を合わせた、より狭く理論的なものです。
ジンの戦前の章は、古典的な帰米グループだけでなく、家族全員で日本または日本帝国に移住した二世、米国で直面した人種差別に幻滅した一世の両親、または1930年代にさらなる教育を受けるため、または米国で限定されていた仕事よりも良い機会を提供してくれそうな仕事に就くために単身日本に渡った二世の若者など、他のグループも網羅している。ジンは、この二世グループをターゲットにした特別な学校やプログラムについて説明し、アメリカ人としてのアイデンティティを利用して日本である程度の名声を得た二世のフットボール選手やジャズ歌手についても言及している。ジンはまた、日本人と結婚し、ケーブル法によりアメリカ国籍を失った二世女性のケースを、二世の市民権をはく奪するより広範な取り組みの文脈で詳しく調べている。この戦前の時期に日本で二世が実際に経験したことについてもっと知りたいと思うだけだ。
真ん中の2章は、戦時中の強制収容所時代の米国での帰米について取り上げており、そのうちの1章は、帰米を主人公にした山崎豊子の悪名高い1983年の小説「 二つの祖国」と、それをテレビ化した日本のドラマ「 山河、燃ゆ」に焦点を絞っている。より一般的な章では、米国政府の調査官や収容所の管理者、そして日系アメリカ人コミュニティの一部にとって、帰米は一種の悪者のような存在だったと主張し、例えば、 ケネス・リングルとカーティス・マンソンによる日系アメリカ人コミュニティに対する「同情的な」調査でさえ、帰米を潜在的な問題として取り上げていたと指摘している。
しかし、ここで紹介されている強制収容所における帰米人の役割についての一般的な扱いは、少々表面的である。例えば、ジンは、1943 年初頭の西レバノン軍の収容所での登録をめぐる騒動で帰米人が大きな役割を果たしたと主張しているが、引用しているのはトパーズという 1 つの収容所からの報告書だけである。登録に関する話は収容所によって大きく異なり、帰米人の役割も異なっている。例えばハート マウンテンでは、登録に対する抵抗は二世が率いるグループ (アメリカ市民会議) から起こり、彼らは二世に対し、市民権が完全に回復されるまで登録を拒否するよう求めた。ジェロームなど他の収容所でも帰米人のグループは抵抗を主導した。ここでも、収容所での帰米人の生活の感覚が欠けている。ジンは、帰米人が自分たちをどう見ていたかよりも、他の人々が帰米人をどう見ていたかについて語っている。
最後の 2 つの章は戦時中について扱っており、1 つは戦時中に日本に捕らわれた二世のジレンマに焦点を当てており、もう 1 つは二世の被爆者についてである。確かに有益で洞察に富んでいるが、どちらも少し表面的な感じがする。前者は、1930 年代の日系アメリカ人市民連盟の指導者で、1942 年までに日本帝国主義の拡張を声高に応援する者へと変貌した村山保の物語を用いて、日本に閉じ込められた二世が「忠実な」日本人でなければならないというプレッシャーについて論じ、村山のような人々の見方を、反対の立場の マイク・マサオカの見方と比較することさえしている。しかし、日本軍に強制徴兵された二重国籍の二世については簡単に触れられているだけで、女性の経験については、 アイバ・トグリについて簡単に触れられている以外ほとんど何も触れられていない。奇妙なことに、日本に捕らえられた二世の中で最も悪名高いカワキタトモヤについては全く触れられていない。被爆者に関する章では、彼らの戦時中の体験よりも、 戦後、2つの国の間に挟まれた人々が医療を受けるのに苦労したことに焦点が当てられている。ジン氏は彼らを「戦後の国家によるケアと補償的正義の体制の中で本質的に無国籍者」と呼んでいる。
対照的に、バクストンの焦点は、戦中および戦後に日本で捕らえられた二世の経験に全面的に当てられているが、最初の2章では、戦時中の話に入る前に、米国と日本での二世の経験の背景を説明している。これらの章は、主に二次資料と、デンショウのアーカイブからの多くのものを含む口述歴史に頼っており、状況設定には優れているが、人種差別への対応として日本を受け入れるという年長の二世のリーダーたち自身のイニシアチブ(親や他の人からその観点を押し付けられたのではなく)については、おそらく過小評価している。第2章では、二世の「コードスイッチング」という概念を紹介している。バクストンはこれを「個人の生来の本物の側面ではなく、文化的パフォーマンスの練習」と定義し、二世が戦時中の日本で生き延びて戦後の生活に素早く移行できるようにするツールであるとしている。
彼女の戦時中の章では、日本社会のより広範な変化と、戦争遂行のために犠牲を受け入れるようすべての日本国民に圧力がかかった状況の中で、そこに閉じ込められた二世の経験を考察している。そうすることで、彼女は、第二次世界大戦中に日本軍に従軍した約3,000人の二世男性の詳細な記述や、二世女性の経験のより微妙な物語など、ジンの記述で残された多くのギャップを埋めている。彼女は、二世が他の外国人とは異なる扱いを受け、その多くが隔離され、抑留され、または投獄されたことを指摘している。これは、彼らが日本人の祖先であるため、帝国の臣民と見なされることを許されたためである。しかし、その特別な地位とともに、彼らの疑わしいアメリカ人性のために、二世には特別なプレッシャーがかかった。また、多くは、イヴァ・トグリの場合のように、生き残るための手段として英語力を活用した。
最後の 2 章では、終戦時に連合国占領軍が日本を占領し、予想を覆すような突然の変化が起こったことを取り上げます。戦時中はアメリカ人であることを隠していた二世たちは、アメリカ人であることを受け入れるよう奨励され、約 5,000 人が占領軍の仕事に就きました。
戦時中と同様、二世は「外国人」として中間的な地位にあり、日本人には手に入らない高給や食料、医薬品を利用できるものの、連合国国民ほどの特権は与えられなかった。彼女はまた、国籍を放棄した二世や国籍を失った人々のユニークなケースにも着目し、彼らは他の二世とのつながりや英語力による占領への有用性により、日本人に比べていくらかの恩恵を受けていたと主張している。
しかし、この忘れ去られた物語に注目を集めることに加えて、バクストンのより広い使命は、この時期の二世の「忠誠心」についての理解を再構築することであり、彼女はこれを明確には述べていないが、おそらく、ようやく薄れ始めているとはいえ、この集団にまとわりついている「不忠誠心」の汚名を取り除くことなのだろう。そうすることで、彼女はこの文脈における「協力」の意味を再考することを主張している。彼女は、二世の行動の説明として「忠誠心」に焦点を当てている人たちは見当違いであり、「忠誠心」は「決断の瞬間に個人の行動を正当化するために使用する枠組み」として理解するのが最もよく、実際の行動は「物理的環境、談話、懲戒権、経済的および対人関係の状況」など多くの要因に影響され、「忠誠心」はその中の1つの要素にすぎないと主張している。彼女は、コラボレーションをパフォーマンスとして再考すべきであり、「戦時中と占領下の日本におけるアメリカ人二世のコラボレーションのプロセスを並行させることで、コラボレーションが歴史的瞬間に埋め込まれたパフォーマンスであることが明らかになる」と主張しています。私自身、自分の家族の歴史を考えると、この問題については賛否両論ありますが、この視点は、日本の二世の経験を再考するための新鮮で非常に必要なものであると思います。
確かに、どちらの本にも問題点はある。ジンの場合、欠点は主に本の野心と範囲によるもので、将来の研究者が物語に付け加える余地を与えている。バクストンの本は一般読者には少々専門用語が多すぎるかもしれないし、所々で繰り返しがある。しかし全体として、どちらも二世の物語に対する理解を大きく広げる重要な作品だ。私たちの「非典型的」な家族のさほど大きくない集団を日系アメリカ人の歴史の主流に持ち込むのに役立ったジンとバクストンには感謝している。
※この記事は、2022年11月14日にDensho's Catalystに掲載されたものです。
© 2022 Brian Niiya / Densho