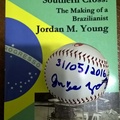兎追いしかの山 小鮒釣りしかの川
夢は今もめぐりて 忘れがたき故郷如何にいます父母 恙なしや友がき
雨に風につけても 思い出づる故郷志をはたして いつの日にか帰らん
山は青き故郷 水は清き故郷― 唱歌『ふるさと』
任期最後の年、3度目のトメアスー敬老会。トメアスー文化農業振興協会とアマゾニア日伯援護協会が中心となって行われ、多くの家族が一同に会して、地元のおもに日系一世である高齢者の健康と長寿を願う。ベレン領事事務所所長や振興協会会長などが挨拶をされ、日本語学校の生徒たちの歌、女性グループによるコーラスや日本舞踊など、いろいろな出し物が披露される。そして、トメアスー婦人会の手作り弁当も振る舞われる。
3度目にして初めて会を終了するまで見届けることができた。最後に参加者全員で記念写真を撮り、そのあと毎年恒例の「ふるさと」を合唱。全員で手をつないで円になって歌う。事前の打ち合わせなどはないのに、音楽が流れ始めると、全員が自然に輪になって隣の人の手を取る。私たちボランティアもいつの間にかその中にいた。幼いころから何度も歌い、慣れ親しんできた歌である。歌詞を見なくても言葉は出てくる。しかし、このときほど詞の意味を強く感じたことがあっただろうか。遠くを見つめて歌うみなさんの視線の先にあるもの。一つひとつの言葉がそこから紡ぎ出されるかのように感じられ、琴線に触れた。
「ふるさと」は、1914年に、高野辰之作詞、岡野貞一作曲による小学校唱歌として6年生の教科書に載せられて以降、日本全国多くの学校で歌われてきた。日本で小中高校時代を過ごした方なら、誰もが知っていると言ってもいいのではないだろうか。生まれ育った場所の風景をこの詞に重ねながら意味を感じ取り歌うことによって、育ててくれた親への感謝の念や故郷を愛する気持ちなどを育むという教育目的があるのだろう。私が育った町はこの詞にあるようなのどかな風景とは異なり、車と人が行き交う都市であるが、それでもこの歌を聞くと、今でも不思議とその町が思い出され幼少期のころが頭に浮かぶ。
しかし、敬老会で日本から移住された方たちが歌う姿は、私のそれとは異なる。ブラジルへ移住されてから、筆舌に尽くしがたい苦労をされてきたであろう。まだヨチヨチ歩きのころに家族に連れられて来た方、電気も水もない暮らしの中で辛苦に絶えざるを得なかった方、生きていくのが精一杯で学校には通えないまま大きくなった方、戦中の排日感情のあるブラジル社会で生きなければならなかった方、いろいろな経験をされてきた一世の方たちの心情を思うと、胸が熱くなる。
歌のあと、司会をされていた十字路アマゾニア病院事務局長の松崎康昭さんに感想を伝えると、「僕は7歳のときに来たからこっちで子ども時代を過ごしている。それでもやっぱり、『ふるさと』を歌うとかすかに記憶に残っている日本を思い出すし、なんとも言えない気持ちになるんだよ。こっちの生活のほうが長くなっても、みんなにとっては日本がふるさとなんだよ」と、とても優しい表情で話してくださった。私が歌う「ふるさと」とは違う「ふるさと」がそこにはあった。
「日本から来た」と言うとみなさん親切にしてくださり、昔話をいろいろと聞かせていただける。それは、私を通して日本を見ておられるからかもしれない。「日本」は地球の反対側にあるが、いつもみなさんの心の中にある「ふるさと」を、私との会話の中で少しでも感じてくださっていたらうれしい。おこがましいかもしれないが、そのお手伝いをすること、それもボランティアの役割なのかもしれないと思った。
© 2018 Asako Sakamoto