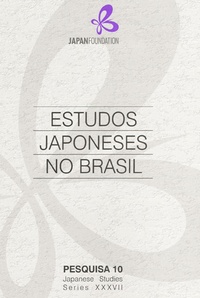No mês de abril foi lançado pela Fundação Japão de São Paulo a quarta edição dos “Estudos Japoneses no Brasil”, resultado da atualização e levantamentos de informações sobre os pesquisadores acadêmicos e centros de pesquisa no Brasil dedicados ao desenvolvimento de conhecimentos sobre o Japão e bibliotecas com acervo significativo de livros sobre a área de estudo.
Nesta nova edição registrou-se que essa área de pesquisa está em expansão no Brasil, com um significativo aumento no número de pesquisadores em relação aos dados da pesquisa divulgada em 1998. A publicação confirma o Brasil como detentor do maior contingente de pesquisadores de “Estudos Japoneses” na América Latina. As estatísticas da última pesquisa apontam que o crescimento foi de cerca de 39% no período de 1998 a 2007, passando de 95 para 132 pesquisadores acadêmicos ativos. A segunda maior concentração está no México, que de acordo com os dados da pesquisa desenvolvida pelo Colégio del México divulgados em 2006, com 41 pesquisadores.
O crescimento do número de pesquisadores no Brasil é um fato importante e muito positivo, pois consolida uma base de pesquisadores e multiplica o potencial de expansão, pois o trabalho de pesquisa acadêmica depende fortemente de professores que possam estimular e orientar novos alunos nos “Estudos Japoneses”. Portanto, o registro de 75 pessoas entre doutores (58), pós-doutores e livre-docentes nesta pesquisa é um elemento importante, na medida em que fortalece a capacidade de multiplicação de pesquisadores em “Estudos Japoneses” no Brasil.
Outro dado positivo é a diversificação de temas da produção acadêmica. Há desequilíbrios, por exemplo, as pesquisas em ciência política, direito, economia, filosofia e psicologia são desenvolvidas, ainda, por um número pequeno de pesquisadores. Contudo, o fato dos trabalhos acadêmicos estarem sendo desenvolvidos em diferentes áreas de conhecimento, contribui para uma produção ampla e diversificada que serve de apoio à consulta, ao intercâmbio, ao debate de informações e idéias.
A diversificação chama atenção também pelo número de pesquisadores não descendentes de japoneses, que chega a 31%, ou seja, só esse grupo já é superior aos 38 pesquisadores registrados vinte anos atrás na pesquisa de 1988, significando mais um sinal de consolidação da base de “Estudos Japoneses” no Brasil. O envolvimento crescente de não descendentes de japoneses na área é um fato importante, pois demonstra que é uma área de pesquisa aberta a todos que a ela quiser se dedicar e amplia a possibilidade de envolvimento de novos pesquisadores. Portanto, as expectativas por uma multiplicação de pesquisadores sobre os “Estudos Japoneses” no Brasil são grandes, pois, mais professores significa maior possibilidade de estímulos para que mais pessoas se envolvam no desenvolvimento de conhecimentos sobre o Japão.
Paralelamente à ampliação do número de pesquisadores, é de se esperar que haja uma redefinição da identidade dos “Estudos Japoneses” no Brasil. Até o final do século XX o seu desenvolvimento no Brasil era relacionado à numerosa comunidade no país, estimada em cerca de 1,3 milhão de imigrantes e descendentes de japoneses. Todavia, pelo menos dois elementos – a cultura e a língua - indicam que o futuro dessa área de pesquisa no Brasil não poderá mais depender das motivações dos pioneiros dos “Estudos Japoneses” no Brasil.
Dados empíricos apontam que os “Estudos Japoneses” foram desenvolvidos nos primórdios, pelo interesse dos imigrantes e descendentes japoneses no Brasil pela cultura, história e outros aspectos sociais de seus antepassados. Contudo, os descendentes de japoneses estão, cada vez mais, sendo assimilados e assimilando a cultura brasileira, assemelhando os seus interesses pelo Japão ao dos não descendentes. Portanto, os laços afetivos que foram importantes para impulsionar os “Estudos Japoneses” no Brasil durante boa parte do século XX se mostram insuficientes para a formação de pesquisas e pesquisadores sobre nessa área no século XXI.
Há um distanciamento das novas gerações de descendentes em relação aos imigrantes e, também, ocorre uma assimilação cultural. A cada nova geração o número de pessoas que necessitam dedicar-se ao estudo da língua japonesa aumenta, aproximando a realidade brasileira dos “Estudos Japoneses” a de outros países.
Esses fatores podem ser vistos como positivos, pois permitirão a constituição de uma nova identidade dos “Estudos Japoneses” no Brasil, que deverá ser mais estável, baseada não apenas na presença de uma grande comunidade de descendentes de japoneses no país, mas pelo crescente interesse de pesquisar o Japão. Um exemplo concreto da repercussão do desenvolvimento de interesse entre os pesquisadores é o do México, que contava com 41 pesquisadores em 2006, apesar da população de imigrantes e descendentes girar em torno de 12 mil pessoas. Esse é um resultado muito significativo se comparando com os 132 pesquisadores no Brasil, que detém uma comunidade de cerca de 1,3 milhão de imigrantes e descendentes.
Portanto, os resultados apresentados pela publicação têm um significado importante, ao revelar uma base multiplicadora que deverá contribuir para o crescimento do número de pesquisadores e para a continuidade da redefinição da identidade dos “Estudos Japoneses” no Brasil, motivada por profundos e renovados interesses.
* Associação Brasileira de Estudos Japoneses (ABEJ), afiliada ao Descubra Nikkei, contribui com este artigo para a Descubra Nikkei. ABEJ é uma organização sem fins lucrativos que congrega professores e pesquisadores de diferentes áreas de conhecimento sobre o Japão, especialistas,estudantes e pessoas interessadas em questões japonesas.
© 2007 Alexandre Ratsuo Uehara